
手続きの煩わしさから敬遠されることもある事業譲渡ですが、事業の存続・企業再生を懸けて選択する経営者は少なくありません。M&Aスキームとしての活用頻度は筆頭に挙げられるほどです。
この記事では、事業譲渡のメリット・デメリットと手続きや税金について解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

事業譲渡とは、会社の事業の一部、もしくはすべてを他の企業に譲渡する取引行為です。M&A手法のひとつですが、株式譲渡のように会社そのものが譲渡されるわけではありません。会社の営む事業のみが譲渡されます。
事業譲渡では事業のみを譲渡するため、雇用契約や一部の許認可については承継できなくなります。したがって、取引先や従業員に情報開示しながら個々と契約を結び直さなければなりません。譲渡する事業に関わる光熱費や通信費、賃貸借における名義、従業員の社会保険なども変更します。
これらの煩雑な手続きを経てもなお、事業譲渡する理由が存在するのも確かです。広げすぎたノンコア事業の縮小や新規事業立ち上げのための資金確保、あるいは経営者の引退後の資金確保などが理由として挙げられます。

事業譲渡が適しているケースについて、売り手側の場合についてご紹介します。
事業譲渡は、会社の一部事業のみを譲渡することで、会社の経営権は維持したまま経営再建を目指す際に適したM&Aの手法です。不採算部門を切り離したり、主力事業に経営資源を集中させたりすることで、事業の選択と集中が可能になります。
事業譲渡で得た対価は会社の資金として活用できるため、負債の弁済や残存事業の運転資金に充てることで、廃業の危機を回避できる可能性があります。
企業内に収益性の高い事業と低い事業が混在している場合、不採算部門を切り離すことで、経営資源を採算部門に集中させ、事業全体の効率化を図ることが可能です。不採算事業を譲渡することで、収益の改善や財務状況の健全化を実現できるため、事業譲渡は有効な選択肢となります。
事業譲渡が適しているケースについて、続いては買い手側の場合についてご紹介します。
買い手企業が特定の事業のみを引き継ぎたい場合、事業譲渡は非常に有効な選択肢です。事業譲渡は、必要な資産だけを選択して取得する方法であるため、簿外債務などの引き継ぎたくない負債やリスクを避けられる点がメリットです。これにより、買い手は安全な形で事業を拡大でき、既存事業とのシナジー効果も期待できます。
事業譲渡は企業全体を買収する株式譲渡などと比較して、事業を譲受する際に必要な資金を抑えられる点が特徴です。例えば、中小企業やスタートアップ企業が事業拡大を図る場合、資金的な制約がある中で、特定の事業に絞って投資できるため、効率的な成長戦略を実現できます。
事業譲渡では、買い手が事業に関連する資産や負債を個別に選択できるため、売り手企業の簿外債務などを引き継ぐリスクを避けたい場合に適しています。これにより、買い手企業は不要なリスクを負うことなく、必要な事業のみを取得することが可能です。
特定の事業のみを買収できるため、買収後の財務的なリスクを軽減できる点が買い手にとって大きなメリットとなります。
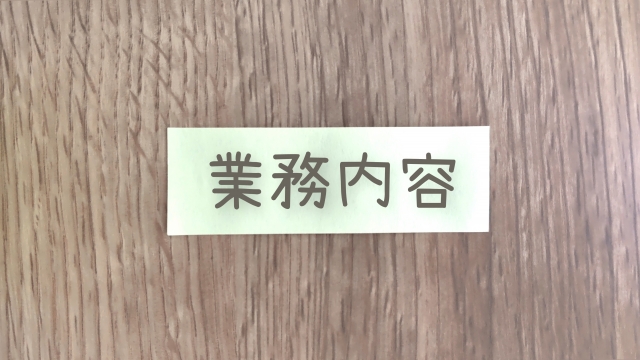
事業譲渡には売り手にも買い手にもメリットがありますので、どんな利点があるのかそれぞれの立場からご紹介します。
売り手にとってのメリットは以下になります。
事業譲渡は、会社の一部事業のみを譲渡するM&Aの手法であり、会社の経営権を維持できる点が大きなメリットです。株式譲渡のように会社全体を売却するわけではないため、オーナー個人が会社に愛着を持ち、経営を続けたい場合に適しています。
事業の一部を譲渡することで、残った事業へ経営資源を集中できます。不採算事業の切り離しは、健全な経営状態を保つために有効です。譲渡により得られた対価を、会社の財務基盤強化や成長分野への投資に充てることで、企業全体の競争力を高めることにつながります。
買い手側にとってのメリットは以下です。
事業譲渡は、買い手が譲受したい事業を選択できるため、特定の事業に必要な資産や負債、人材や設備、ノウハウなどを限定して引き継ぐことが可能です。例えば、新規事業の立ち上げを検討している買い手企業が、必要な部分のみを譲受することで、投資コストを抑えながら短期間での事業展開が期待できます。
売り手企業の全体を買収する場合と比較しても、買い手はコストを大幅に抑えることが可能です。
事業譲渡とは、買い手が事業に関連する資産や負債を個別に選択して引き継ぐ方法のため、不要なリスクを抑えて譲受できる点がメリットです。例えば、株式譲渡の場合、買い手は売り手企業の簿外債務や訴訟リスクといった企業全体のリスクを承継することになります。
しかし、事業譲渡は引き継ぐものを限定できるため、買い手は想定外の債務を負うリスクを避けることができます。特に中小企業のm&aでは、過去の財務状況が不透明なケースも少なくないため、買い手にとってリスクコントロールができる点は大きなメリットと言えるでしょう。
事業譲渡において、買い手企業は税務上のメリットを享受できる場合があります。事業譲渡では、譲渡の対価と譲渡対象事業の資産・負債の差額が「のれん」となります。この「のれん」とは、売り手のブランド力や技術力などの無形資産を指し、買い手側は税務上、これを5年間で償却し、損金として計上することが可能です。 この「のれん」の償却によって、買い手は節税効果に期待ができます。
一方、株式譲渡では、この「のれん」に相当する金額を損金として計上することはできません。

事業譲渡にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。売り手・買い手の立場からご紹介しますので、事業譲渡をお考えの場合には事前にデメリットも把握しておきましょう。
売り手にとってのデメリットは以下です。
事業譲渡では、株式譲渡のように包括的な承継ではなく、個別の資産や契約を移転する手続が必要です。例として、取引先との契約や賃貸借契約、従業員との雇用契約など、事業に関連するあらゆる契約を個別に引き継ぐ必要があります。
そのため、関係者への説明や交渉、そして個別の手続に時間を要し、複雑になる傾向があります。
事業譲渡における売り手側のデメリットとして、譲渡益に対する税負担が高くなる点が挙げられます。
事業譲渡で得た益金には法人税、事業税、地方法人税、法人住民税が課せられ、これらの実効税率は約30~35%です。一方、株式譲渡で個人株主が株式を売却して得た譲渡益に対する税率は約20%であり、事業譲渡の方が税負担が重い傾向にあります。
また、事業譲渡は譲渡対象が法人であるため、売却によって得た利益が直接法人に入りますが、この益金を売り手の役員へ還元する際には、配当や役員報酬として追加の税負担が発生する可能性もあります。
そのため、事業譲渡を検討する際は、譲渡益の計算だけでなく、税務面での詳細なシミュレーションが非常に重要です。適切なスキームを構築するためにも、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
事業譲渡後、売り手は競業避止義務の対象となることに留意が必要です。これは、譲渡した事業と同じ事業を、同一市町村および隣接する市町村の区域内で、20年間行うことが禁止されることを意味します。
この競業避止義務は、売り手にとって重要な留意点であり、期間や範囲について慎重に検討する必要があります。
買い手にとってのデメリットは以下になります。
事業譲渡においては、買い手側に消費税が課せられる点が特徴です。
譲り受ける資産の中には、土地や有価証券などの非課税資産もありますが、それ以外のほとんどの資産に対して消費税が発生します。負債の譲受には消費税はかからず、資産の金額に課税されるため、負債を差し引いた金額ではなく、譲受資産の合計金額が課税対象となります。
特に、営業権や「のれん」といった無形資産も消費税の課税対象となるため、譲受の際は、これらの金額に消費税分も加味して資金計画を立てる必要があります。
事業譲渡では、譲り受ける事業に関する様々な契約や名義変更の手続に時間がかかる点がデメリットです。
例えば、従業員との雇用契約や取引先との契約を再締結する必要があり、不動産の名義変更なども発生します。これらの個別の手続は、事業譲渡全体の流れを複雑にし、完了までに長い期間を要するリスクがあります。
特に、事業運営に必要な許認可の再取得には時間がかかり、事業開始が遅れる例も少なくありません。このリスクを最小限に抑えるには、事前の準備と専門家のサポートが重要です。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

M&A手法には事業譲渡の他に株式譲渡や合併吸収、会社分割などがあります。
もっとも頻繁に行われているのが事業譲渡で41%、次いで株式譲渡が40.8%です。少し開いて15%が合併、その他に会社分割や株式移転などが選択されています。それぞれに条件が異なりメリット・デメリットもありますが、業種や経営状況、そして何を目的としたM&Aであるかによって選択されます。
事業譲渡と株式譲渡の最大の違いは、売却する対象です。事業譲渡は事業(仕事)を売却しますが、株式譲渡は株式(資本)を売却します。したがって、事業譲渡では一部、もしくはすべての事業が移動したとしても会社自体は存続し、独立して経営を続けられます。譲渡益は会社の収入となり、法人税などの課税対象です。
対して、株式譲渡では資本が移動するため、買い手企業が過半数の株式を取得することで、事実上、経営権も買い手企業に移ります。 売り手企業は会社として存続しますが、買い手企業の株主が株主総会の意思決定を行えるようになります。
資本の移動に伴う譲渡益は株主のものとなり、個人の株主であれば所得税、住民税、復興特別所得税が、法人の株主であれば法人税等が課税されます。
事業譲渡も会社分割も事業の再生を図る再編の目的で行われるM&A手法です。
しかしながら、事業のみを売買する事業譲渡に対し、会社分割の場合は事業に関わる資産や権利義務なども包括的に移動し、組織の再編が行われます。会社分割は、事業譲渡と比較して手続きが容易な点や、株式での取引が可能なことからグループ企業の再編のために用いられることが少なくありません。
会社分割の定義は既存の会社を別の会社、もしくは新設する会社に分割することであり、2000年の商法改正で設けられました。事業譲渡が事業のみを移動するのに対し、会社分割では事業に付随する資産や負債、従業員や取引先との関係も包括して移動します。
会社分割には、新しく会社を設立する新設分割と、その事業に特化した会社に吸収させる吸収分割があります。
会社分割のために新しく会社を立ち上げて、事業の一部またはすべてを、事業に付随する資産や権利義務と共に移動させるのが新設分割です。元会社に負債や担保となる不動産などを残し、好調な事業だけを新設会社に移動して企業再生を図る例などがあります。
その名の通り、会社の事業の一部を他の会社に吸収させるM&A手法のひとつです。事業譲渡や吸収合併と酷似していますが、一部事業であることと事業に付随する権利義務の移動がある点が異なります。不採算事業のみを切り出し、その事業に特化した好調な企業に吸収分割させることにより会社のスリム化を図るケースなどが見られます。
合併とは、2つ以上の会社がひとつの会社になることです。既存のどちらかの会社が消滅し1社に吸収される吸収合併と、2社共に消滅し新しく1社を設立する新設合併があります。会社が消滅する点で、既存の会社の存続再生を目的とする事業譲渡とは根本的に異なるといえるでしょう。
基本的に事業譲渡は事業のみが移動しますが、合併では、会社分割などと同様に付随する資産や権利義務関係も合併会社のものとなります。
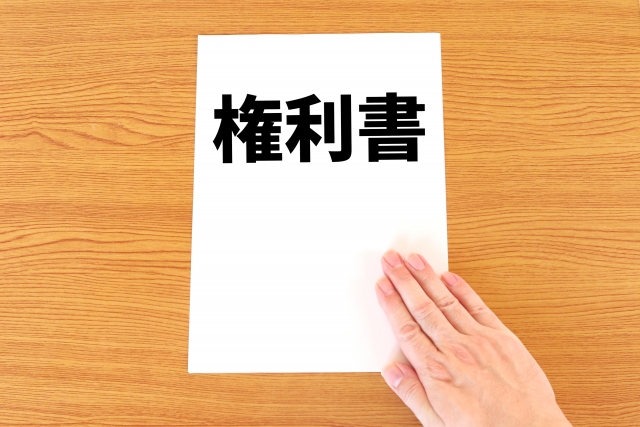
事業譲渡は、譲渡対象となる事業に含まれる資産や負債、各種契約などを個別に移転させるため、多くの手続きと時間を要する場合があります。ここでは、事業譲渡を進める上で必要となる主な手続きの流れについてご紹介します。
事業譲渡を進めるにあたり、売り手企業は原則として取締役会決議と株主総会の特別決議が必要です。
買い手企業は、事業譲渡によって自社の総資産の5分の1を超える対価を支払う場合などに株主総会の特別決議が必要となりますが、原則として取締役会決議のみで進められる場合もあります。これらの決議では、会社法に基づき、譲渡対象となる事業の範囲や対価、従業員の処遇、取引先との関係維持など、M&Aに関する重要な条件が検討されます。
特に、会社法362条4項1号に定められた手続きに則り、取締役会が事業譲渡の必要性と条件を正式に決議し、株主総会への諮問方針を決定します。売り手企業と買い手企業は、それぞれ自社の株主への影響や、従業員への説明、取引先との調整など、多岐にわたる項目を精査し、適切な手続きを進めることが求められます。
売り手企業と買い手企業は、譲渡対象となる事業の範囲や対価の金額、支払いのスケジュール、資産や負債、契約の移転手続など、事業譲渡に関する具体的な内容を盛り込んだ契約書を締結します。この契約には、従業員の雇用継続に関する条件や、売り手による競業避止義務の有無と範囲についても詳細に定めることが重要です。
また、株主総会の開催予定日や、その他必要な手続のスケジュールも契約書の内容として含めることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
事業譲渡を行う際、会社法では原則として、効力発生日の20日前までに株主への通知、または公告による開示が義務付けられています。
これは、事業譲渡が株主にとって重要な意思決定を伴うため、十分な情報提供期間を確保し、株主が適切に判断できるようにするためです。適切な通知方法で株主へ情報を開示するようにしましょう。
事業譲渡に反対する株主は、会社に対し、保有する株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。この買取請求は、効力発生日の20日前から効力発生日の前日までの期間内に行う必要があります。
反対株主からの株式買取請求は、売り手と買い手双方にとって重要な手続きであり、適切な価格設定が求められます。
売り手企業が事業譲渡を行う際、原則として株主総会における特別決議が必要です。
これは、事業の全部を譲渡する場合や、譲渡する事業の資産が売り手企業の総資産の5分の1を超える場合に義務付けられています。この特別決議には、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。
この手続きは、買い手側にとっても同様に必要となる場合があるため、双方の企業が連携してスムーズに進めることが重要です。
事業譲渡の買い手側は、事業譲受の対価が譲受企業の純資産の5分の1を超えない場合、「簡易事業譲受け」として株主総会の特別決議が不要になります。この際、売り手側の反対株主による株式買取請求権も発生しません。
ただし、事業譲渡は個別の契約や許認可の取得、従業員の退職・再雇用といった様々な手続きを伴います。譲受対象に従事する従業員の雇用契約は、売り手企業を退職し、買い手企業へ入社する手続きが必要となります。また、事業に必要な各種契約関係の移転や許認可取得に向けた準備も重要です。
略式事業譲渡の場合、親会社が子会社の議決権を90%以上保有している場合、子会社側の株主総会は省略できます。これらの手続きを適切に進めることで、スムーズな譲受が実現可能です。

事業譲渡にはさまざまな費用と手数料、税金が発生します。
費用として大きな位置を占めるのが、専門家に支払う事務手数料や仲介手数料、許認可料などです。また、事業の売買に関して売り手企業・買い手企業共に税金が発生することにも留意しておきましょう。
事業譲渡の売り手には法人税が課せられます。法人税とは、法人の所得に対して課せられる税金です。
事業譲渡によって売り手である法人が得る譲渡益は、所得として計算され、法人税の課税対象となります。譲渡益の計算方法としては、譲受側(買い手)から得た対価の金額から、譲渡対象となる資産や負債の簿価を差し引くことになります。
例えば、売り手から譲受側へ契約が移るケースでは、売却金額と譲渡対象の資産や負債の損益を計算し、譲渡益を算出します。この譲渡益に税率を乗じて法人税を計算します。また、売り手である法人が株主や役員といった個人に対価を還元する場合には、追加で税負担が生じる例もあります。
事業譲渡における消費税の計算方法について解説します。売り手は、譲渡する事業に含まれる課税対象資産に対して消費税を計算し、買い手からその税金を徴収して納税します。買い手は、売り手へ支払う譲受対象の消費税を負担しますが、この際、全ての資産が課税対象となるわけではありません。
具体的には、土地や株式、売掛金などの債権は非課税資産として扱われます。一方、棚卸資産(商品など)や営業権、その他の有形・無形固定資産は課税対象となります。
消費税の計算は「課税対象資産の金額に10%を乗じる」方法で行われ、売り手はこの計算内容に基づき税金を算出します。買い手側は、譲受資産の合計金額に対して消費税を考慮して資金計画を立てる必要があります。
事業譲渡を始めとするM&A費用で大きな割合を占めるのが仲介手数料です。仲介手数料とは、M&A仲介会社が仲介を請け負った時点から発生するさまざまな手数料の総称ですが、仲介業者によって設定が異なります。
事業譲渡の取引価格は双方の企業の合意で進めることも可能ですが、事業価値の算定には客観性が必要です。そのため、専門家の企業価値評価によって算出された事業評価を参考にするケースは珍しくありません。その費用を企業価値評価費用といい、事業規模によって異なりますが概ね50万円程度が相場となっています。
その後、交渉過程の活動費や人件費として月毎に発生する月額報酬、基本合意書締結時に発生する中間報酬を経て、最終的な制約段階に至って成功報酬が支払われます。成功報酬は仲介手数料のうちもっとも大きな割合を占め、取引価格にレーマン方式の科率を乗じて決めるのが一般的です。
M&A仲介会社への手数料は、依頼する会社によってさまざまです。中には相談・着手金無料の仲介会社もあるので、いくつかの候補から選ぶことをおすすめします。
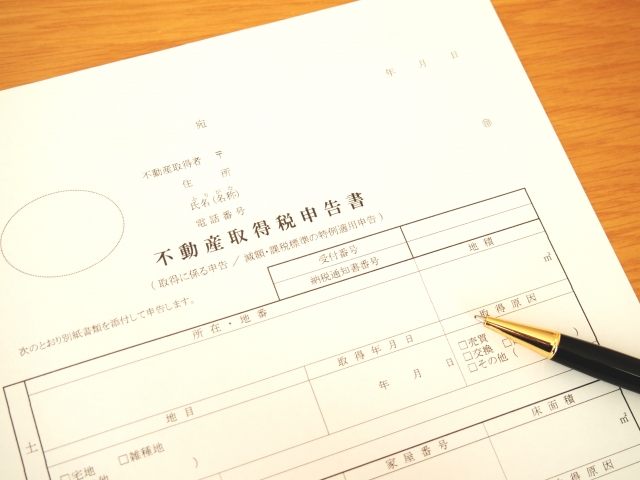
事業譲渡によって不動産を引き継ぐ場合、買い手は不動産取得税を支払う必要があります。不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される地方税です。この税額は、原則として不動産の評価額に対して課税されます。不動産取得税の税率は、土地や住宅では3%、住宅以外の建物では4%と定められています。
不動産を事業譲渡によって引き継ぐ場合は、対象となる不動産の登記が必要になり、この際に登録免許税が課されます。登録免許税は、譲渡される不動産の固定資産税評価額に対して一定の税率を乗じて算出されます。この税金は、不動産登記を行う際に法務局へ納付する国税です。

事業譲渡を行う際には起こりうるトラブルや、失敗しないために事前に取り決めておくべきことがいくつかあります。以下の留意点を確認し、事業譲渡の際には注意してください。
後々のトラブルを避けるために何を譲渡対象とし、何を除外するかを明確にしておく必要があります。
契約書に「事業に関するすべてを譲渡する」と記載するよりは、譲渡項目を個別に列記するのが望ましいでしょう。そうでなければ「関連するすべて」から除外項目を列記する方法をおすすめします。
包括的な記載は誤解を招きやすく、債権者や取引先との間でトラブルが発生しかねません。
譲渡対象となる事業の価格は、事業譲渡の契約日の財産の評価額を基準に算定されることがほとんどです。客観性を保つために専門家や仲介会社へ協力を要請するのが望ましいでしょう。
事業譲渡でもっともデリケートなのが従業員との関係です。会社法625条1項によると、雇用契約に基づく使用者の移転には、従業員の同意を得なければならないと規定されています。事業譲渡開始日までに、売り手企業・買い手企業共に、従業員の同意を取り付けなければなりません。
具体的には、売り手企業を退職し、買い手企業に再就職する形になりますが、その際も同意が必要です。譲渡契約書には、退職と再雇用の旨を明記し、退職金や未払金などの処理についても定めておくことをおすすめします。
会社法467条、および309条には株主総会の特別決議の必要性が記されています。譲渡する資産が双方の純資産の5分の1を超える場合、それぞれの株主総会において承認を得なければなりません。株主への告知は20日前までに、株主総会の特別決議は譲渡実行開始の前日までに行う必要があります。
会社法21条1項に定められているのが「競業避止義務」です。事業譲渡した企業は、以後20年間は同一地区および隣接市町村において同じ事業を行うことができないとされています。さらに2項には特約義務として30年間の効力持続が定められています。
ただし、双方の企業が同意すれば「競業避止義務」を負わないとすることも可能です。「競業避止義務」を負うか負わないか、負う場合の期間などを明確にしておく必要があります。
事業譲渡における情報開示をどの段階でどの程度まで広げるかには、慎重な判断を要します。
従業員や関係機関、取引先への情報開示は契約成立後に必要ですが、事前相談せざるを得ないケースもあります。しかしながら、あまりに早い段階で告知してしまうと情報漏洩につながり株価が低下、業績が悪化する可能性も否定できません。そうなると、会社経営は厳しさを増し、譲渡対価も下げざるを得なくなります。
また、従業員や取引先に早い段階で知られてしまうと離職や反対運動が起こったり、取引停止となったりすることもあります。情報管理には細心の注意を払い、相談する場合にも信頼できるキーパーソンに対し、慎重に手順を踏んでいくことが必要です。

企業の事業承継問題を危惧した政府が事業承継に関する税制優遇措置を発表したのが2018年でした。それを受けて活性化したM&Aですが、コロナ禍による経済危機がいっそう拍車をかけたのはいうまでもありません。いくつかの事例を案内します。
武田薬品工業は数多くの製薬ポートフォリオを保有し、新しい薬品を製造すると特許期間中に集中的に販売するビジネススタイルを取っています。特許期間を過ぎた薬品に関してはジェネリック薬品との競合になり大きな利益が見込めなくなるため、絶えず入れ替えを行います。その一環としての2型糖尿病治療薬4製品の販売事業譲渡が発表されたのは2021年2月のことでした。
買い手となったのは帝人ファーマ、4製品の製造販売承認権を担うという発表です。流通売却額は1,330億円で、武田薬品工業の特別利益は1,300億円といわれています。
参考
https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2021/20210226-8242/
オンキョーホームエンターテイメントが、アメリカの音量機器大手のウォックスとシャープへ家庭向けのAV事業を売却すると発表したのは2021年5月26日のことです。33億円で売却されました。生産はシャープが担い、販売はウォックスが中心となり展開します。この事業譲渡によりオンキョーは車載向けシステム事業のいっそうの充実を図ります。
参考
https://maonline.jp/articles/tsr0319-onkyo2
2015年5月25日、サントリー食品インターナショナルは日本たばこ産業(以下JT)の飲料自販機事業の買収を発表しました。JTの「桃の天然水」と缶コーヒー「ルーツ」のブランドも取得します。これによりサントリー食品の自販機は約63万台になり、首位を走る日本コカ・コーラグループに近づきます。
自販機による飲料の売り上げは全体の3割程度ですが、自販機の設置場所により大きな差があるのが現実です。その点、JTの自販機はオフィスビル内など利用頻度の高い場所に設置されているものが多く、収益力の強化を期待されています。
参考
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ25HVZ_V20C15A5MM8000/
手続きの複雑さや税金・手数料などのデメリットがありながら高い頻度で行われているのが事業譲渡です。それはメリットの方がはるかに大きいからに他なりません。事業を選択できるメリット・負債を回避できるメリット、何より金銭的なメリットが大きなウエイトを占めます。これらのメリットを生かすにはスムーズな交渉締結が大切でしょう。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください