
買収と聞くとあまりいいイメージがありません。政治家の買収事件のような用例が思い浮んでしまいますね。
M&Aにおける買収は、一般的に用いられる非常にメリットの多いスキームです。
この記事では、買収の概要と目的やメリット・デメリット、どんなケースで有効なのかなど、くわしく解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

会社はその株式の過半数を取得すると経営権を掌握できます。この仕組みを利用して株式を取得することで他社の経営権を掌握するM&A手法を企業買収と呼びます。また、経営権ではなく、一部の事業のみを譲り受ける場合もあり、これは事業買収と呼びます。この2つに大別されるM&Aスキームを総称して買収と呼びます。
企業買収の場合、過半数の株式を取得すると役員の選任などの普通決議を自由にでき、日常的な事業運営はほぼ掌握できます。これを子会社化と呼びます。さらに2/3以上の株式を取得すると定款変更や組織再編も可能な特別決議を自由にでき、少数株主の強制排除(スクイーズアウト)も検討可能です。
合併は複数の会社を1つに統合するM&Aスキームです。ある会社を別の既存の会社と合わせる吸収合併と、新しく設立する会社に複数の当事者会社を合わせる新設吸収があります。買収との大きな違いは、合併によって法人格を失う会社(消滅会社)があることです。買収では、被買収企業は買収相手の傘下には入りますが法人格は失われません。
ちなみにM&A(Mergers & Acquisition)は日本語に訳すと「合併と買収」となります。合併は買収と並ぶM&Aの手法であることが明確に示されています。M&Aという用語には、広義には業務提携や資本提携なども含まれていることには注意が必要です。

企業買収にせよ事業買収にせよ、相対売買で行われるとは限らず、必ずしも合意の上で買収が進むわけではありません。特に売り手側が買収に同意しているかどうかは重要で、売り手が同意していない場合を敵対的買収、同意している場合を友好的買収と呼んで区別します。それぞれについてくわしく見ていきましょう。
敵対的買収は売り手の同意が得られていません。売り手が同意していないのになぜ買収ができるのでしょうか?それはTOB(株式公開買付)の手法を利用するからです。この手法は上場企業でないと用いられません。非上場会社は、多くの場合譲渡制限付きの株式になっており、相対でしか取引できず、敵対的買収はほぼ不可能です。
TOBは、不特定多数の者に公告で株式の買い付けまたは売り付け等の申込みについて勧誘し、市場外で株式買付け等をする行為と規定されています。(金融法第27条の2、6項)敵対的買収はこれを利用して議決権株式の過半数を取得し、被買収企業の同意なく経営権を奪取しようとするものです。
被買収側も甘んじてこのTOBを看過するわけではありません。一般的に買収防衛策を講じてこれを阻止しようとします。主な買収防衛策を挙げてみます。
会社の重要な資産等を友好的な第三者に売却してしまい、買収目的である企業価値を引き下げてしまいます
例えば取締役の解任を特別決議によるものとしたり、合併等の決議をより重い要件の必要な決議としたりする定款改正を行い、買収者による経営権掌握を難しくさせます
買収者の取得株式が一定割合を超えたら、買収者には行使不能の新株予約権を他の株主に無償割り当てして過半数の取得を阻止します
取締役変更などの重要議題の議決に関する拒否権を友好的な株主に付与して買収者の議決権に制限をかけてしまいます
自社に友好的な会社に対して、先に会社を売却したり合併したりしてしまいます
株式の上場を廃止してTOBが仕掛けられないようにします
買収者の会社に対して、逆に買収を仕掛けて対抗します
売り手側にもメリットがあれば、その同意に基づいて買収を行えます。この友好的買収は、売り手買い手双方の条件交渉などを経て、株式譲渡、または事業譲渡の形で行われます。
非上場会社では交渉による相対取引が必須ですからほぼ友好的買収の形となります。上場会社ではTOBの形で行われることもありますが、売り手側もこのTOBに同意し協力することになります。
売り手の同意の有無以外にもこの2つの買収には違いがあります。なんといってもそのコストと労力が違うのです。敵対的買収は売り手の同意を得ていないぶん、競合的な株式買い取りにならざるを得ず、どうしても単位あたりの株式の取得価額が高くなりがちです。また防衛策などを講じられればさらにリスクも大きくなります。
円滑にことが進む友好的買収に比べ、敵対的買収の成功率はかなり低くなります。このような違いから、日本におけるM&Aでは友好的買収がほとんどで、敵対的買収は非常に稀といえます。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

2020年はコロナ禍の渦中にあって、経済は停滞していました。しかしその間にあっても年間のM&A件数は3,730件に及び、これは2017年にそれまでの最高を記録した3,080件を大きく上回っています。なお、2019年には4,000件を超え過去最高を更新していました。(以上、レコフデータ調べ)
昨今、国内においてM&Aが盛んに行われている主な理由は4点が考えられます。
どの理由も一時的なものではなく、今後も継続する事由が並びます。したがって、M&Aやその手法としての買収は今後も活発に行われていくと考えられます。
特に中小企業の後継者不足は深刻です。中小企業庁発表の「中小M&Aガイドライン」によると、2025年までに245万人の経営者が70歳を超え、その半数の127万人程度が後継者がいない見込みが示されています。同庁発表の「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」には、2018年には2012年から増加傾向だった事業承継型M&Aが544件に達したと報告されています。
この中小企業の事業承継先として、事由の1つ目の大企業の拡大ニーズや、同じく4つ目の海外企業の投資などがマッチすることで、一層加速することも考えられます。

買収は、かんたんにいえば事業の拡大と会社の成長を意図するものです。しかしその目的とするところを詳細に見ていくと、主に5つあるといえます。
一般的に経営リソースと考えられているものは6つあります。
会社の成功は、最終的には売り上げや利益として資金的なもので測られます。しかし、資金だけを溜め込んでいったところで、それは次の資金を生み出しません。すなわち、残る5つのリソースを獲得し、さらなる資金を生むための投資を行うわけです。買収はこうした投資の有効な方法の一つと考えられます。
買収によってさまざまな経営リソースを獲得したとき、相乗効果が得られます。これをシナジー効果と呼び、M&Aの大きな目的となります。
例えば買収によって売り上げや事業エリアなどが拡大します。すると生産部門において大量仕入れが可能になりコスト削減が見込めます。また販促面でも効率化が可能となりここでもスケールメリットによるコストシナジーが得られます。結果的に業界シェアは単なる足し算以上に拡大することが見込めるわけです。
また優秀な人材リソースの獲得や、技術面での生産性向上も見込めます。今までアウトソーシングしていた部門で内製化が進めば、生産性の改善や開発力の向上が見込めますし、コスト面でも大幅な削減が期待できます。
こうしたシナジー効果は大企業のみに起こることではありません。ある程度の事業規模を獲得すれば、こうしたシナジー効果をより有効的に得られる見込みがあります。この考え方から、規模の小さな同業者を複数買収して経営資源の共有化と収益性向上を図る手法を特にロールアップと呼びます。
買収は必ずしも対外的に行われるとは限りません。企業グループ内の、いわゆる身内での買収も頻繁に行われます。これは単純な事業拡大を目指しているわけではなく、企業グループとしての組織再編を企図するものです。
似たような企業が乱立したり、グループ企業の数が増えすぎたりして、効率的な経営戦略の妨げになることがあります。こうした場合にそれらを買収によって整理、統合することで事業の効率性を上げることは有効な経営戦略です。こうした場合には株式交換や株式移転などのスキームがよく用いられ、必要に応じて合併や会社分割なども用いられます。
単一の事業で会社を経営するのはなかなかにリスキーです。社会的な変化や業界の規制強化などで、一気に業績悪化の可能性があります。ある程度の事業規模を持つ会社であれば、そうした悪影響をこうむる従業員等の関係者も多くなります。こうした事態を避けるリスクヘッジとして、事業を多角化していくことは重要な経営戦略です。
複数の事業を並行して手掛けることで、企業としてのリスクを分散化できます。しかし、未参入の事業を展開し、販路を獲得して利益を上げていくことはなかなかに困難なことです。買収を行うことで、すでにその事業を手掛けている企業をまるごと手に入れることが可能です。そうなればすぐにでも新規事業に参入し、事業の多角化が実現できるわけです。
買収が税金対策を目的に行われるというのは少々意外かもしれません。しかし、赤字企業を買収した場合、その繰越欠損金の引き継ぎによって利益を低減し、法人税などの節税になる場合があります。税負担が大きくなっている大企業などにあっては、この節税による経営効果は馬鹿になりません。
ただしこの繰越欠損金だけを目的にした買収は、損金算入に制限がかかるという規定があり、注意しなければなりません。また連結納税を導入している場合にも利用条件が限られることがあります。

一言で買収といっても、実は多様な手法(スキーム)が含まれています。売り手、買い手、双方の事情やビジネス面での影響、税の負担や買収の主目的などによって、最も効果的と思われるスキームを選択することが一般的です。5つの主な手法について解説します。
株式譲渡は、売り手企業の株式を買い手企業が対価を支払って譲渡を受けることによって、売り手企業の経営権を掌握する手法です。あるM&A仲介会社によると、扱う案件の9割程度がこのスキームで行われ、中堅や中小企業のM&Aで特に多く用いられています。売り手企業は経営者が変わること以外に影響を受けないのが特徴です。
この手法が多く用いられるのはその手続きの簡便さにあります。大雑把にいえば売り手企業と買い手企業間で株式譲渡契約を締結した上で、買収価額にあたる対価が支払われ、株式を譲り受けることで成立します。基本的には当事者間における売買取引となるわけです。株主総会の承認や債権者保護手続きも必要ありません。
少なくとも議決権株式の過半数を取得する必要があります。これでも普通決議は自由に行えるので、経営権をほぼ掌握できるからです。しかし、特別決議までを自由にすることを考えて、2/3以上の議決権株式の譲渡を受けることが一般的です。
売り手企業がそのまま残るため、PMI(経営統合)は困難で、シナジー効果が出にくいのはデメリットです。また経営権をまるごと承継するので、簿外債務などのリスクも引き受ける可能性があります。売り手側には対価を所得とした所得税や住民税(会社が受け取り手なら法人税)が発生します。
株式譲渡では主に3つの方法で取引が行われます。以下に紹介します。
売り手企業が非上場会社の場合はこの方法で行われます。読んで字のごとく、売買の当事者間で相対して株式数やその価額、対価の支払い方法を協議して決定します。市場に出回っていない非公開株式ですので、取引所を経由しない直接取引となるわけです。実務上、証券会社に取引を委託して手数料を支払うケースもよくあります。
売り手企業が上場会社であれば、市場で株式が取引されています。当然この株式を必要な数量買い集めれば買収は成立するわけですが、実際にはほとんど実施されることはありません。市場で取引対象になっている株式数が限定されていることや、市場価格の変動の影響で買収価額の見込みが立ちにくいことなどがその理由です。
公開買付け(TOB=Take Over Bid)は、上場会社の買収ではよく行われる方法です。株券などの発行会社、または第三者により、不特定多数に対して株券等の買付け、または売り付けの申込みを勧誘します。この場合、買付け期間や数量、価格などを明示し、市場を経ずに買付けが行われます。
株式譲渡では会社の経営権が移転するわけですが、事業譲渡では特定の事業だけが取引対象となります。売り手企業の事業の全部、または一部を、買い手企業が対価を支払って譲渡を受ける手法です。対価は原則的に現金で支払われます。
業績の振るわない事業部門を整理したい売り手企業と、事業規模の拡大や新規参入を考える買い手企業のニーズが合致して行われます。個人商店など個人経営者が事業を譲渡とする場合は営業譲渡と呼ばれます。
当事者間の売買契約によって取引対象が定められるので、会社の経営権が移転する株式譲渡と違い、不測の簿外債務などを引き継ぐリスクがありません。また売り手としても、手放したくない事業や資産などを譲渡しないで済みます。
会社法の規定によって、全事業や主要な事業が買収対象の場合は株主総会の特別決議を要します。また売り手には同一地域での同一事業を一定期間(通常は20年)行えない競業避止義務も課せられます。包括承継ではないので、資産や負債の移転、許認可や契約関係など個別に手続きを要するのもデメリットです。
次に説明する合併や会社分割などの組織再編とは違い、適格要件を満たす場合の優遇税制がありません。時価によって資産、負債を承継するため、簿価との差額が生じ、譲渡損益が発生します。このことによって売り手には法人税が、買い手には消費税が発生する場合があります。
会社分割は事業譲渡とよく似た目的で行われるスキームで、会社の特定の事業部門を分割して別会社に承継させる手法です。
会社分割は包括承継となるので、資産や負債、取引関係や契約などを個別に移転させる事業譲渡よりも手間を掛けずに引継ぎが行える点がメリットです。ただしその手続き自体は非常に複雑で、労力やコストがかかります。
会社分割では対価を株式とすることも可能で、資金調達のハードルも低くなります。最近では、会社分割で非事業用の資産を新設会社に承継させ、この新設会社を株式譲渡などの形で買収させる手法がよく見られます。事業譲渡と会社分割のいいとこ取りをするハイブリッドというところです。
会社分割は主に4つのパターンがあります。
株式交換や株式移転は、買い手企業が100%株式を保有して売り手企業を完全子会社化することを目的とする手法です。
買収が行われてもそれぞれの法人格は維持されるので、事業継続がスムーズなのがメリットです。売り手企業の株主が買い手企業の株主となるため、株主構成が変わる点と、原則的に株主総会の特別決議を要するのがデメリットといえます。
株式交換は、売り手企業の全株式を買い手企業の株式や新株予約権と交換する方法で行います。売り手の経営権のすべてを買い手の株式などを対価として取引しているわけです。(必要に応じて現金での取引も可能です)
株式移転は、複数の売り手の全株式を譲渡する相手が、新設会社であるという点が異なります。新設会社は持株会社となり、これを媒介として買い手企業と緩やかな支配関係(グループ企業化)を結ぶことになります。合併などに比べて、売り手の抵抗感が少ない、現金調達が不要などのメリットからよく用いられる手法です。
2021年3月施行の改正会社法では、必ずしも全株式の買収ではなく、50%超100%未満の子会社化にあたるケースでも対価を株式または新株予約権によることができるようになりました。(子会社化が条件となります)この方法は「株式交付」と呼ばれ、資金調達が不要な新たなM&A手法として今後の活用が予想されます。
第三者割当増資は、もともとは資金調達方法の1つで、発行する新株を特定の第三者に割り当ててその対価を得る手法です。この株式の取得(投資)によって、該当の第三者の議決権比率は高まります。新株の発行数によっては、経営権を掌握できる程度にもできます。
財務状況の悪い企業の買収や資本提携、関連会社化を目的としたM&Aスキームとして用いられます。売り手が公開企業の場合、原則的に取締役会の決議のみで実施でき、株主の同意を要しません。基本的にTOB規制の対象外なのもメリットですし、会社に現金が直接入ることも大きな魅力です。
買い手企業の関連会社となるか、単なる資本提携にとどまるかは株式の発行数の比率によります。いずれにせよ既存の株主が存在するので、株式の100%を保有する完全子会社化はあり得ません。
また、既存株主の株式を留保したまま経営権を得ようとする場合、通常の株式譲渡よりも多くの株式を取得する必要がありコスト高になります。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

買収はよく用いられるスキームであり、それは多くのメリットがあるからといえます。
買い手のメリットは、買収のスキームによっても違ってきますが、事業拡大の効率性や、コスト面での良さが主に挙げられます。具体的に5つを解説します。
買収における買い手側の最大の目的は会社の成長です。買収は、その成長に直結する事業拡大がスピーディーかつ低コストで実現できる可能性があります。
買収するのが会社であれ、事業であれ、そこに付随する営業エリアや必要な施設、事業運営に慣れた従業員が一気に獲得できます。すでに事業が行われているわけですから、取引先や販路も開拓する必要はありません。
もちろん、自前でそうしたインフラを整備すれば買収しなくても事業拡大は可能です。しかし、買収によることで、新規に整備するよりはぐっとコストを削減できます。低く抑えられた投資で、期待する規模の事業拡大を図れるのは大きなメリットです。
買収によって事業規模は単純に拡大するでしょう。しかし、そこにとどまったのではあえて他者を自分の物にするうまみには乏しいですね。そこには相乗効果、シナジーが生まれることが期待されます。
優秀な人材を手に入れ、そこが起点となって自社内の技術力や開発力が上がったり、販路の拡大によって新規の事業の可能性が拓けたり、生産ラインが整理されて効率化が図られたり、さまざまな面での改善や効率アップの効果が期待できます。コスト削減によるコストシナジーや、売上げ増加として表れる販売シナジーなどが得られるのです。
企業グループを形成することで、グループ企業間で不足部分を補完し合うことも期待されます。経営情報などの共有化により、採算の上がらなかった事業分野に活路が見いだせることもあります。互いの良さを活かし、短所を補い合うことでグループ全体としての収益性もアップするのです。
被買収企業は、合併とは違ってその法人格を失いません。買収した企業の子会社やグループ企業になっても、法人としての会社は維持されます。変わらないということは、関係した取引先や従業員に安心感を与えます。ひいては事業運営の安定化につながり、継続的な利益確保が得やすいことが考えられます。
買収では一般に資金調達が必要になります。株式譲渡は基本的に多額の対価が必要ですし、事業譲渡も現金取引が基本です。しかし、株式交換や移転、会社分割などのスキームでは原則的に株式や新株予約権が対価となるので、資金調達を要しません。資金調達を外部に頼れば、大きな債務リスクも抱えかねませんので、その意味でも大きなメリットとなり得ます。
株式会社は株主の意見を反映して経営されています。株主総会は原則多数決ですから、少数株主の意見が反映されることは多くありません。しかし、一定条件下では少数株主から決議の取消し、無効を訴えられることもあります。買収によって大株主が生まれることで、こうした少数派の株主を排除できる可能性があります。
十分な数の議決権株式を持てば、株式併合(株式の単位をまとめて新たな単位とすること)などによって、少数意見株主の持ち株が議決権を失うようにすることで排除が可能です。このプロセスをスクイーズアウトと称します。
買収においては受動的立場と思われがちな売り手企業ですが、想像以上にアグレッシブなメリットがあります。それは売却の対価が得られることと事業に継続性があることに依拠します。主に3つ考えられます。
買収によって、売り手は売却益を得られます。これはさまざまな面で売り手にメリットとなります。
赤字経営に苦しむ企業は、これを債務弁済や事業資金にあてられます。事業譲渡であれば、不採算部門の売却益で、比較的好調な部門のテコ入れも可能でしょう。赤字企業であっても、その繰越欠損金などを当てにした買い手が見つかる可能性は少なくありません。
またリタイアを考えている場合には、引退後の生活資金を得ることにもなります。ベンチャー企業などで、新しい事業に向けてのイグジットを検討しているのであれば、売却益はその資本ともなりますし、投資家などへの還元にも活用できます。
また直接の売却益でなくとも、資本が潤沢な大企業の傘下に入ることで財務基盤が強固になる財務シナジーが得られるのも大きなメリットです。中小企業が資金的な問題で事業維持が難しくなった場合など、あえて大企業の傘下に入ることで財政基盤を強化するという考え方もあります。
昨今のM&Aスキームの動向でも解説しましたが、後継者不足の問題は喫緊の課題です。多くの中小企業などがそのために廃業に追い込まれる可能性があります。そうなれば蓄積してきた事業成果は水泡に帰してしまいます。これを回避して、事業承継によって会社の存続を図れることは重要なポイントです。
上記とも関連しますが、廃業となれば最もショックを受けるのは従業員です。経営者としても退職金の調達や失業保険の手続きなど、講ずるべき対応策に要する労力とコストは大変なものです。しかし買収によって、会社は現状維持でき、従業員の雇用は確保されます。事業承継できるメリットはこの点でも大きいのです。

メリットの多い買収ですが、デメリットがないわけではありません。注意しないとM&A自体がブレークに至るような深刻なものも考えられます。
買い手のデメリットは、会社をまるごと引き継ぐことに起因するものが主です。また会社が売買対象になることによるメンタル面の影響も考えられます。ここでは5つ挙げておきます。
買収する側としては、買収価額を提示し売り手の納得を得なければなりません。売り手は少しでも高く売りたいと思っているわけですから、それを納得させながらリーズナブルな価額を示すのは容易ではありません。企業価値の算定やデューデリジェンスの結果なども踏まえて根気強い交渉が必要です。
M&Aプロセスの中でも、基本合意書や最終契約書の作成など、買い手側の負担となる手続きは多く、そうした意味でも手続きが困難であることはデメリットとなります。
買収が成功すると、売り手側企業の従業員は原則的に買い手の傘下に入ります。事業は継続されるのがメリットなのですが、やはり立場の違いなどから不満や不信感を持つ従業員も出てきます。特にそれが、人的リソースの要としてシナジーのキーパーソンとなる人物の離職につながる場合、買収の効果が期待ほど得られなくなりかねません。
買収などM&Aの成否を握るのは、実行後のPMI(経営統合)といっても過言ではありません。企業風土のすり合わせから就業ルールの統一、給与テーブルの統合など必要なものは多岐にわたります。ところが買収の場合、売られたというコンプレックスも手伝って、買い手側の一方的な要求は反感を招きかねません。
買い手側は、売り手企業側のシステムなどを可能な限り尊重して、丁寧なPMIを行う必要があります。同様に取引先など関係者に対しても、前例などをしっかりと踏まえて対応をしていかなければなりません。
PMIの失敗はそのままシナジー効果の低下につながります。期待していたようなシナジー効果を発揮することはもう期待できないでしょう。もちろん、シナジーの見込みが楽天的すぎた場合もあるでしょうが、あくまでもPMIの成功が前提でシナジー効果は発揮されるのです。
買収では事業譲渡を除き、会社の経営権をまるごと承継することになります。デューデリジェンスなどで経営上のリスクは入念に精査することになりますが、それでもさまざまな簿外債務などがあとから顕在化してくることはあり得ます。もしこれが大きなものだと、最悪、買収後の経営悪化の原因にもなりかねません。
賞与や退職金の引当金、未払いの社会保険料や残業代、買掛金やリース債務、第三者の債務保証、手形割引による償還義務などの財務的なリスクもさることながら、訴訟リスクや環境問題でのリスクなども考えられます。
のれん(買収価額に対する純資産額の差額、無形固定資産)の減損も憂うべきリスクの1つです。買収後に想定した収益が上がらなかったときは、計上したのれんの減損処理が必要になる場合があります。これは決算上、当期の損失額となり、大きな経営上のリスクとなります。
買収対価として株式を交付した場合、売り手企業やその株主が買い手企業の株主となります。対価とした株式が非常に多い場合、既存の株主との間で保有比率に無視できない影響を及ぼす可能性があります。資金調達しないで済むのは大きなメリットですが、買収後の株式比率を正確に把握しておかないと、「軒を貸して母屋を取られ」かねません。
売り手のデメリットは、そもそもM&Aが失敗に終わる可能性をはらむものが考えられます。それだけ根源的に買収というスキームに依拠しているともいえるでしょう。3つ挙げます。
売り手としてはできるだけ高く会社を売却したいと考えます。企業価値算定などを参考にしながらも、身贔屓の意識が働き高めの価額設定になりがちです。そうなると買い手側が興味を示したとしても予算的に折り合わず見送ることも考えられます。
また財務状況が極端に悪かったり、法務上のトラブルを抱えていたり、買収後のリスクとなりそうな要素があれば、やはり相手を見つけることは困難になります。
買収は売り手企業も事業を継続できるのがメリットです。とはいうものの、買収によって経営環境が変われば、取引先などの関係者は従前どおりの関係が維持できるかということに不安を感じます。
大手企業による買収であっても、買収によって不利な立場に置かれ、取引条件が悪化するのではないかと考え、取引を控える可能性もあります。
売り手企業としてはあらかじめ同条件か、より有利な条件で取引が継続できる見通しを関係者に伝えておく必要があります。
買収されれば、売り手企業は買い手の経営方針に従うことになります。しかし、それが意に沿わない経営方針だった場合、それに従うことがストレスとなり、ひいては経営意欲や就業意欲を削がれてしまう可能性があります。売り手としては、買収後の経営統合においても必要不可欠な要求はきちんと伝え、理解を得る努力をしなければなりません。
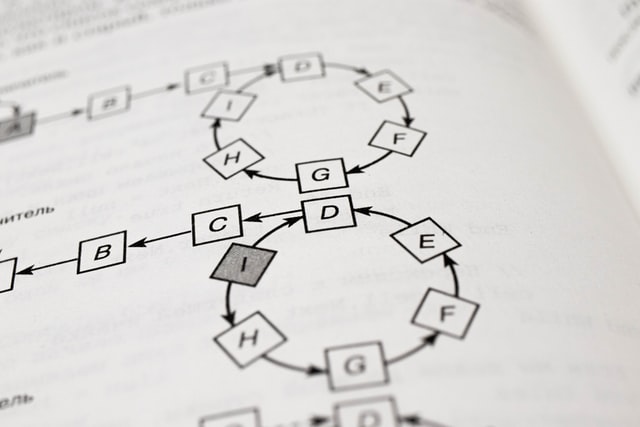
買収はいくつものスキームがあり、それごとに必要な手続きなどは異なります。ここでは大きくM&Aにおける買収の流れを、9つのステップとして解説していきます。
M&Aは目的ではなく手段です。M&Aによってどういう経営を目指したいのか、ゴールを明確にイメージする必要があります。そのゴールに向けてM&Aが必要だと判断したら、どのような相手先が必要なのか、条件は何か、またその優先順位はどうするか、とM&Aの戦略を立てる必要があります。その結果、買収が適していると判断すれば、買収のプロセスがスタートするわけです。
買収は地道なプロセスの積み重ねです。またそのプロセスの中では複雑で専門的な手続きを要します。企業の中にM&Aのチームを作ることは重要ですが、専門性のある助言やサポートをしてくれる存在が必要です。
M&A仲介会社などのM&Aアドバイザーに依頼することは最も堅実な方法といえます。M&Aアドバイザーも特に情報が豊富な業界や得意な専門分野などがありますから、自社のM&A戦略に合致するアドバイザーを選ぶべきです。報酬体系などもさまざまですので、条件に合うアドバイザーを慎重に検討する必要があります。
またコスト的に抑えて、マッチングする企業探しに主目的を置くなら、Web上のM&Aプラットフォームを利用するという選択肢もあります。
買収の相手を決めるには、買い手が主体的に動くケースと売り手側から持ち込むケースの主に2つがあります。
買い手が主体的に動くケースでは、買い手側が希望する売り手の条件(業種や事業規模、営業地域など)を提示し、M&A仲介会社やプラットフォームでマッチする相手を探します。一般的には数十社のリストが提示され、そこから数社に絞った「ショートリスト」を作成、さらに買収の可能性やシナジーなどを観点に優先順位を付けて打診していきます。
売り手側から持ち込むケースでは、売り手企業の名前が特定できない形で業種や規模、実績や売却希望の理由などを記載したノンネームシートが提供されます。この中で食指の動く案件があれば、秘密保持契約を締結して情報漏えいを防止した上で、より高度で具体的な情報が記載されたインフォメーションメモランダムを確認、検討していきます。
相手先が決まったら、簡易的なバリュエーション(企業価値算定)を行い、暫定的な買収価額を提示し合いながら、トップ面談を行います。この面談は具体的な条件交渉ではなく、相互の企業理念や事業内容の共通理解を図るのがねらいです。
その後、具体的な交渉に移ります。買収価額はもちろん、買収スキームやスケジュール、買収後の従業員や経営体制の取り扱いなど、基本的な妥結点を探っていきます。利害は相反していますから、無理に要求を通そうとすればM&A自体がブレークしかねません。根気強く相互の要望をすり合わせていく必要があります。
買収の基本条件や見通しについて合意に至ったら、基本合意書を作成します。ここには守秘義務や独占交渉権、法的な拘束力についても記されます。特に独占交渉権は、このあとの買収プロセスを安心して進められるよう、売り手が他の買い手と交渉できないようにする重要な取り決めです。
基本合意書の作成は必須ではなく、一般に法的拘束力は生じません。しかし独占交渉権の合意などには法的拘束力を持たせる例も見られ、買収プロセスをスムーズに進める意味でも作成が望ましいといえます。
デューデリジェンスは買い手が売り手企業の財務面や経営状態、ITシステムや財務、また法務面の健全性など、多岐にわたる精査を行うプロセスです。このプロセスで、買い手は売り手を買収することによる効果などを検証するとともに、簿外債務などの潜在的なリスクがないか、あるならその対策をどうするかを検討していきます。
このプロセスで、買収後のリスクヘッジが担保されます。また買収価額の妥当性などにも関わってきますので、M&Aの成否のかかる重要なプロセスといえます。
買収価額は企業の株式の価値として算定されます。この算定のプロセスをバリュエーションと呼びます。バリュエーションによって、売り手企業の客観的な企業価値を明確にして交渉を進められるようになります。デューデリジェンスで明らかになったマイナス要因などは、この算定に織り込まれます。
方法としてはマーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチの3種類があります。できるだけ複数のアプローチを用いて、より客観性の高い企業価値を算定することが重要です。
デューデリジェンスやバリュエーションの結果をもとに、最終的な交渉が行われます。買収価額はもちろん、付帯する条件などにもデューデリジェンスの内容は反映されます。
相互に妥結したら、最終契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など)を取り交わします。契約書には買収価額、売り手側の表明保証、契約解除に関する事項,クロージングまでのスケジュールなどが記載されます。事業譲渡では、譲渡対象を明確にするため、その資産や負債に関しても詳細に記載されます。
この契約書は法的拘束力を持ち、売り手買い手双方に履行すべき義務が課せられます。
契約書の内容を相互に実行し、最終的にM&Aを完了させることをクロージングといいます。株式譲渡なら株式の移転と対価の支払い、事業譲渡なら資産等の移転手続きと対価の支払いのように、スキームによって具体的な作業は異なってきます。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

買収価額は一律に示されるものではありません。あくまでも当事者間の合意で決定されていくわけですが、簡易的に目安となる企業価値を算定する方法があります。それは「修正純資産+単年度利益×3年分=企業価値」とする考え方です。買収交渉に先立って、相場の価額を知りたい場合に用いられることがある算定方法です。
相場価額によってスモールM&A(数百万~1億円)、中小企業間のM&A(数千万~100億円)、大企業間のM&A(10億円以上)に分類されることがあります。
相場価額だけで交渉を進めることはできません。バリュエーションによって、客観性のある妥当な企業価値を算定する必要があります。代表的な3つの考え方を解説します。
市場株価を基準として企業価値を算定する考え方です。代表的な算定方法は類似会社比較法(マルチプル法)です。これは売り手企業と類似した上場企業を選び、その株価をもとに、純利益や純資産、EBITDAなどの財務指標に対する倍率(マルチプル)を求め、それを対象企業の財務指標に係数として乗じて株式価値として算定する方法です。
売り手企業が非上場であっても、同業種、同程度の事業規模の上場企業が見つかれば、客観的な企業価値(株式価値)が算定できるのがメリットです。ただし、類似企業が見つからなければこの算定方法は適用できません。
企業の将来にわたる収益性をもとに企業価値を算定する考え方です。代表的な算定方法はDCF(Discount Cash Flow)法です。これは売り手企業の向こう3年間の事業計画(中期計画)などに基づいて将来的なキャッシュフローを推定し、割引率を乗じるなどして現在価値に修正して企業価値を算定する方法です。
売り手企業が持つ現在の資産や負債などだけでなく、将来的な収益力も含めて企業価値を算定できます。いわゆる「のれん」のブランド力などの無形固定資産も加味できる点で優れ、多くのバリュエーションで用いられています。ただし中期計画などに潜在する計画者の恣意性が算定結果に影響する点は、注意が必要です。
企業が保有する純資産をもとに企業価値を算定する考え方です。代表的な算定方法は時価純資産法です。これは売り手企業の資産や負債を時価に換算し、資産から負債を減じて時価純資産額を求め、これを企業価値とする算定方法です。資産には取引関係や知的財産などの無形固定資産(のれん)も含めて算定します。
貸借対照表などの財務諸表を用いてかんたんに算定できる点がメリットになります。また時価の資産や負債額という、恣意性のない数値が用いられるので主観的な判断が入り込む余地もありません。ただあくまでも現在の企業価値評価のみにとどまり、将来的な収益性などは加味されず、スタートアップ企業などでは不利に働く算定方法といえます。

買収にかかる費用は、大きくは対価として支払う金額であり、関係する事務経費、そして税金です。ここでは税金について解説していきます。買収のスキームによって、関係する税金は変わってきます。
株式譲渡の場合、対価を受け取った株主には所得税と住民税がかかります。買収価額から必要経費(取得費や手数料)を減じたものが譲渡所得となり、これに20.315%(復興特別所得税を含む所得税15.315%、住民税5%)が課税されます。株主が法人(会社など)であれば、外形標準適用法人で29.74%の法人税(法人住民税、法人事業税を含みます)の課税です。
株式譲渡で買い手に課税されることは基本ありませんが、著しく高い価額で買収した場合は差損が贈与とみなされ贈与税が、その逆の場合差益が受贈益と見なされ法人税が課税されることがあります。
事業譲渡の場合は、まず売り手に、買収価額と純資産額(簿価)の差額が事業売却損益と見なされ、他の所得と合算して法人税が課税されます。買い手には消費税課税対象の資産が含まれていれば消費税が課せられます。ただし資産に不動産が含まれる場合は、不動産取得税の課税となります。そのほか、登記等に際して登録免許税がかかります。
会社分割や株式交換、移転の場合、組織再編優遇税制の適格要件を満たしていれば資産や負債が簿価で引き継がれるため、売却損益を生じず非課税となります。この適格要件は非常に複雑ですので、税理士などの専門家に対応を依頼することが肝要です。

買収された会社は、原則的には現状維持で経営されます。しかし何の変化もないというわけではありません。主に5つの変化が生じます。
従業員の処遇は原則的には変わりません。しかしPMI(経営統合)の過程で、給与規定などの統合が行われるのにつれ、変動する可能性はあります。また事業譲渡の場合は、労働契約は個別に締結し直すことになりますので、当然従前の労働条件が維持されず変更されることは十分あり得ます。
役員は常勤、非常勤で大きく違います。非常勤役員は一般的に実態が伴わない場合が多く、買収後は退任となるのがほとんどです。
常勤役員はPMIを円滑に進めるのに必要だったり、本人が買収後のキーパーソンだったりして、残留することも少なくありません。ただし報酬や退職慰労金などは株主総会で決定されるため、待遇が維持される保証はありません。
人事制度は原則的に買い手企業に統合されていきます。ただしこれを急速に行うと労働者の不利益変更で法的責任を問われかねないので、1、2年かけて丁寧に行われることが普通です。
また福利厚生も買い手企業のシステムに統合されていきます。結果として売り手企業側の福利厚生の条件に変更が生じることはよく起こります。
そして何よりも企業風土、社風が変わります。子会社として組織が維持されたとしても、親会社の企業理念や経営方針などに影響されることは避けられません。場合によっては不本意なものを受け入れざるを得ない場合もあります。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

買収は事業拡大のターニングポイントとなり得る一大イベントですが、場合によっては「大山鳴動して鼠一匹」となりかねない危険もはらんでいます。特に2つの点に注意が必要です。
第1にシナジー効果を得られない可能性を踏まえておくことです。買収の大きなメリットでもあり、目的でもあるのがスケールメリットなどによって生じるシナジー効果ですが、PMIがうまく行かないと想定通りの効果を得られないことはよくあります。シナジー効果に頼り過ぎず、着実な経営統合を進めるプランを持っておかなければなりません。
第2にリスクのないチャレンジはないと肝に銘じておくことです。入念なデューデリジェンスとそれを受けた条件交渉によって、リスクは最小化されますが0にはなりません。想定外のコンプライアンス違反や偶発的な債務発生など、リスクは必ず潜んでいます。常に最悪を念頭に置きつつ、取り返しのつかない事態にならないよう対応していく必要があります。

一般的にM&Aの成功率は3割から5割といわれています。つまり失敗するほうが多いということです。失敗にも大小ありますが、投資が全く無駄になってしまった、利益を上げるどころか損失を計上してしまった、などということになればまさに本末転倒です。少しでも成功確率を高めるために、5つのポイントを押さえておきましょう。
まずシナジー効果を十分に見込める相手先を見つけることです。時間、労力、資金をつぎ込んで行う以上、できるだけ多くの相乗効果が得られるよう検討を重ねましょう。期待されるシナジー効果の主な要因は次の3つです。
買収対象として大きすぎる企業は避けたほうが賢明です。相手が大きければ大きいほど、その手間も資金も膨れ上がり、万一の際のリスクは大きくなります。買収後のPMIも困難です。一般的に従業員数や売上高において、自社の3割未満の企業が望ましいといわれています。
デューデリジェンスはやり過ぎるということはありません。売り手企業の状況について、徹底的に調べ上げ、その結果をもとに適正な買収価額や必要な取引条件を交渉していかなければなりません。買収後にリスクが発覚しても、文字通り後の祭りなのです。
買収後はPMIを確実に進めましょう。一般的にPMIは、統合方針の決定、ランディングプラン(3~6カ月の作業計画)の立案、100日プラン(被買収企業の中期的な経営計画)の立案、統合実施と効果検証(定量的な目標値であるKPIの活用)の4つのプロセスを経ます。
特に100日プランは、事業経営上重要ですので、プロジェクトチーム体制などを組み、実務担当者を明確にして取り組むことが望ましいでしょう。
買収には多くのプロセスがあり、デューデリジェンスやバリュエーション、契約書の締結など、専門性や高度な知識を求められる作業も目白押しです。これらを独力のみでクリアしていくのは並大抵ではなく、事務的な課題に忙殺されて失敗に陥りかねません。
M&A仲介会社などの専門家を依頼することは、必須のファクターといえます。手数料などを惜しんで、頼れるビジネスパートナーの助力を得ないことは、成功を目指す上で選択すべき道ではありません。

買収にはいろいろなスキームがあり、M&Aの目的や当事者間の関係性などによって選択する必要があります。ここでは代表的なスキームで行われた成功事例を3つ紹介します。
コロワイドは2019年10月、大戸屋創業者の家族から大戸屋ホールディングスの株式を19%弱取得しました。これをきっかけにコロワイドは大戸屋ホールディングスに友好的買収を持ちかけます。しかし大戸屋ホールディングス側はこれを拒否、コロワイドはTOBによる敵対的買収を仕掛けました。
このTOBにおいてコロワイドは、1株3,081円、総額60億円以上を費やし、大戸屋ホールディングスの全株式の46.77%(約200万株)を取得しました。この買収で大戸屋ホールディングスはコロワイドのグループ会社となり、取締役の交代で実質的に経営権を失いました。国内では珍しいTOBによる敵対的買収の事例です。
スピードウェイは、アメリカのMPC社が手掛けるガソリンスタンド併設型のコンビニエンスストアのブランドです。アメリカにおけるコンビニエンスストア事業の展開を目論むセブン&アイHDは、アメリカの子会社を通じてこのスピードウェイの買収を実施しました。
買収は株式および持分を取得する形で行われ、買収価額は2.2兆円に及びました。しかし、このM&Aでセブン&アイHDは、全米47エリアの店舗網を獲得、業界のトップシェアを占め、営業利益を倍増させる見込みです。また5億ドル以上の財務シナジーが見込まれ、15事業年度にわたる30億ドル程度の節税も可能となりました。
M&Aのスケールの大きさもさることながら、グローバルな事業譲渡による買収で、多大なシナジー効果を獲得した成功例です。
2021年5月、広告やデザインのデータ処理、デジタルコンテンツの制作などを手掛ける日本創発グループは、印刷デザインやDTP制作事業を展開していたアド・クレールを買収し、完全子会社化しました。
これはグループ関係にあった両社の経営資源を統合し、シナジー効果によって両社の企業価値を高めることがねらいでした。株式交換による完全子会社化の買収事例です。

買収は、M&Aの目的に沿って適切な相手先を探して戦略的に進めていく必要があるスキームです。しかし数多ある企業の中から、ねらいに合致する企業を探し出すのは困難な作業です。
ウィルゲートM&Aでは、15,100社を超える経営者ネットワークを活用し、ベストマッチングを提案します。Web・IT領域を中心に、幅広い業種のM&Aに対応しているのがウィルゲートM&Aの強みです。M&A成立までのサポートが手厚く、条件交渉の際にもアドバイスを受けられます。
一般的にM&Aの成約までは6ヶ月〜1年ほどの期間を要しますが、ウィルゲートでは平均で4ヶ月、最短1.5ヶ月での成約実績、40億円以上での成約実績もあります。完全成功報酬型で着手金無料なので、お気軽にご相談ください。
無料相談・お問い合わせはこちらから ※ご相談・着手金無料

買い手は即戦力の事業を獲得でき、売り手は会社を維持しながら売却益を得られる買収は、まさにウィンウィンのM&Aを実現できるスキームだといえます。しかしその手続きは複雑で、遺漏なくM&Aを進捗していくためには専門家のサポートを受けながら、慎重に進める必要があります。
頼りになる専門家をお探しなら、ぜひウィルゲートM&Aの無料相談をご利用ください。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください