
会社の値段、すなわち企業価値は、M&Aや事業承継、資金調達といった重要な経営判断の場面で客観的な指標となります。この価値を算出するには、企業の資産や将来の収益性、市場での評価など、多角的な視点からのアプローチが必要です。
本記事では、会社の値段を構成する企業価値と株式価値の基本的な関係性から、具体的な計算方法までを分かりやすく解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

会社の値段である企業価値の把握は、多様な経営シーンで必要とされます。代表的な例がM&Aの場面であり、売り手と買い手の双方が納得できる取引価格を決定するための基礎となります。
また、金融機関からの融資といった資金調達の際にも、企業の信用力を示す客観的なデータとして機能します。
その他、事業承継で後継者に株式を引き継ぐ際の評価額算定や、純粋に自社の経営状態を客観的に分析し、将来の経営戦略を立てるためにも企業価値の算出は有効な手段です。これらの場面において、適正な企業価値を理解しておくことは、円滑な交渉や意思決定の前提となります。

企業価値とは、会社全体の価値を示すもので、事業そのものが生み出す「事業価値」と、事業とは直接関係のない預金や不動産などの「非事業用資産」の合計で表されます。
一方、株式価値は、株主が所有する部分の価値であり、一般的にM&Aで売買される価格の基準となります。株式価値は、企業価値から有利子負債を差し引き、現預金などの資金を加えることで算出されます。この関係は「株式価値 = 企業価値 − 有利子負債 + 現預金」などと表現され、ネットデット(Net Debt)で調整されるのが一般的です。
つまり、会社全体の価値から債権者(銀行など)の分を引いた残りが、株主の取り分である株式価値になるという関係です。最終的な売買価格は、この株式価値を基に1株あたりの価格を算出し、交渉が行われます。
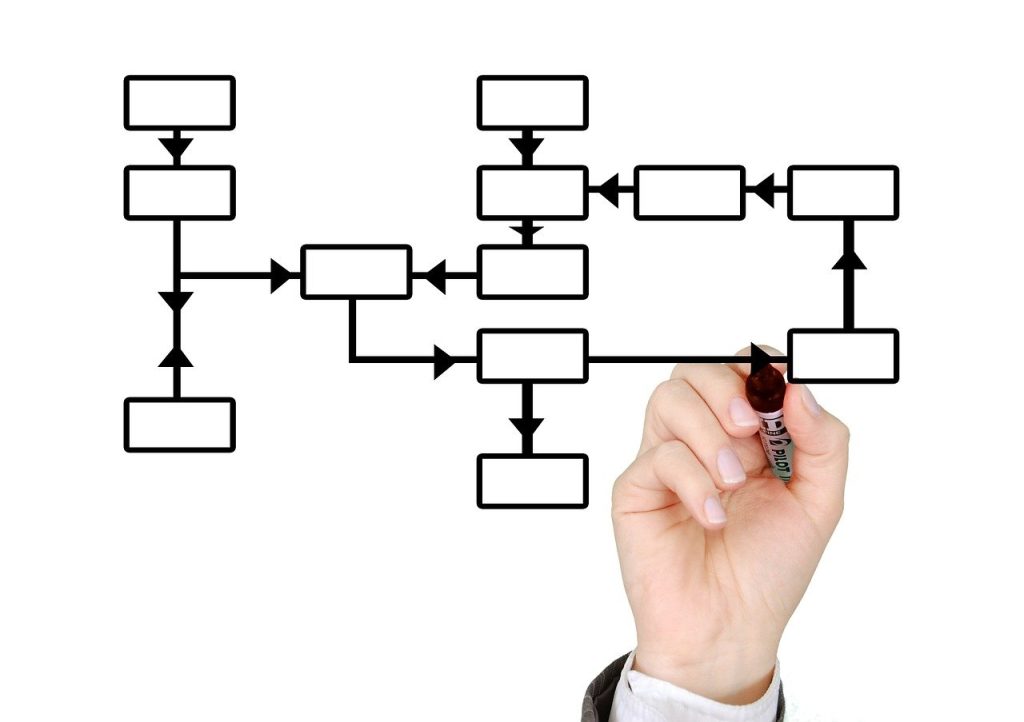
会社の値段を算出するには、客観性を持たせるための確立された評価アプローチが存在します。
これらのアプローチは、企業のどの側面に焦点を当てるかによって、大きく3つに分類されます。
会社の純資産を基準にする「コストアプローチ」、将来の収益力から価値を導き出す「インカムアプローチ」、そして市場での類似取引を参考にする「マーケットアプローチ」です。
コストアプローチは、会社の貸借対照表に記載されている純資産額を基に企業価値を評価する方法です。評価時点での会社の純資産に着目するため、客観的なデータに基づいており、計算が比較的容易であるという利点があります。
このアプローチには、帳簿上の数値をそのまま用いる「簿価純資産法」と、土地や有価証券、解約返戻金が見込まれる生命保険などの資産・負債を現在の価値(時価)に評価し直して計算する「時価純資産法」が存在します。
過去の実績を積み上げた結果である純資産を基準とするため、企業の清算価値に近いとされ、特に成熟企業や資産を多く保有する企業の評価に適している手法です。
インカムアプローチは、会社が将来生み出すと予測される収益やキャッシュフローを基に企業価値を算出する方法です。
将来の収益力を評価の中心に据えるため、現時点での資産は少ないものの、高い成長性が見込まれるスタートアップや、技術力、ブランドといった貸借対照表には表れない無形資産を持つ企業の価値を評価するのに適しています。
代表的な手法にDCF法があります。
このアプローチの評価額は、将来の事業計画の実現可能性に大きく依存します。将来の収益を保証するものではないため、予測の客観性や、将来の不確実性を反映させる割引率の設定が非常に重要となり、専門的な知識が求められます。
マーケットアプローチは、株式市場やM&A市場といった第三者間での取引事例を基に、相対的に企業価値を評価する方法です。
評価対象企業と事業内容、規模、成長性などが類似する上場企業を選び、その企業の株価や財務指標(売上高、利益など)との倍率(マルチプル)を算出して価値を導き出します。
市場での客観的な評価が反映されるため、説得力が高いというメリットがあります。
しかし、評価対象企業と完全に一致する類似企業や取引事例を見つけることは困難です。特に、特殊な事業モデルを持つ企業、例えば特定の専門分野に特化した人材派遣会社などの場合、適切な比較対象の選定が難しく、評価の信頼性が左右される点に注意が必要です。

ここからは、前述した3つの評価アプローチに基づいた、より実践的な会社の値段の計算方法を4つ紹介します。
コストアプローチの「時価純資産法」、インカムアプローチの「DCF法」、マーケットアプローチの「類似会社比較法(マルチプル法)」、そして中小企業のM&Aで広く用いられる「年買法(年倍法)」です。
これらの計算方法を理解することで、自社の状況に合った評価手法を選択し、客観的な企業価値を算出することが可能になります。
時価純資産法は、コストアプローチの一種で、会社の貸借対照表に記載されているすべての資産と負債を現在の市場価値(時価)で評価し直し、その差額である純資産を企業価値とする計算方法です。
具体的には、「時価資産総額から時価負債総額を差し引く」ことで算出します。
例えば、土地や建物といった不動産は専門家による鑑定評価額、有価証券は市場価格、売掛金は回収可能性を考慮した評価額に修正します。
負債側でも、退職給付引当金などが実態に合わせて見直されます。
この方法は、評価時点での会社の価値を客観的に把握できる点で優れていますが、将来の収益力やブランド価値といった帳簿に表れない無形資産は評価に反映されないという側面も持ち合わせています。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)は、インカムアプローチの代表的な手法です。
企業が将来にわたって生み出すと予測されるフリーキャッシュフロー(事業活動から得られる現金)を、将来のリスクを反映した割引率を用いて現在価値に換算し、それらを合計して事業価値を算出します。
この計算には、信頼性の高い将来の事業計画と、資本構成などを基にした適切な割引率の設定が不可欠であり、専門的な知識が求められます。
将来の成長性やブランド力といった貸借対照表に現れない無形資産も価値に反映できるため、多くの企業価値評価の場面で理論的な根拠として重視される手法であり、特に成長が見込まれる企業の評価に適しています。
類似会社比較法(マルチプル法)は、マーケットアプローチの一種で、評価対象の会社と事業内容や規模が似ている上場企業の株価を参考に価値を算出する方法です。
まず、類似企業のEV/EBITDA倍率(企業価値がEBITDAの何倍か)やPER(株価収益率)といった指標(マルチプル)を計算します。次に、そのマルチプルを評価対象企業のEBITDAや純利益などの財務数値に乗じることで、事業価値や株式価値を推定します。
この手法は、市場の評価を客観的に取り入れられる利点がありますが、完全に類似した企業を見つけることは困難です。また、非上場企業の場合は、株式の流動性が低いことを考慮した割引(非流動性ディスカウント)が必要になるなど、専門的な調整が求められ、これが1株あたりの単価に影響します。
年買法(年倍法)は、中小企業のM&Aの現場で広く用いられている簡易的な企業価値評価方法です。
「年買法」は、時価純資産に「実態営業利益 × 年数(通常3〜5年)」を加えることで株式価値を簡易的に求める手法です。この営業権(のれん)は、過去の実績だけでなく将来の収益見通しに応じて調整されるべきです。使用する営業利益は、節税目的で調整されている役員報酬などを修正した「実態営業利益」が用いられます。
この方法は計算が非常にシンプルで直感的に理解しやすいため、M&Aの初期段階でのおおよその価格感を掴むために重宝されます。
ただし、理論的な厳密性には欠けるため、あくまで交渉のたたき台として活用されることが多く、最終的な合意価格は他の評価方法や交渉によって決定されるのが一般的です。

会社の値段は、貸借対照表に記載された資産や計算上の利益だけで決まるわけではありません。長年の事業活動で培われたブランドイメージ、独自の技術力や特許、質の高い顧客リスト、従業員の専門スキルや組織風土といった、数値化しにくい「見えない価値」も評価の重要な要素となります。
例えば、特定の許認可や、優秀な人材を多数抱える人材派遣会社の組織力などは、将来の収益の源泉となり得ます。
これらの無形資産は「のれん」や「超過収益力」とも呼ばれ、M&Aにおいては計算上の純資産額に上乗せされる形で取引価格に反映されます。将来の収益を直接保証するものではありませんが、買い手にとって魅力的な要素であれば、企業価値を大きく引き上げる要因となります。

これまで解説してきた計算方法は、あくまで客観的な会社の値段を算出するための理論値や参考値です。
実際のM&Aの場面では、この算出された価値を基に、最終的には売り手と買い手、双方の当事者間での交渉によって取引価格が決定されます。例えば、買い手側がその会社を買収することでどれだけのシナジー効果を見込めるか、売り手側がどの程度売却を急いでいるか、他に有力な買い手候補が存在するかといった、個別の事情が価格に大きく影響します。
したがって、算出された評価額は交渉の出発点として重要ですが、それがそのまま最終的な売買価格になるわけではありません。自社の強みや相手のニーズを理解し、戦略的に交渉を進めることが、双方が納得する価格での合意形成につながります。

自社の評価額を高めるためには、日頃からの経営改善への取り組みが不可欠です。
まずは本業の収益性を高めることが基本であり、売上の拡大やコスト構造の見直しを通じて利益を安定的に創出できる体制を構築することが重要です。
また、遊休資産の売却や借入金の返済を進め、財務体質を健全化することも評価向上に直結します。
経営者個人に依存している業務を減らし、組織として事業が回る仕組みを整備することも、買い手にとってのリスクを低減させます。
これらの施策は、結果として一株あたりの株式価値を高めることになり、M&Aを検討する際に有利な条件での交渉を可能にします。将来の選択肢を広げるためにも、計画的な企業価値向上策を実践すべきです。
会社の値段、すなわち企業価値は、単一の絶対的な数値で決まるものではありません。
企業の純資産を基にするコストアプローチ、将来の収益力を見るインカムアプローチ、市場での取引事例を参考にするマーケットアプローチという、異なる3つの視点から総合的に評価されます。
具体的な計算方法として時価純資産法やDCF法などが存在しますが、どの方法にも長所と短所があり、評価の目的や会社の特性に応じて使い分ける必要があります。
また、算出された理論値はあくまで交渉の出発点であり、ブランド力などの無形資産や、買い手とのシナジー効果、交渉の状況といった様々な要因が加味され、最終的な取引価格が形成されます。
自社の価値を客観的に把握し、継続的な経営改善を行うことが、適正な評価を得るための基礎となります。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください