
イグジット戦略とは、スタートアップやベンチャー企業の創業者・投資家が、株式売却などによって投資資金を回収し、利益を得るための一連の計画を指します。エグジット戦略とも呼ばれ、企業の成長段階において重要な経営課題の一つです。主な手法には、第三者に会社を売却する「M&A」と、証券取引所に株式を公開する「IPO」の2つが存在します。
本記事では、それぞれの戦略の違いやメリット・デメリット、自社に最適な手法を選択するためのポイントを網羅的に解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

イグジット戦略は、企業の創業者や出資者が投下した資本を回収し、利益を確定させるための出口戦略を意味します。特に、ベンチャーキャピタルなど外部から資金調達を行っているスタートアップにとっては、投資家へのリターンを実現するために不可欠なプロセスです。
イグジットは単なる資金回収に留まらず、成功すれば創業者に大きな利益をもたらし、事業をさらに成長させるためのステップとなります。そのため、起業の早い段階からどのような形でイグジットを目指すのかを具体的に計画しておくことが、事業の方向性を定める上で重要になります。
イグジット戦略の主な目的は、創業者や株主が投じた資本を回収し、キャピタルゲイン(株式売却益)を得ることです。これにより、創業者は経済的な成功を手にし、新たな事業への挑戦や個人的な資産形成が可能となります。
また、ベンチャーキャピタルなどの投資家にとっては、投資先企業がイグジットすることで初めてリターンが確定するため、出資の前提条件としてイグジット計画が重視されます。さらに、M&Aによって大企業の傘下に入ることで、自社だけでは実現できなかった大規模な事業展開や、安定した経営基盤の確保といった、事業の継続的な成長を目的とする場合もあります。

イグジット戦略には様々な方法がありますが、代表的な手法として「IPO(新規株式公開)」と「M&A(企業の合併・買収)」の2つが挙げられます。どちらの手法を選択するかによって、得られる利益の規模、必要な期間やコスト、イグジット後の経営への関与の仕方が大きく異なります。
1.IPO(新規株式公開):株式を証券取引所に上場させる
2.M&A(企業の合併・買収):第三者に会社や事業を売却する
IPO(Initial Public Offering)とは、自社の株式を証券取引所に上場させ、一般の投資家が自由に売買できるようにすることです。株式を公開することで、企業は市場から直接、大規模な資金調達が可能になります。創業者や既存株主は、保有する株式の一部を市場で売却することにより、大きな創業者利益を得られます。
上場企業となることで社会的な信用度が飛躍的に向上し、優秀な人材の確保や事業展開においても有利になりますが、そのためには厳しい審査基準をクリアし、上場後も継続的な情報開示の義務を負う必要があります。
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、自社の株式や事業の全部または一部を、他の企業などの第三者に売却する手法です。株式譲渡や事業譲渡といった形式があり、創業者や株主は売却対価として現金や買い手企業の株式を受け取ることで、投資資金を回収し利益を確定させます。
IPOに比べて準備期間が短く、比較的確実にイグジットできる可能性があります。特に、自社の事業と買い手企業の事業との間にシナジーが見込める場合、従業員の雇用維持や事業のさらなる成長につながる有効な選択肢となります。
-1024x683.jpg)
日本と海外、特にアメリカでは、イグジット戦略の傾向に大きな違いが見られます。経済産業省の「大企業×スタートアップのM&Aに関する調査報告書」によると、日本ではIPOがイグジットの主要な手段として利用される割合が高く、M&Aの割合はアメリカと比較して低い傾向にあります。この背景には、日本市場におけるIPOのしやすさがあると考えられています。
一方で、M&Aの実行においては、買収後の統合プロセス(PMI)がうまくいかないケースが多いことも、M&Aが活用されにくい要因として挙げられます。ベンチャー企業やスタートアップ企業にとって、「イグジット=IPO」というイメージが日本では強く、この認識が実際の調査結果にも反映されていると言えるでしょう。
また、日本とアメリカでは買収価格にも大きな差があります。アメリカでは買い手が多く、競争原理が働くことで、シナジー効果なども考慮され買収価格が高めに設定されやすい傾向が見られます。もちろん、IPOとM&Aにはそれぞれメリット・デメリットが存在するため一概には言えませんが、日本においては、アメリカと比較して買収価格が低いことも要因となり、IPOが選択される現状があります。

M&Aをイグジット戦略として選択する際には、メリットとデメリットの両面を深く理解しておくことが重要です。ここではM&Aによるイグジット戦略のメリットとデメリットについて解説します。
M&Aによるイグジットは、IPOに比べて成功の可能性が高いとされています。特に、買い手が豊富な資本や販路、経営ノウハウを持つ大企業である場合、買収された企業の事業は安定した基盤の上で成長を加速させられます。
買い手企業が持つ経営リソースや広範なネットワークを活用することで、単独では困難だった事業展開も可能になり、リスクを抑制しながら成長軌道に乗せることが可能です。このように、M&Aは企業成長の促進とリスク軽減の観点から、確実性の高いイグジット手法といえます。
M&Aの大きな利点の一つは、イグジットまでの期間が短いことです。IPOが準備開始から上場まで数年単位の時間を要するのに対し、M&Aは交渉相手が見つかれば、数ヶ月から1年程度で完了するケースが一般的です。
買い手となる企業は、豊富な資金力と経営に関する専門知識を背景に、買収プロセスを迅速に進めることができます。このスピード感は、市場の変化が速い業界において大きなアドバンテージとなり、経営者が時機を逃さずに次のステップへ進むことを可能にします。
M&Aによって会社を売却するということは、基本的に会社の所有権と経営権を買い手企業へ譲渡することを意味します。これにより、創業者は経営の第一線から退くか、新しい親会社の方針に従う必要が出てきます。これまで自身が持っていた経営の自由度は大きく制限され、創業時のビジョンや理念を維持することが難しくなる可能性があります。
ただし、イグジットによって得た資金を元手に、再び新しいビジネスを立ち上げるという選択肢も生まれます。
M&Aによるイグジットでは、創業者や株主が得られる利益がIPOに比べて少なくなる傾向があります。
これは、企業の価値が株式市場全体ではなく、特定の買い手企業との相対交渉によって決定されるためです。
買い手側は買収リスクを考慮して、将来の潜在的な価値よりも現在の企業価値を基準に評価額を算出することが多く、結果として売却価格が抑制されることがあります。したがって、M&Aを選択する際には、市場での評価額よりも低い利益を受け入れる可能性があることを認識しておく必要があります。

IPO(新規株式公開)は、多くの創業者にとって大きな目標の一つであり、成功すれば多大な利益と社会的な信用をもたらします。しかし、その道のりは長く険しく、多大なコストと労力を要するだけでなく、上場後には新たなリスクも生じます。
ここでは、IPOによるイグジット戦略が持つ輝かしいメリットと、その裏にあるデメリットについて詳しく見ていきます。
IPOによるイグジットは、M&Aと比較して創業者利益が大きくなる傾向にあります。株式を証券取引所に公開することで、不特定多数の投資家が企業の将来性や成長性を評価し、株価が形成されるためです。
事業内容が高く評価されれば、時価総額は飛躍的に高まり、保有株式の売却によって莫大なキャピタルゲインを得ることが可能です。
企業は市場から正当な評価を受けることで、その潜在価値に見合った高い収益を実現するチャンスを掴めます。
経営権を維持できる点は、IPOを選択する大きな動機の一つです。M&Aでは会社の所有権が買い手に移りますが、IPOでは発行済み株式の一部を市場に放出するだけであり、創業者が過半数に近い株式を保有し続けることで、引き続き経営の主導権を握ることが可能です。
これにより、創業者は外部から成長資金を調達しつつも、自らが描いたビジョンや経営方針を維持しながら事業を拡大していけます。
経営の自由度を保ちたい創業者にとって、これは非常に魅力的な選択肢です。
IPOを果たすことで、企業の社会的な信用度は格段に向上します。証券取引所による厳しい上場審査をクリアしたという事実は、企業のガバナンス体制や財務の健全性、事業の将来性が公的に認められたことを意味します。
この信用力は、金融機関からの資金調達、大手企業との取引、そして優秀な人材の採用活動など、あらゆる事業活動において有利に働きます。上場企業というステータスは、企業のブランド価値を高め、さらなる成長に向けた強固な基盤となります。
IPOの実現には、多くの手間と高額な費用が発生します。上場準備には、監査法人による会計監査、主幹事証券会社による審査、内部管理体制の構築、膨大な申請書類の作成など、数年単位の期間を要する複雑なプロセスが必要です。
これらに伴い、監査費用、コンサルティング費用、弁護士費用、上場審査料など、合計で数千万円から数億円規模のコストがかかることも珍しくありません。企業はこれらの負担に耐えうるだけの体力と覚悟が求められます。
IPOによって株式が市場で自由に取引されるようになると、これまで想定していなかったリスクに直面します。その一つが、経営陣の同意なしに株式を買い集められる「敵対的買収」のリスクです。市場で過半数の株式を取得されれば、経営権を奪われる可能性があります。
このような事態を防ぐため、安定株主の確保や買収防衛策の導入などを検討する必要が出てきます。IPOとは、資本調達の機会を得る一方で、常に経営権を巡る競争に晒される可能性を内包する選択でもあるのです。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

イグジット戦略を検討する上で、M&AとIPOのどちらが自社に適しているかを判断するためには、両者の違いを多角的に理解することが重要です。ここでは、「資金調達規模」「期間とコスト」「経営権」「従業員への影響」「社会的信用」という5つの観点から、それぞれの特徴を比較し、その違いを明確にします。
①資金調達規模と創業者利益
②実行までにかかる期間とコスト
③イグジット後の経営権
④従業員の処遇や雇用への影響
⑤会社の社会的信用
資金調達の規模と創業者利益の観点では、一般的にIPOの方が大きくなる傾向があります。IPOは株式市場全体から評価を受けるため、高い成長性が見込まれる企業には多額の資金が集まり、株価が高騰することで創業者も大きな利益を得られます。
一方、M&Aは特定の買い手との相対交渉で価格が決まるため、評価額はIPOに比べて抑制されることが多いです。ただし、M&Aでも買い手が強いシナジー効果を見込む場合は、高値での売却が実現するケースもあります。
実行までにかかる期間とコストは、M&Aの方がIPOよりも大幅に少なく済みます。M&Aは、買い手候補の選定から交渉、契約締結まで、早ければ数ヶ月、長くても1~2年程度で完了します。
コストも仲介手数料などが主で、IPOに比べれば限定的です。
対照的に、IPOは内部管理体制の構築や監査、審査といったプロセスに数年単位の時間を要し、監査法人や証券会社、弁護士などに支払う費用も数千万円から数億円に上ることがあります。
イグジット後の経営権の維持については、両者で明確な違いがあります。M&Aでは、通常、会社の株式の過半数以上を売却するため、経営権は買い手企業に移ります。創業者は経営から退くか、買い手企業の方針下で事業に関わることになります。
一方、IPOでは、創業者は保有株式の一部を市場で売却するだけであり、残りの株式を持ち続けることで経営権を維持することが可能です。経営の自由度を保ちたい場合はIPOが適しています。
従業員の処遇や雇用への影響も、選択する手法によって異なります。
M&Aの場合、買い手企業の方針によって組織再編が行われ、労働条件の変更や配置転換、場合によっては雇用の維持が難しくなる可能性もゼロではありません。
一方、IPOでは既存の経営体制が維持されるため、従業員の雇用や処遇に直接的な変化は起こりにくいです。ただし、上場企業として業績向上へのプレッシャーが高まり、職場環境が変化することは考えられます。
会社の社会的信用は、IPOによって飛躍的に向上します。上場企業というステータスは、取引先や金融機関からの信頼を高め、人材採用においても大きなアドバンテージとなります。
M&Aの場合、買い手が社会的に信用の高い大企業であれば、そのグループの一員となることで信用度は向上します。しかし、買い手の知名度が低い場合や、買収の事実がネガティブに捉えられた場合には、必ずしも信用の向上につながるとは限りません。

M&Aによるイグジットは、特定の条件を満たす企業にとって非常に有効な選択肢となります。ここでは、M&Aでのイグジットが適している企業の特徴についてご紹介します。
・後継者問題を抱えている企業
経営者の高齢化や親族内に適切な後継者がいない場合、M&Aによって事業と雇用を守りつつ、創業者利益を得られます。
・事業の成長を加速させたい企業
自社単独では難しい大規模な投資や販路拡大が必要な場合、買い手企業の資金力やネットワークを活用することで、事業を飛躍的に成長させられます。
・短期間でイグジットを完了させたい企業
IPOに比べて準備期間が短く、数ヶ月から1年程度でイグジットが可能なため、市場環境の変動リスクを抑えられます。
・特定の技術やノウハウを持つ中小企業
大企業が求める特定の技術やノウハウを持っている場合、その価値を高く評価され、有利な条件で売却できる可能性があります。
・事業構造転換やリスク分散を考えている企業
現在の主力事業からの撤退や、新たな事業分野への集中を目指す場合、M&Aは迅速なポートフォリオ再編に役立ちます。
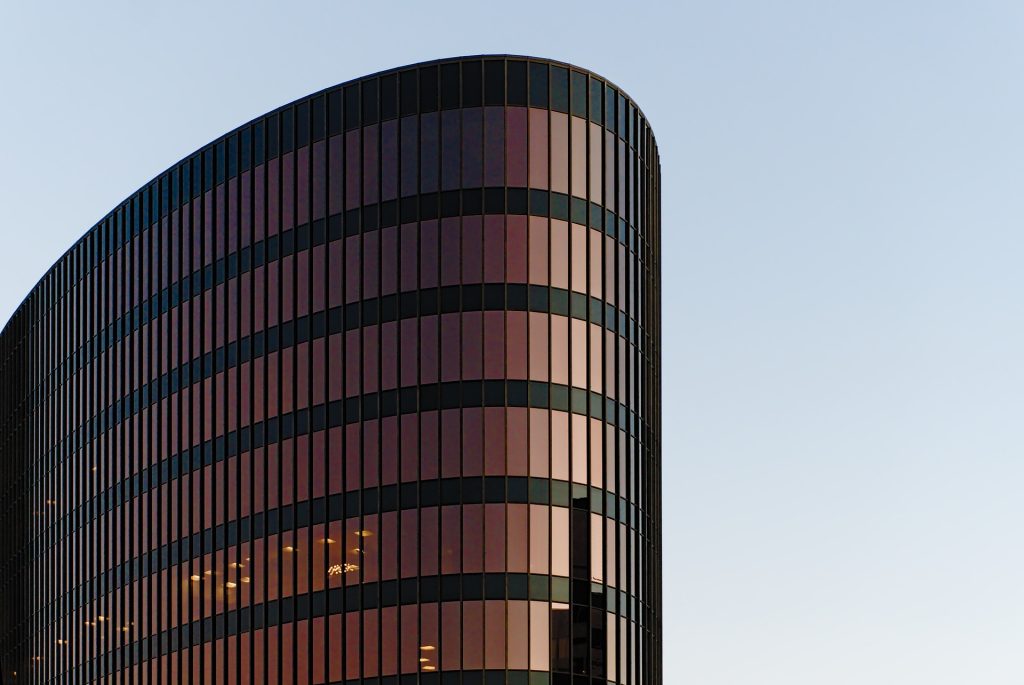
IPOによるイグジットは、継続的な成長を目指し、経営の独立性を維持したい企業に適しています。
主に以下の特徴を持つ企業が該当します。
・成長性が高く、大規模な資金調達が必要な企業
大規模な設備投資や研究開発、海外展開など、多額の資金を必要とする成長戦略を描いている場合、株式市場から直接資金を調達できるIPOは非常に有効です。
・経営の独立性を維持したい企業
M&Aとは異なり、創業者が引き続き経営の主導権を握ることが可能です。
・企業価値の最大化を目指したい企業
将来的に時価総額が10億ドルを超えるようなユニコーン企業を目指すスタートアップにとって、IPOは企業価値を最大化し、社会的なステータスを確立するための重要なマイルストーンとなります。
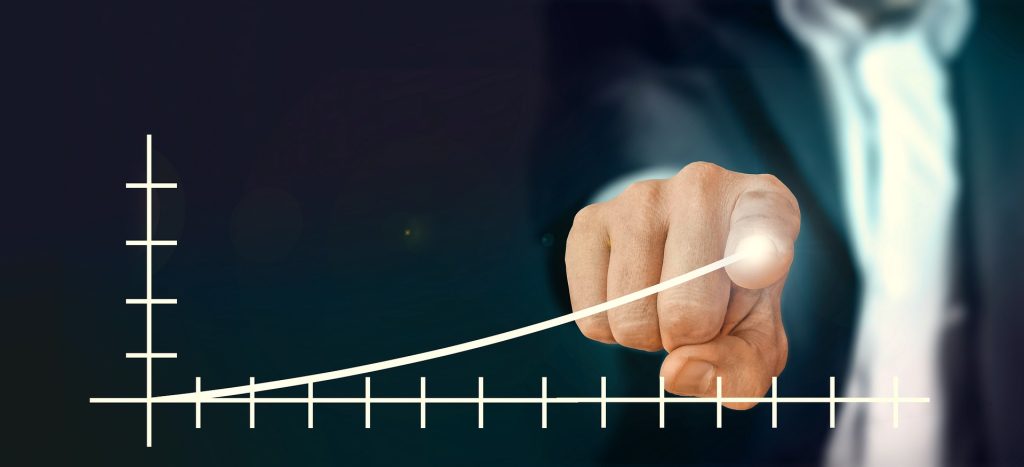
イグジット戦略を成功させるためには、周到な準備と戦略的なアプローチが不可欠です。
単に会社を売却したり上場したりするだけでなく、企業価値を最大化し、最適な条件で実行することが重要になります。ここでは、その成功確率を高めるための4つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:事業の将来性や強みを明確にする
ポイント2:企業価値を最大化できるタイミングを見極める
ポイント3:シナジー効果が期待できる相手先を選ぶ
ポイント4:専門家のアドバイスを活用して交渉を進める
イグジットを成功させるための第一歩は、自社の価値を客観的に評価し、それを買い手や投資家に対して説得力をもって提示することです。独自の技術、強固な顧客基盤、優れたビジネスモデル、市場における競争優位性といった自社の強みを整理し、それらが将来どのように成長につながるのかを具体的なデータや事業計画で示す必要があります。
この将来性や強みが明確であるほど、買い手や投資家は高い価値を認め、有利な条件でのイグジットが実現しやすくなります。
イグジットはタイミングが極めて重要です。自社の業績が右肩上がりで成長している時期や、自社の事業領域が市場のトレンドとして注目を集めている時期は、企業価値が最も高く評価される絶好の機会です。
逆に、業績が停滞していたり、市場環境が悪化したりしている時期では、足元を見られて不利な条件を提示される可能性があります。常にマクロ経済の動向や業界のトレンドを注視し、自社の成長ステージと照らし合わせながら、最適なタイミングを見極める戦略的な視点が求められます。
特にM&Aにおいて重要となるのが、シナジー効果です。シナジー効果とは、複数の企業が統合することで、それぞれが単独で活動するよりも大きな成果を生み出す相乗効果を指します。
自社の技術やサービスと、相手企業が持つ販売網や顧客基盤、開発力を組み合わせることで、どのような価値が新たに生まれるのかを具体的に描くことが重要です。高いシナジー効果が期待できる相手であれば、相手企業も高い買収価格を提示する動機が生まれ、M&A後の事業の成功確度も高まります。
イグジットのプロセスは、企業価値評価(バリュエーション)、法務、税務、会計など、高度に専門的な知識を必要とする交渉の連続です。これらの知識や交渉経験が不足していると、自社にとって不利な条件で契約を結んでしまうリスクがあります。
そのため、M&A仲介会社、証券会社、公認会計士、弁護士といった外部の専門家の力を借りることが成功の鍵となります。専門家は豊富な経験とネットワークを活かし、最適な相手先の選定から交渉戦略の立案、契約書の作成までをサポートし、企業価値の最大化に貢献します。
日本国内においても、多くの企業がIPOやM&Aを通じてイグジットを成功させ、新たな成長ステージへと進んでいます。ここでは、具体的な成功事例をIPOとM&Aのそれぞれの手法に分けて紹介し、どのような企業がどのような形でイグジットを実現したのかを見ていきます。
IPOによるイグジットは、企業の成長性と将来性が市場から高く評価された結果であり、多くのスタートアップにとっての目標です。ここでは、近年注目を集めたIPOの成功事例をいくつか紹介します。
名刺管理サービス「Sansan」を提供する同社は、法人向けSaaSの先駆けとして知られています。
2019年に東証マザーズ(現:東証グロース)に上場を果たし、上場時の時価総額は約2,000億円規模に達しました。BtoB領域でもSaaSモデルが成功することを示し、多くのスタートアップが同社をロールモデルとして参考にしています。これは、企業の成長性と市場からの高い評価が結びついたIPOイグジットの好例として挙げられます。
クラウド会計ソフトを提供するfreee株式会社は、2019年12月に東証マザーズ(現:東証グロース)への上場を果たしました。
同社は、個人事業主や中小企業向けの会計・人事労務のSaaS領域で独自のポジションを確立し、多くのユーザーを獲得していました。
国内のSaaSスタートアップとして高い注目を集め、2019年の中でも大規模なIPO案件の一つとして、その後のクラウドサービス企業のIPOの道を拓く象徴的な事例となりました。
株式会社ジモティーは、地域に根差した情報(売ります・あげます、求人など)をユーザー間でやり取りできるクラシファイド広告サイトを運営しています。
消費者からの高い認知度と地域コミュニティにおける独自のプラットフォームとしての地位を確立し、2020年2月に東証マザーズ(現:東証グロース)に上場しました。
CtoC(個人間取引)プラットフォームの収益性と成長性が市場に評価され、IPOによるイグジットを成功させた事例です。
日本航空(JAL)の事例は、再生型のイグジットとして特筆されます。
同社は2010年に経営破綻しましたが、その後、企業再生支援機構の主導のもとで大規模なリストラや路線見直しなどの経営改革を断行しました。
その結果、劇的なV字回復を遂げ、破綻からわずか2年8ヶ月後の2012年9月に東京証券取引所に再上場を果たしました。
この再上場により、企業再生支援機構は保有していた全株式を売却し、公的資金を上回る利益を得てイグジットを成功させました。
M&Aによるイグジットは、事業のさらなる成長やシナジー効果の創出を目的として行われます。
大手企業の傘下に入ることで、安定した経営基盤を得て飛躍を遂げた事例を紹介します。
C2Cチケット取引サービス「チケットキャンプ」を運営していた株式会社フンザは、2015年にミクシィグループにM&Aされました。
ミクシィグループは、フンザが持つプラットフォーム技術と顧客基盤を評価し、エンターテインメント事業強化の一環としてこのM&Aを実施しました。この事例は、成長途中のスタートアップが大手企業の傘下に入ることで、さらなる成長の機会を得た成功例として知られています。
スマートフォンで撮影した写真を使って高品質な年賀状やフォトブックを作成できるアプリを提供する株式会社スフィダンテは、2019年にSNS大手の株式会社ミクシィの完全子会社となりました。
ミクシィが展開する写真共有アプリ「家族アルバムみてね」との連携により、写真データの活用やサービス間の送客といったシナジー効果が見込まれました。
このM&Aは、双方のサービスの付加価値を高め、ユーザー体験を向上させることを目的とした戦略的なイグジットの好例です。
高級ブランドバッグの月額制レンタルサービス「Laxus」を運営するラクサス・テクノロジーズは、2019年にアパレル大手のワールドの傘下に入りました。
ラクサスは事業拡大のための資金調達と成長戦略を模索しており、一方のワールドは新たな収益源としてシェアリングエコノミー市場への参入を目指していました。
両社の戦略的なニーズが一致し、事業シナジーを目的としたM&Aが成立したことで、ラクサスはさらなる成長基盤を確保しました。
海外の有名な事例として、写真共有SNSのInstagramが挙げられます。
同社は創業からわずか2年、従業員13人という小規模な段階で、2012年にFacebook(現:Meta)に約10億ドルで買収されました。
当時、Instagramに売上はほとんどありませんでしたが、急成長するユーザー数と将来的な脅威になると判断したFacebookが、将来への投資として高額な買収を決定しました。
このM&Aにより、InstagramはFacebookの強力なリソースを得て世界的なサービスへと成長を遂げました。
ここでは、イグジット戦略を検討する経営者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
戦略立案のタイミングや重要性、具体的なコスト、そして失敗のリスクなど、実践的な疑問にお答えします。
イグジット戦略は、会社の設立や事業計画の策定段階から検討を始めることが理想的です。早い段階からイグジットを視野に入れることで、事業の成長戦略や資本政策、組織体制の構築を計画的に進めることが可能となり、いざイグジットを目指す際にスムーズな移行につながります。
ベンチャー企業やスタートアップにとってイグジット戦略が重要な理由は、投資家へのリターンを実現するためと、創業者自身が経済的な対価を得るためです。投資家は出資した企業がIPOやM&Aを通じてイグジットを達成することで、初めて投資資金を回収し利益を得られるため、イグジットは投資契約上の重要なゴールです。また、成功したイグジットは創業者に大きな利益をもたらし、次の事業への挑戦や社会貢献活動の原資となります。
IPOの準備には、主に監査法人への監査報酬、主幹事証券会社へのコンサルティング料や株式の引受手数料、証券取引所への上場審査料や新規上場料などがかかります。これに加えて、目論見書作成費や弁護士費用なども発生し、総額は数千万円から数億円規模に達することが一般的です。
イグジットに失敗する主な原因は、事業計画の未達や業績悪化による企業価値の低下が多いです。市場環境の急変や競合の台頭も大きく影響します。
M&Aでは買い手が見つからない、条件が折り合わないといったケースや、IPOでは審査基準を満たす内部管理体制を構築できない、コンプライアンス上の問題が発覚するといった原因で失敗する場合があります。
本記事のまとめとして、イグジット戦略は企業と創業者、投資家が次のステージへ進むための重要な経営判断であることが挙げられます。
主な手法であるM&AとIPOには、それぞれ明確なメリットとデメリットが存在します。
M&Aは比較的短期間かつ確実に実行できる可能性がある一方、経営権を手放すことになります。
対照的にIPOは、大きな利益と経営の独立性を維持できる可能性があるものの、長い準備期間と多大なコスト、そして上場後の責任が伴います。
自社の事業フェーズ、成長戦略、市場環境、そして創業者が描く将来像を総合的に考慮し、最適なイグジット戦略を選択することが成功への鍵となります。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください