
中小企業において経営者の高齢化も課題となる中、「事業承継」に対するニーズは年々拡大しています。
一方で、事業承継について具体的にどんなものかを把握できていない方や、「そもそも何から始めればいいのか」「どのような選択肢があるのか」と悩んでいる中小企業の経営者の方も多いのが現状です。
本記事では、事業承継の目的や課題、重要性についてわかりやすく解説し、事業を承継するための具体的な方法や成功のポイントまでを掘り下げていきます。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぎ、事業を継続していく一連のプロセスのことです。これは単に会社の所有権を移すだけでなく、経営理念、従業員、取引先との関係など、事業を取り巻くあらゆる要素を次世代に引き継ぐことを意味します。
承継の対象は企業の規模や形態によって異なりますが、経営権、資産、そして目に見えない知的資産が主な要素となります。
特に中小企業においては、経営者の高齢化が進む中で後継者が見つからないことによる廃業が増加傾向にあり、事業承継は喫緊の課題となっています。
スムーズな事業承継は、従業員の雇用維持、地域経済の活性化、そして企業の永続的な発展に繋がるため、計画的な準備が不可欠です。
「事業承継」と「事業継承」の違いについて、どちらも事業を次の世代に引き継ぐことを意味する言葉として使われますが、引き継ぐ対象の抽象度によって意味合いが異なるとされています。
「承継」は経営理念や精神など抽象的なものを、一方で「継承」は権利や財産など具体的なものを指す傾向があります。
法律や行政の文書、またビジネスの現場では一般的に「事業承継」という表現が用いられることが多いです。例えば、中小企業庁が発行する事業承継に関するガイドラインや支援策でも「事業承継」という言葉が採用されています。
事業全体や企業理念など、形のないものを含めて引き継ぐ行為全般を指す場合には「事業承継」を使用することが適切です。

事業承継では、単に会社名義を変更するだけでなく、様々な引き継ぐべき要素が存在します。
主なものとして、
の3つが挙げられます。
これらの要素を適切に引き継ぐことは、事業の持続的な成長と発展を実現する上で非常に重要です。
経営権の承継とは、会社の意思決定を行う権利と責任を後継者に引き継ぐことです。
具体的には、会社の株式を後継者に譲渡し、株主総会における議決権の過半数を取得させることで、経営の支配権を移転させます。特に中小企業の場合、現経営者がほとんどの株式を保有しているケースが多く、この株式の移転が経営権承継の中心となります。
また、代表取締役としての地位や取締役会の構成も重要な要素であり、後継者が円滑に経営を執行できるよう、適切な役職の承継も必要不可欠です。円滑な経営権の承継は、事業の継続性や取引先との関係維持に直結するため、非常に重要な要素といえます。
株式の譲渡方法や評価方法など、専門的な知識も必要となるため、税理士や弁護士などの専門家のアドバイスを受けながら進めるのが一般的です。
資産の承継とは、会社が保有する様々な財産を後継者に引き継ぐことを指します。
これには、現金や預金、売掛金などの流動資産、土地や建物、機械設備などの不動産や固定資産、そして最も重要な要素の一つである株式が含まれます。特に、非上場株式の場合、その評価は専門的な知識を要し、相続や贈与の際には高額な税金が発生する可能性があるため、事前の税務対策が不可欠です。
また、会社の事業用資産だけでなく、現経営者の個人資産が事業と密接に関わっている場合(例えば、経営者個人の不動産を会社が借り上げている場合など)も少なくありません。これらの資産をどのように引き継ぐかによって、後継者の負担や事業の継続性に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
知的資産の承継とは、会計帳簿には載らないものの、企業の競争力の源泉となる無形資産を後継者に引き継ぐことです。
これには、長年にわたって培われてきた技術やノウハウ、顧客との信頼関係、ブランドイメージ、従業員の持つスキルや知識、組織文化などが含まれます。知的財産として法的に保護されている特許や商標だけでなく、経営者のリーダーシップ、従業員の士気、企業風土といった要素も、事業の継続性において非常に重要な知的資産です。
これらの目に見えない資産は、企業価値を大きく左右するため、後継者がこれらの知的資産を理解し、活用できるような形で承継することが求められ、後継者が既存の顧客と顔を合わせる等、顧客との関係性を構築する機会を設けるといった工夫も重要です。

事業承継には主に3つの方法があります。
1.親族内承継
2.社内承継(親族外承継)
3.M&Aによる事業承継(第三者への承継)
それぞれメリット・デメリットがあり、自社の状況や後継者候補の有無によって最適な選択肢が異なります。それぞれの方法を理解し、自社にとって最適な事業承継の方法を検討することが重要です。
親族内承継とは、現経営者の家族である子や孫、兄弟姉妹のほか、甥や姪などの中から後継者を選び、事業を引き継ぐ方法です。
これは、中小企業において最も一般的に行われてきた事業承継の形であり、日本企業の文化に深く根差しています。後継者教育を計画的に行える点や、家族間の合意形成が比較的容易である点が特徴です。
具体的には、まず後継者を役員や従業員として現場に迎え入れ、経営資源や物的資産の承継を数年かけて済ませた後に経営権の承継を実施するといった方法が考えられます。
親族内承継のメリットは以下の通りです。
・社内外の関係者からの理解が得やすい
取引先や金融機関、従業員にとって、経営者が変わっても経営の安定性が保たれるという安心感があり、事業への信頼が維持されやすくなります。
・早い段階から後継者候補を選ぶことができ、計画的に育成できる
これにより、経営理念や企業文化、独自の技術やノウハウといった無形資産も円滑に引き継ぐことができるため、事業の一貫性を保ちやすくなります。
・経営権、経営資源、物的資産などの承継時期を柔軟に決めることができる
親族内承継のデメリットは、以下の点が挙げられます。
・親族内に適任者がいない場合がある
親族の中に事業を継ぐ意思のある人がいなかったり、経営者としての能力や資質が不足していたりする場合、事業承継自体が難しくなります。
・親族間の対立が発生する可能性がある
複数の親族間で株式の承継や経営権を巡って意見が分かれたり、相続トラブルに発展したりするケースもあります。
・税負担が大きくなる可能性がある
株式や不動産などの資産を承継する際、高額な相続税や贈与税が発生することがあり、事前の税務対策が不可欠です。
社内承継(親族外承継)とは、現経営者の親族以外の社内の役員や従業員の中から後継者を選び、事業を引き継ぐ方法です。後継者の候補には、共同創業者や経営者の右腕を担ってきた役員、優秀な若手経営層などがあげられます。
長年会社に貢献し、企業の文化や事業内容を熟知している人物が後継者となるため、スムーズな引き継ぎが期待できます。特に、親族内に後継者が見当たらない場合や、親族が事業を継ぐ意思がない場合に有効な選択肢です。
現経営者以外の役員や従業員の理解と協力も不可欠であり、事前に十分なコミュニケーションを図ることが成功の鍵となります。近年では、内部昇格として、社長が勇退した後も社内の役員がそのまま社長になるケースが増加傾向にあります。
社内承継のメリットは、以下の点が挙げられます。
・承継後の経営がスムーズに進みやすい
後継者が会社の事業内容や企業文化、従業員、取引先との関係を深く理解しているため、事業の連続性が保たれやすいです。
・従業員のモチベーション維持につながる
身近な人物が後継者となるため、将来に対する不安が少なく、従業員のモチベーション維持にも繋がります。
・現経営者が安心して引退できる
長年苦楽を共にしてきた従業員に事業を引き継ぐことで、現経営者は安心して引退できるという精神的なメリットも得られます。
・情報漏洩のリスクを低減できる
M&Aに比べて秘密保持がしやすく、情報漏洩のリスクを低減できます。
社内承継のデメリットは、以下の点が挙げられます。
・後継者の辞退や従業員の離職リスクがある
他の役員や従業員との関係性の変化を気にして、後継者候補が辞退するケースや、
複数の後継者候補がいる場合に、選ばれなかった役員や従業員が離職してしまうリスクがあります。
・資金不足の問題
会社の株式の取得価額は、数千万から数億円に上ることもあり、役員や従業員が株式を買い取る際、資金不足の問題が生じることが多々あります。
・個人保証の問題
現経営者の金融機関に対する個人保証の引き継ぎが大きな課題となる場合があります。
後継者にとっては大きなリスクとなるため、金融機関との交渉や保証協会の保証制度の活用を検討する必要があります。
M&Aによる事業承継とは、親族や社内から後継者を選ぶのではなく、第三者の企業や個人に事業を引き継ぐ方法です。
この方法は、親族や社内に適切な後継者が見当たらない場合に、事業を継続させる有効な選択肢として近年注目されています。経営権や物的資産の承継に加え、技術やノウハウといった経営資源の引き継ぎも行われますが、これらはM&Aの実施前後に時間をかけて進めるケースもあります。
一般的に、経営権の承継である社長交代と、物的資産の承継である株式の引き継ぎは同時に行われることが多いです。
M&Aで事業承継するメリットは、主に以下の点が挙げられます。
・後継者不在の問題を解決できる
親族や社内に後継者が見つからない場合でも、後継者にふさわしい人を幅広く後継者を探し、事業を引き継ぐことが可能です。
・現経営者は売却益を得られる
会社の売却によりまとまった資金が得られるため、引退後の生活資金や新たな挑戦への資金に充てることができます。
・事業のさらなる成長が期待できる
買い手企業が持つ経営資源やノウハウを活用することで、自社単独では難しかった事業拡大や新分野への進出が可能になる場合があります。
・従業員の雇用維持に繋がる
事業が継続されるため、従業員の雇用が守られ、安心して働き続けられる環境を提供できます。
M&Aで事業承継を行う場合、以下のようなデメリットが考えられます。
・買い手が見つからない可能性があること
親族や社内への承継と異なり、M&Aは相手企業が存在することが前提となるため、買い手が見つからないリスクがあります。
・交渉が決裂したり、難航したりする可能性があること
買い手との間で条件や価格について利害が対立することもあるため、交渉がスムーズに進まないことがあります。
・希望する売却額で売却できない可能性があること
買い手と売り手の間に価格面での相違が生じ、会社の評価や市場環境によって、希望する金額で売却できない場合があります。。
これらのデメリットを回避し、トラブルに発展させないためにも、専門家を活用しスムーズに交渉を進めていくことが大切です。
事業承継の実施割合は、年々変化しています。かつては親族内承継が主流でしたが、近年は親族以外への承継が増加傾向にあります。
帝国データバンクの『全国「後継者不在率」動向調査(2024年)』によると、2024年には内部昇格(社内事業承継)が36.4%に達し、初めて同族承継(親族内事業承継)を上回りました。
M&Aによる承継も緩やかに増加しており、2024年の速報値では20.5%となっています。
この傾向は、中小企業における後継者不足の深刻化を背景に、多様な承継方法が選択されるようになっていることを示しています。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

事業承継は一朝一夕に完了するものではなく、計画的かつ段階的に進めることが重要です。
一般的な流れとして、以下の手順を考慮することが、スムーズな承継の実現に繋がります。
①経営状況や経営課題を可視化
②事業承継の種類に応じ専門家に相談
③事業承継計画を作成
④作成した計画に基づき、経営権・経営資源・物的資産を承継
⑤各種手続きと税務申告を実施
⑥関係者への周知とアフターフォロー
各ステップについて解説します。
事業承継の最初のステップは、現在の会社の経営状況を詳細に把握し、事業承継にあたっての課題を明確にすることです。
具体的には、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を分析し、収益性の高い商品やサービス、他社にはない強みや優位性、競合他社との比較など、経営全般の状況を把握します。特に株式の評価額は、承継方法や税金に大きく影響するため、専門家による正確な評価が不可欠です。
また、後継者候補の有無、相続財産の特定や相続税額のシミュレーション、親族への対応など、事業承継における潜在的な課題を事前に洗い出し、可視化しておくことで、その後の対策を立てやすくなります。会社の現状を客観的に評価することは、事業承継を成功させるための重要な土台となります。
経営状況や課題が可視化できたら、次に、どの事業承継の種類が自社に最適かを見極め、それぞれの種類に応じた専門家に相談することが重要です。
例えば、親族内承継を検討している場合は、相続税対策や株式評価に詳しい税理士や弁護士に相談し、親族間の合意形成や遺産分割についてもアドバイスを求めることが有効です。
社内承継を検討している場合は、後継者への株式譲渡の方法や個人保証の引き継ぎなどについて、税理士や金融機関に相談する必要があります。
M&Aによる事業承継を検討する場合は、M&A仲介会社や金融機関のM&A部門に相談し、最適な買い手企業の探索や交渉のサポートを受けることが不可欠です。専門家の知見を借りることで、複雑な手続きや法務・税務に関する問題をスムーズに解決し、適切な判断を下すことができます。
なお、後継者が未定である場合には、民間のM&A仲介会社や各都道府県に設置されている事業引継ぎ支援センターに相談してみましょう。
専門家からのアドバイスを踏まえ、具体的な事業承継計画を策定します。この計画は、いつ、誰に、何を、どのように引き継ぐのかを明確にするためのロードマップとなります。
計画には、後継者の選定と育成計画、株式の譲渡方法や時期、資産の承継方法、相続税や贈与税などの税務対策、役員構成の変更、関係者への周知方法などが盛り込まれます。事業承継にかかる期間や費用についても具体的に記載し、具体的なスケジュールを立てることが重要です。
事業承継計画は一度作成したら終わりではなく、状況の変化に応じて柔軟に見直し、修正していく必要があります。関係者全員が計画を共有し、協力体制を築くことが大切です。
事業承継計画が策定されたら、その計画に基づき、実際に経営権や経営資源、物的資産の承継を進めていきます。
経営権の承継は、主に株式の譲渡によって行われ、必要に応じて取締役会や株主総会の承認を得る手続きも伴います。経営資源の承継には、顧客リストやサプライヤーとの契約、従業員の引き継ぎ、独自のノウハウや技術の伝授などが含まれます。物的資産の承継では、事業用不動産や設備、車両などの所有権移転手続きを行い、必要に応じて名義変更や登記変更を実施します。
経営権、経営資源、物的資産の承継が完了したら、各種法的な手続きと税務申告を行います。会社法の規定に基づき、代表取締役の変更登記や役員変更登記、必要に応じて定款の変更などを行います。
特に重要なのが、相続税や贈与税、所得税などの税務申告です。株式や不動産などの資産を承継する際には、多額の税金が発生する可能性があるため、事前に税理士と連携し、適切な納税計画を立てておくことが不可欠です。
事業承継税制などの特例制度を活用できる場合もあるため、適用条件や必要書類について確認し、漏れなく手続きを進めることが求められます。これらの手続きを怠ると、後々トラブルに発展する可能性があるため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが重要になります。
事業承継が完了した後も、関係者への周知とアフターフォローは非常に重要です。
まずは、従業員、取引先、金融機関など、すべての関係者に対して、事業承継が完了したことと、新体制について丁寧に説明を行います。特に、現経営者から後継者への引き継ぎ期間中に、関係者との面会や挨拶を共同で行うことで、信頼関係の継続を図ることができます。
承継後も現経営者が一定期間、顧問として事業に関わるなど、後継者へのアフターフォローを行うことも有効です。関係者への丁寧な対応は、事業承継後の企業の評判や信用を維持するためにも重要です。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

中小企業の事業承継は、経営者にとって大きな決断であり、多くの課題を伴います。
しかし、国や自治体、金融機関などによって、様々な支援策が用意されており、これらの支援策をうまく活用することで、事業承継を円滑に進めることもできます。
特に、M&Aを検討している企業にとって、公的な支援は大きな助けになることもあります。
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業が事業承継やM&Aを円滑に進めるための公的な支援制度です。
この補助金は、事業の再編や事業統合を促進し、後継者が事業を引き継ぐ際の費用負担を軽減することを目的としています。
具体的には、「M&A支援機関登録制度」に登録のあるM&A専門家を活用する際の手数料やデューデリジェンス費用、表明保証保険料などの経費、さらに事業承継後の新しい設備投資費用などが補助対象となる場合があり、廃業費用の一部も補助対象に含まれることがあります。
補助金には複数の類型があり、それぞれに異なる要件や補助率、上限額が設定されているため、自社の状況に最も適した類型を選択し、計画的に申請を進めることが重要です。
事業承継税制は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、後継者が取得した非上場会社の株式等について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。この制度は、後継者の税負担を軽減し、円滑な事業承継を支援することを目的としています。
この税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
2018年度の税制改正では、従来の「一般措置」に加え、10年間の期間限定で「特例措置」が創設されました。特例措置では、納税猶予の対象となる非上場株式の制限(総株式数の3分の2まで)が撤廃され、納税猶予割合が80%から100%に引き上げられるなど、一般措置よりも優遇された内容となっています。
特例措置の適用を受けるには、「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。
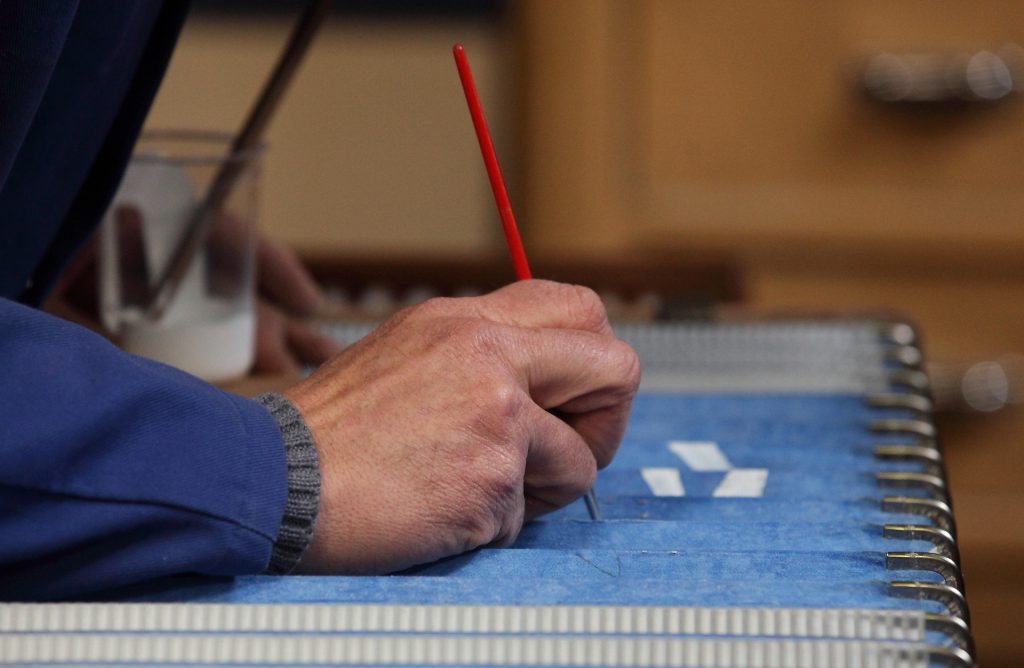
事業承継を成功させるためには、多岐にわたる要素を考慮し、計画的に進めることが不可欠です。
ここでは、事業承継を円滑に進め、成功に導くためのポイントをいくつか紹介します。
事業承継を成功させるための最も重要なポイントの一つは、早期に準備を開始することです。
事業承継には、後継者の選定・育成、会社の経営状況の把握、資産の評価、税務対策、法的手続きなど、多くの工程が含まれます。これらは数ヶ月で完了するものではなく、数年単位の時間を要することが一般的です。特に、後継者の育成には十分な時間をかける必要があり、経営者としてのスキルや知識だけでなく、経営理念や企業文化を理解し、浸透させるためには実践的な経験が不可欠です。
早期に準備を開始することで、選択肢を増やし、予期せぬ問題が発生した場合でも柔軟に対応できる余地が生まれます。漠然とした不安を抱えるのではなく、まずは事業承継の計画を立てることから始めることが、成功への第一歩となります。
特に親族内承継を検討している場合、親族家族間での十分な話し合いは不可欠です。
事業承継は、単なる財産の引き継ぎではなく、家族の生活や関係性にも大きな影響を与えるため、感情的な問題が発生しやすい側面があります。後継者候補の意向確認はもちろんのこと、後継者とならない親族への配慮や、相続財産の公平な分配についても、事前に話し合いの場を設けることが重要です。
すべての親族が納得できる形で承継を進めるためには、オープンなコミュニケーションと相互理解が重要で、必要に応じ第三者の専門家(弁護士や家族信託コンサルタントなど)を交えて話し合いを進めることも検討すべきです。これにより、将来的な相続トラブルのリスクを低減しスムーズに進めやすくなります。
事業承継は、法務、税務、労務、財務など、多岐にわたる専門知識を必要とする複雑なプロセスです。
そのため、事業承継の成功には、弁護士、税理士、公認会計士、中小企業診断士、M&Aアドバイザーなどの専門家である士業のサポートが不可欠です。
専門家は、自社の状況を客観的に評価し、最適な事業承継の方法やスキームを提案してくれるだけでなく、複雑な手続きや交渉を代行してくれます。
例えば、株式評価や税務対策においては税理士が、法務問題や契約書の作成においては弁護士が、M&AのプロセスにおいてはM&Aアドバイザーがそれぞれ専門的なアドバイスをもらうことができます。経験豊富な専門家からのアドバイスを受けることで、リスクを低減やスムーズかつ確実な事業承継の進行が可能です。
事業承継を成功させるためには、国や自治体が提供する税制や補助金制度を積極的に活用することが重要です。特に、事業承継税制は、非上場株式の贈与税や相続税の納税を猶予する特例措置であり、多額の税負担を軽減できる可能性があります。
また、事業承継・引継ぎ補助金は、M&Aの費用や事業再編費用などを補助してくれるため、資金的な負担を軽減できることがあります。
制度を最大限に活用するためには、事前に情報収集を行い、税理士などの専門家と連携して、自社が対象となる制度を特定し、適切な手続きを行うことが不可欠です。これらの支援制度をうまく活用することで、事業承継に伴う経済的な負担を軽減できます。

事業承継に失敗した場合、企業経営に深刻な影響を及ぼす様々なリスクが伴います。後継者選びの失敗や準備不足は、企業の存続そのものを危うくする可能性があります。
例えば、後継者が経営能力を欠いていたり、従業員からの信頼を得られなかったりすると、業績の悪化や人材の流出を招く恐れがあります。また、親族間の承継においては、相続を巡る争いが事業に悪影響を及ぼし、会社が分裂する事態に発展することもあります。さらに、税務対策の不備によって高額な税金が発生し、企業の資金繰りを圧迫する可能性も考えられます。
最悪の場合、事業の継続が不可能となり、廃業に追い込まれるケースも少なくありません。廃業は、従業員の失業や取引先の損失、地域経済への悪影響など、広範囲にわたる負の影響をもたらします。これらのリスクを回避するためには、早期から計画的に準備を進め、専門家のサポートを得ながら慎重に事業承継を進めることが不可欠です。

中小企業の事業承継は、少子高齢化や経済状況の変化といった外部要因と、企業固有の内部要因が複合的に絡み合い、多くの課題を抱えています。
中小企業が抱える最も深刻な課題の一つが、後継者不足です。
少子高齢化の進行により、親族内に後継者となるべき人材がいないケースが増加しています。
親族がいても、多様な価値観の中で、事業を継ぐことへの意欲が低い、あるいは別の道を歩むことを選択するといったケースも少なくありません。
社内承継を検討しても、会社の株式を買い取る資金力が不足している、あるいは個人保証の引き継ぎがネックとなるなど、様々な問題が生じることがあります。
結果として、後継者が見つからないまま、廃業を選択せざるを得ない中小企業が増加しているのが現状です。この問題は、地域経済の活力を低下させるだけでなく、長年培われてきた技術やノウハウが失われることにも繋がるため、社会全体にとって大きな損失となります。
事業承継において、資金調達と税負担は大きな課題となります。
親族内承継や社内承継の場合、後継者が会社の株式を買い取るための資金をどう調達するかが問題となることがあります。非上場株式の場合、評価額が高額になることもあり、後継者の自己資金だけでは賄いきれないケースも少なくありません。金融機関からの融資を受ける場合でも、後継者の信用力や会社の業績が問われます。
また、株式の贈与や相続には、高額な贈与税や相続税が発生する可能性があります。事業承継税制などの特例制度を活用することで、税負担を軽減できる可能性はありますが、適用要件が複雑であり、事前の計画的な対策が不可欠です。これらの資金面での課題は、後継者の確保や承継後の経営に大きな影響を及ぼします。
中小企業の事業承継において、現経営者が金融機関に対して負っている個人保証や連帯保証の引き継ぎは、非常に大きな課題となります。
多くの中小企業では、会社の借入金に対し、経営者個人が連帯保証人となっているケースが一般的です。事業承継後もこの個人保証が引き継がれるとなると、後継者にとっては大きなリスクとなり、事業承継をためらう要因となることがあります。
金融機関との交渉によって、個人保証の解除や保証協会の保証制度の活用など、様々な解決策が考えられますが、金融機関側の判断によって引き継ぎがスムーズにいかないケースも少なくありません。この問題は、後継者候補が見つかったとしても、承継の実現を阻む大きな障壁となるため、早い段階で金融機関と交渉し、解決策を模索することが重要です。
事業承継は、企業の存続と発展にとって不可欠な経営課題であり、その成功には早期からの計画的な準備が何よりも重要です。
後継者の選定と育成、会社の経営状況の正確な把握、法務・税務対策、そして関係者との円滑なコミュニケーションなど、多岐にわたるプロセスを数年かけて進める必要があります。
親族内承継、社内承継、M&Aによる第三者への承継といった選択肢の中から、自社に最適な方法を見極め、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、具体的な計画を策定することが成功の鍵となります。
後継者不足や資金調達、個人保証の問題など、中小企業が抱える様々な課題を乗り越えるためには、弁護士や税理士、M&Aアドバイザーなどの専門家からのサポートも不可欠です。不安を抱えるのではなく、まずは一歩を踏み出し、専門家とともに事業承継の準備を始めることが、企業を未来へと繋ぐための最善の策となります。
事業承継に関する疑問や質問は多岐にわたります。
ここでは、事業承継を検討している経営者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。これらの情報を参考に、自身の事業承継計画に役立ててください。
A:事業承継にかかる期間は、企業の規模や複雑さ、後継者の有無、承継方法などによって大きく異なりますが、一般的には数年から10年程度の期間を要すると言われています。
特に、後継者の育成や経営ノウハウの引き継ぎには十分な時間が必要です。
A:事業承継にかかる費用は、承継方法や専門家への依頼内容によって大きく異なります。
M&Aを選択した場合、仲介手数料やデューデリジェンス費用などが発生し、一般的に数百万円から数千万円程度になることもあります。
事業承継・引継ぎ補助金などの国の支援制度を活用することで、費用負担を軽減できる場合もあるため、専門家と相談しながら計画的に進めることが大切です。
A:はい、可能です。
親族内や社内に適切な後継者がいない場合でも、M&A(第三者への承継)という選択肢があります。M&A仲介会社などを活用することで、自社の事業を引き継いでくれる企業や個人を見つけることができます。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください