
会社売却とは、自社の経営権を第三者に譲渡することです。近年、経営戦略の一つとして会社売却を検討する企業が増加しています。
会社売却には、売却益を得られる、企業のさらなる成長が見込める、後継者問題を解決できるなど、多くのメリットが期待できる一方で、注意点も存在します。
本記事では、会社売却の基礎知識から具体的な進め方、評価方法、注意点、成功のポイントまで、会社売却を検討している経営者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

会社売却とは、その名の通り「会社(自社)を売却すること」、つまり会社の所有権を第三者に譲渡し、その対価として金銭を得る行為を指します。
一般的に会社売却はM&A(Mergers&Acquisitions:合併と買収)の一種として位置づけられ、M&Aは買い手側から見た「買収」という言葉に相当し、会社売却は売り手側から見た表現です。
会社売却では、株式譲渡によって経営権を移転するケースが多く見られます。会社が所有する資産や負債だけでなく、長年築き上げてきた取引先との関係や従業員なども譲渡の対象となるため、売却によって新たな経営資源を獲得し事業のさらなる成長を期待できます。
近年、中小企業において会社売却が増加している背景には、複数の理由が挙げられます。
最も大きな理由の一つは、多くの企業で経営者の高齢化が進む一方で、親族内や社内に適切な後継者が見つからない「後継者不在問題」が深刻化している点です。
帝国データバンクの調査によると、中小企業の半数以上が後継者不在に悩んでおり、事業承継の手段としてM&Aや会社売却を選択するケースが増えています。
これにより長年培ってきた技術やノウハウ、雇用が守られ、企業の存続が可能となります。
また、業界全体の再編が進む中で、自社の将来に不安を感じ、大手企業の傘下に入ることで経営基盤の安定や事業発展を目指す企業も少なくありません。
不採算事業を切り離し、主力事業に経営資源を集中させる「選択と集中」を目的に会社売却を行うケースや、ベンチャー企業が創業者利益の獲得(イグジット)を目的に会社売却を選ぶこともあります。さらに、M&Aを支援する専門機関や民間企業の増加、国の支援制度の整備、M&Aに対する社会的なイメージの向上なども、中小企業の会社売却が増加している理由として挙げられます。

会社売却は、経営者にとって大きな決断ですが、同時に様々なメリットをもたらす可能性があります。
会社を手放すだけでなく、経営者自身の新たなキャリア形成や、会社のさらなる発展につながることも期待できます。具体的にどのようなメリットがあるのかを以下で詳しく解説します。
会社売却は、自社の事業をさらに発展させる大きなメリットをもたらします。買い手企業が持つ豊富な資金、人材、技術、ノウハウ、顧客基盤といった経営リソースを活用することで、自社単独では達成が困難だった規模の事業成長が期待できます。
例えば、大手グループの傘下に入ることで資金面での制約が解消され、大規模な設備投資や研究開発が可能になるでしょう。
また、買い手企業が同じ事業を営んでいる場合、両社の技術や営業ルートを組み合わせることで、新たなシナジー効果が生まれ、より大きな成果を生み出す可能性もあります。
譲渡先のブランド力が高い場合や経営基盤が安定している場合、採用面でもプラスの影響が期待でき、優秀な人材の確保につながることも少なくありません。
中小企業の経営者にとって深刻な問題の一つが、事業承継です。
親族内や社内に適切な後継者が見つからず、事業の継続に悩むケースは少なくありません。少子化の影響に加え、現代では経営者の子供が事業を継ぐという価値観も変化しており、後継者不在の企業は増加傾向にあります。このような状況において、会社売却は事業承継問題を解決する有効な手段となります。
売却によって新たな経営者が見つかることで、会社の存続と発展が期待でき、経営者自身の引退後の不安も解消されるでしょう。
多くの中小企業では、会社が金融機関から融資を受ける際に、経営者自身が連帯保証人となる個人保証が設定されています。これは経営者にとって大きな負担であり、会社の経営が困難になった場合、個人の資産まで危険にさらされるリスクがあります。
しかし、会社売却を行うことで、この個人保証を解消できる可能性が高まります。会社を売却し、経営権が買い手企業に移転すれば、原則として個人保証も買い手企業に引き継がれることになります。
これにより、現経営者は個人保証という重圧から解放され、精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。
会社を売却することで、経営者は、これまでの企業価値に見合ったまとまった金額を手元に得られます。
この売却益は、創業者が新たな事業を立ち上げるための資金として活用したり、引退後の生活資金、あるいは残っている借入金の返済に充てるなど、幅広い用途に利用できるでしょう。
特に、上場企業の場合は株主が複数存在するため、経営者が自由に使える売却益は限られる場合がありますが、中小企業のオーナー経営者の場合は、原則として個人資産として多額の売却益を得ることが可能です。
会社の売却は、単に経営権が移るだけでなく、そこで働く従業員の処遇にも影響を与えます。会社売却を選択することで、従業員の雇用を維持できるという大きなメリットがあります。
もし後継者が見つからずに会社を廃業せざるを得なくなった場合、従業員は職を失うことになります。
しかし、会社売却によって事業が継続されれば、従業員の雇用は基本的に守られます。
買い手企業にとっても、対象企業の従業員は、事業を運営する上で不可欠な人材やノウハウの集合体であるため、従業員の継続雇用は重要な要素です。売却後も従業員が安心して働き続けられる環境が維持されることで、従業員の生活とモチベーションを守り、事業の安定的な継続に貢献できます。
会社売却は、事業の効率化を図る上でも有効なメリットとなります。
特に、複数の事業を展開している企業で、収益性が低い、あるいは将来性が見込めないノンコア事業を抱えている場合、その事業を切り離して売却することで、経営資源を自社の主力事業に集中させることが可能になります。
これにより、資金や人材、設備などのリソースが分散することなく、コア事業の強化や新規事業への投資に集約できるため、全体の経営効率が向上し、収益性の改善が期待できます。
自社にとっては利益になりにくい事業であっても、他社にとっては技術の活用や販路の拡大、業務効率化につながる場合もあり、双方にとってメリットのある選択肢となるでしょう。
もし会社を存続させることが困難になった場合、廃業という選択肢も考えられます。
しかし、廃業には多くの費用と手間がかかります。例えば、会社を清算するためには、従業員の解雇費用、未払いの債務の整理、事務所の原状回復費用、資産の売却費用、税金や専門家への報酬など、多岐にわたるコストが発生します。
これらの費用は、会社の規模や状況によって異なりますが、決して少なくない負担となるでしょう。会社売却を選択すれば、これらの廃業にかかる費用を大幅に削減できるというメリットがあります。売却によって、買い手企業が会社の資産や負債、従業員を引き継ぐため、売り手側は廃業に伴うコストを負担する必要がなくなります。
これにより、経営者は余分な出費を抑え、新たなスタートを切るための資金を確保できる可能性が高まります。
会社売却には多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点も存在します。これらの注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることで、予期せぬトラブルを避け、円滑な売却を実現できます。以下に、会社売却で特に注意すべき点を詳しく解説します。
会社売却には様々な方法(スキーム)があり、それぞれ特徴が異なります。代表的なものには株式譲渡や事業譲渡、合併などがあります。どの売却方法を選択するかによって、税金や手続きの複雑さ、売却後の経営者の関わり方、従業員や取引先への影響などが大きく変わってきます。
例えば、会社全体を売却したい場合は株式譲渡が一般的ですが、特定の事業のみを切り離したい場合は事業譲渡が適しています。
合併は会社同士が一体となるため、組織文化の統合が課題となることもあります。最適な売却方法を選ぶためには、まず売却の目的を明確にし、自社の状況や将来の展望を考慮した上で、それぞれの方法のメリット・デメリットを十分に比較検討する必要があります。専門家と相談しながら、自社にとって最も有利で円滑な売却が実現できる方法を見極めることが重要です。
会社売却においては、必ずしも希望する条件、特に売却額で売却が実現するとは限りません。
売却価格は、企業の業績や財務状況、市場の需要、将来性など、様々な要因によって決定されます。特に、直近の業績が低迷している場合や、簿外債務などのリスクを抱えている場合、買い手からの評価が低くなり、希望する売却額に届かない可能性があります。
また、買い手側も自社の事業戦略や投資回収の見込みに基づいて買収価格を提示するため、売り手側の期待と乖離が生じることも少なくありません。希望する条件で売却できない可能性も考慮し、現実的な売却目標を設定することが重要です。
そのためには、事前に自社の企業価値を適正に評価し、市場の動向や買い手のニーズを把握しておくことが不可欠です。
会社売却は、従業員の雇用維持というメリットがある一方で、一部の従業員が退職する可能性もゼロではありません。特に、経営権の移行に伴い、雇用条件や労働条件が変更されたり、買い手企業の企業文化や経営方針に馴染めなかったりする場合、従業員が不安を感じて転職を考えることがあります。
また、買い手企業による組織再編や事業統合によって、人員削減や配置転換が行われる可能性も考慮しておくべきでしょう。従業員のモチベーション低下や主要な人材の流出は、売却後の事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、会社売却の交渉段階から従業員の処遇について買い手側と十分にすり合わせを行い、売却決定後も従業員に対して丁寧な説明とフォローを行うことが重要です。
会社売却後、売り手である旧経営者には一定期間、競業避止義務が課されることが一般的です。
これは、売却した事業と同種または類似の事業を一定期間行わないという契約上の制限であり、買い手企業が買収した事業の価値を維持し、競争上の不利益を被らないようにするために設けられます。
また、M&Aの契約内容によっては、旧経営者が売却後も一定期間、買収された会社の役員や顧問として残る「ロックアップ」条項が盛り込まれることもあります。
これは、スムーズな事業引き継ぎや、買い手企業が求める専門知識・ノウハウの提供を目的としていますが、旧経営者にとっては一時的に自由な事業活動が制限されることを意味します。売却後のキャリアプランを考える上で、これらの制限について契約内容を十分に確認し、理解しておくことが重要です。
会社売却によって得られる売却益には税金が課せられます。
売却方法によって税金の種類や税率が異なりますが、最も一般的な株式譲渡の場合、個人の株主が株式を譲渡して得た所得は「譲渡所得」とみなされ、所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。具体的には、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合わせた合計約20.315%の税率が適用されます。この税金は、売却益の約2割を占めるため、手元に残る金額に大きな影響を与えます。
そのため、税金を考慮せずに売却益の計画を立ててしまうと、資金運用計画に支障が生じる可能性があります。会社売却を検討する際には、事前に税理士などの専門家と相談し、発生する税金について正確に把握し、資金計画に含めておくことが非常に重要です。
会社売却の交渉を進める上で、情報漏洩は極めて重大なリスクとなります。
売却に関する情報は非常に機密性が高く、従業員、取引先、顧客、競合他社などに知られてしまうと、様々な問題が発生する可能性があります。例えば、従業員が売却に不安を感じて離職したり、取引先が取引関係を見直したりする事態も考えられます。
また、競合他社に情報が漏れれば、事業戦略に悪用される恐れもあります。M&Aの交渉中は、企業概要書や財務資料など、機密性の高い情報をやり取りするため、細心の注意が必要です。情報漏洩を防ぐためには、M&A仲介会社などの専門家と秘密保持契約(NDA)を締結し、情報管理を徹底することが不可欠です。
また、交渉の初期段階では、具体的な社名や個人名が特定できるような情報は開示しないなど、段階的に情報を開示する工夫も求められます。
会社売却は、適切なタイミングで行わないと、希望通りの売却ができなかったり、最悪の場合、売却自体が失敗に終わったりする可能性が高まります。
例えば、会社の業績が悪化してから売却を検討すると、企業価値が低下しているため、買い手が見つかりにくくなったり、売却価格が低くなる傾向があります。経営者の体力や気力が衰えてからでは、売却プロセスを進める上での負担が大きくなり、冷静な判断が難しくなることも考えられます。また、業界再編の波に乗り遅れると、競争環境が厳しくなり、売却の機会を逸する可能性もあります。
業績が好調な時期や、業界再編が進む前など、企業価値が高く、買い手にとって魅力的なタイミングを見極めることが、会社売却を成功させる上で非常に重要です。そのためには、日頃から自社の状況や業界動向を把握し、早めに売却の検討を始めることが望ましいでしょう。
会社売却は、買い手が見つかるまでにかなりの時間を要するプロセスです。一般的に、買い手探しから最終的な契約締結までには数ヶ月から1年以上かかることも珍しくありません。
特に、自社の事業内容や規模、希望する売却条件などによっては、買い手候補が限定される場合もあります。買い手候補の選定、秘密保持契約の締結、企業概要書の提示、トップ面談、デューデリジェンスなど、多くの段階を踏む必要があり、それぞれの段階で交渉や調整に時間がかかります。
買い手探しに時間がかかると、その間に会社の状況が変化したり、市場環境が変わったりするリスクも考えられます。そのため、会社売却を検討する際には、時間的な余裕を持って計画を立て、M&A仲介会社などの専門家と連携しながら、効率的に買い手を探すことが重要となります。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
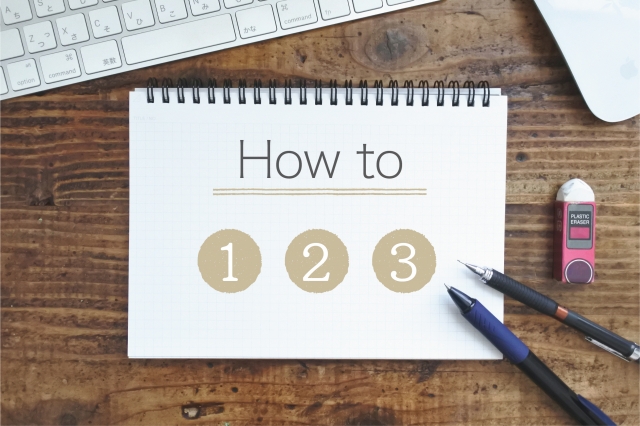
会社売却には主にいくつかの異なる方法が存在します。それぞれの方法には法的な手続き、税務上の取り扱い、売却後の経営権の行方などに違いがあります。経営者は自社の状況や売却の目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
株式譲渡は、会社売却において最も一般的に用いられる方法です。この方法では、売り手である会社の株主が、保有する株式を買い手企業に譲渡することで、会社の経営権や支配権を移転します。
株式会社の場合、株式の過半数を譲渡すれば経営権を移転できるため、会社全体を売却したい場合に適しています。株式譲渡の大きな特徴は、会社が法人格を維持したまま買い手企業の子会社となる点です。
そのため、原則として従業員の雇用契約や取引先との契約を個別に引き継ぐ必要がなく、手続きが比較的簡便であるというメリットがあります。また、売り手である株主は、株式の譲渡によって得た売却益に対して、所得税や住民税、復興特別所得税といった税金が課されますが、事業譲渡に比べて税負担が軽減されるケースが多いことも特徴です。
事業譲渡は、会社が営む事業の一部、あるいは全部を切り出して、第三者に売却する方法です。
株式譲渡とは異なり、会社の経営権そのものを譲渡するわけではなく、特定の事業部門や、その事業に関連する資産(設備、ブランド、顧客基盤など)、負債、従業員などを個別に売買します。この方法のメリットは、売り手会社がM&A後も法人格を維持し、売却した事業以外の事業は継続できる点にあります。不採算事業の整理や、主力事業への経営資源の集中を図りたい場合に有効な選択肢です。
しかし、事業譲渡では、譲渡する個々の資産や負債、契約について、それぞれ移転の手続きが必要となるため、株式譲渡に比べて手続きが複雑化し、時間や手間がかかる傾向があります。また、税務面では、売却益に対して法人税が課税されるだけでなく、譲渡対象となる資産の種類によっては消費税も発生することがあります。
合併とは、複数の会社が一体となって一つの会社になる組織再編の手法です。
大きく分けて、一方の会社が存続し、他方の会社が解散して存続会社に吸収される「吸収合併」と、全ての会社が解散して新たに会社を設立する「新設合併」の2種類があります。
会社売却の文脈では、売り手側が買い手企業に吸収される吸収合併が一般的です。合併の目的は、事業規模の拡大、重複部門の効率化、新たな技術やノウハウの獲得など多岐にわたります。
合併により、これまで別々に事業を行っていた会社が統合されるため、単独では実現できなかったシナジー効果を期待できるでしょう。ただし、会社全体が一体となるため、異なる企業文化や組織風土の統合(PMI)が課題となることがあります。また、株主総会の特別決議が必要となるなど、法的な手続きも複雑になります。
会社分割とは、一つの会社がその事業を二つ以上の事業に分割し、その分割した事業を他の会社に承継させる組織再編の手法です。会社分割には、会社が既存の事業を一部または全部を切り出して、新しく設立する会社に承継させる「新設分割」と、既存の会社に承継させる「吸収分割」があります。
会社売却の文脈では、主に特定の事業部門を切り離して売却したい場合に用いられます。
例えば、不採算事業を切り離して主力事業に集中したい、あるいは新規事業の資金を確保したいといった場合に活用されます。会社分割のメリットは、売却したい事業のみを切り離せるため、他の事業への影響を最小限に抑えられる点です。
ただし、事業譲渡と同様に、譲渡する事業に関連する個別の資産、負債、契約の移転手続きが必要となるため、手続きが複雑になる傾向があります。
会社売却は、多岐にわたるプロセスと専門的な知識を要する重要な意思決定です。この複雑な手続きを円滑に進めるためには、全体的な流れを事前に把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。以下に、会社売却の主な手順を詳細に解説します。
会社売却を検討する最初のステップは、売却の意思を明確にし、そのための準備を始めることです。
なぜ会社を売却したいのか、売却によって何を達成したいのかといった目的を明確にすることが重要です。例えば、後継者問題を解決したい、事業のさらなる成長を目指したい、あるいは経営者のリタイア資金を確保したいなど、売却理由は様々です。目的が明確であれば、それに合った売却方法や買い手候補の選定、交渉戦略を立てやすくなります。
また、売却に向けた準備として、自社の財務状況や事業内容を整理し、企業価値を把握するための資料作成に着手する必要があります。これは、買い手候補に自社の魅力を伝える上で不可欠な作業であり、M&A仲介会社などの専門家と協力しながら進めるのが一般的です。
会社売却の意思が固まったら、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)といった専門家との契約を検討します。
会社売却は、法務、税務、会計、交渉など多岐にわたる専門知識が必要となるため、自社だけで進めるのは非常に困難です。M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立って、マッチングから交渉、契約締結までの一連のプロセスをサポートします。
FAは、売り手または買い手の一方に寄り添い、M&A戦略の立案から実行までを支援します。専門家と契約することで、自社の企業価値の適切な評価、買い手候補の探索、条件交渉、法務・税務面のリスク回避など、様々な面で支援を受けられます。信頼できる専門家を選定することが、会社売却成功への重要な鍵となります。
M&A仲介会社と契約後、次のステップは買い手候補の選定です。専門家は、売り手企業の事業内容や企業文化、売却目的などを踏まえ、潜在的な買い手候補をリストアップします。
この段階では、業界内の同業他社だけでなく、異業種からの参入を検討している企業、投資ファンドなど、幅広い選択肢から検討が行われます。リストアップされた候補企業に対しては、秘密保持契約(NDA)を締結した上で、企業概要書(ノンネームシート)などの情報が開示され、関心のある買い手からのアプローチを待ちます。
買い手候補が複数現れた場合は、それぞれの企業の事業戦略や買収目的、提示される条件などを比較検討し、自社にとって最適なパートナーを見つけるためのマッチング作業が進められます。
買い手候補が絞り込まれたら、具体的な売却条件の交渉へと移行します。この段階では、売却価格だけでなく、従業員の雇用条件、役員の処遇、事業の継続性、取引先との関係など、多岐にわたる条件が話し合われます。交渉は売り手と買い手の双方の意向を擦り合わせる場であり、M&A仲介会社が間に入って調整役を担うことが一般的です。
各条件について詳細な議論を重ね、双方が納得できる合意点を見つけることが重要です。特に、売却価格は最終的な契約締結に直結するため、慎重に交渉を進める必要があります。また、交渉の過程で、後述するトップ面談や意向表明書の提示、基本合意契約の締結といった重要なステップを踏むことになります。
売却条件交渉の初期段階で行われるのがトップ面談です。これは売り手企業の経営者と買い手企業の経営者が直接顔を合わせ、お互いの経営理念や事業に対する考え方、将来のビジョンなどを共有する場です。トップ面談の目的は具体的な売却条件の交渉に入る前に、お互いの信頼関係を築きM&A後の企業統合を円滑に進めるための土台を作ることです。
この面談を通じて数字だけでは測れない経営者の人柄や熱意、企業文化への理解を深めることができます。トップ面談はM&Aの成否を左右する重要なステップの一つであり、お互いの相性を確認しM&A後のシナジー効果を具体的にイメージする上で不可欠な機会となります。
トップ面談などを経て、買い手企業が本格的な買収意思を固めた場合、売り手企業に対して「意向表明書」を提示します。意向表明書は、買い手企業が買収に関する具体的な意思と、その後の交渉における基本的な条件(買収価格の目安、買収スキーム、買収後の事業方針、デューデリジェンスの実施希望など)を記載した書類です。この書類には法的拘束力がないことが一般的ですが、買い手企業の真剣度を示す重要な意思表示となります。
意向表明書を受け取った売り手企業は、提示された条件を精査し、自社の売却目的や希望条件と合致するかどうかを検討します。この書類の内容が、その後の詳細な交渉の基礎となるため、慎重な検討が求められます。
意向表明書の提示と交渉を経て、売却に関して大枠の合意が得られた場合、「基本合意契約」を締結します。基本合意契約書は、現時点での両社の合意内容を明確にするための書類であり、一般的には法的拘束力を持たない条項(ノンバインディング条項)と法的拘束力を持つ条項(バインディング条項)が含まれます。法的拘束力を持つ条項としては、独占交渉権の付与(売り手が一定期間、他の買い手と交渉しないことの約束)や秘密保持義務などが挙げられます。
この契約は、今後のデューデリジェンスの実施や最終契約締結に向けたステップを確実にするためのものであり、まだ最終的な合意ではないことに注意が必要です。しかし、基本合意契約の締結は、M&Aのプロセスが次の段階に進む重要な節目となります。
基本合意契約の締結後、買い手企業は売り手企業に対して「買収監査(デューデリジェンス:DD)」を実施します。デューデリジェンスとは、買い手企業が、買収対象となる企業の財務、税務、法務、事業、労務、ITなどのあらゆる側面を詳細に調査し、リスクや問題点、そして隠れた価値を把握するために行う精密調査のことです。
公認会計士、弁護士、税理士などの専門家が派遣され、会社の帳簿、契約書、各種規程などを確認します。この調査によって、事前に売り手から提供された情報と実際の状況に差異がないか、簿外債務や訴訟リスクなど潜在的な問題がないかなどが徹底的に調べられますられます。
デューデリジェンスの結果は、最終的な売却価格や契約条件に大きく影響を与えるため、売り手企業は誠実かつ正確な情報開示を行うことが求められます。
デューデリジェンスの結果を踏まえ、双方の最終的な合意が得られた場合、「最終契約」を締結します。最終契約書は、M&Aのプロセスにおける最も重要な書類であり、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書など、選択した売却方法に応じた名称となります。
この契約書には、最終的な売却価格、譲渡の実行日(クロージング日)、売却後の保証事項、損害賠償に関する条項など、M&Aに関する全ての条件が詳細に記載され、法的な拘束力を持ちます。最終契約の締結をもって、M&Aのプロセスは実質的に完了し、会社の経営権が買い手企業に移転します。契約締結後は、契約内容に基づいて譲渡対価の支払いが行われ、必要な登記変更などの手続きが実施されます。
最終契約の締結後、経営権の移転に伴い、従業員や取引先などの関係者への情報開示を行う必要があります。これは非常にデリケートなプロセスであり、開示のタイミングと方法を誤ると、従業員の動揺や取引関係への悪影響を及ぼす可能性があります。
一般的には、最終契約が締結され、売却が確定した後に、適切なタイミングで開示が行われます。従業員に対しては、M&Aの目的、売却後の会社の展望、自身の雇用や待遇の変化について、経営者自身の言葉で丁寧に説明することが重要です。
また、取引先に対しても、M&Aによる事業継続性やサービス品質の維持について説明し、安心して取引を継続してもらえるよう配慮が必要です。M&A仲介会社などの専門家と相談し、情報開示の計画を事前に練り、適切な方法で実行することが、売却後の円滑な事業運営のために不可欠な注意点となります。
会社売却の最終段階として、経営統合(PMI:PostMergerIntegration)があります。
これは、M&Aが完了した後、買い手企業と買収された会社が、それぞれの組織、システム、文化などを統合し、M&Aの目的であるシナジー効果を最大限に引き出すためのプロセスです。
PMIは、単にシステムを統合するだけでなく、異なる企業文化を持つ両社の従業員が協力し、一体となって目標達成に向けて進むための組織づくりが重要になります。
具体的には、役職や業務内容の見直し、人事評価制度の統一、ITシステムの統合、経理や法務などのバックオフィス機能の統合などが挙げられます。PMIが円滑に進むかどうかは、M&Aの成功に直結するため、売却前から統合計画を立て、専門家の支援を受けながら戦略的に取り組むことが大切です。

会社売却において、売却価格がどのように決定されるかは、経営者にとって最も関心の高いポイントの一つです。会社の価値を客観的に評価する方法は複数あり、それぞれの方法で算出される評価額が異なる場合があるため、これらの評価方法を理解しておくことが重要です。
一般的に、企業価値評価には「コストアプローチ」「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」の3つの代表的な手法があります。
企業価値評価とは、会社の経済的な価値を算定するプロセスです。会社売却における売却価格は、この企業価値評価に基づいて決定されます。
企業価値は、単に帳簿上の資産の合計額だけではなく、将来生み出すであろう収益性や、無形資産(ブランド力、技術、顧客基盤など)も考慮して評価されます。評価方法にはいくつかの種類があり、どの方法を用いるかによって評価額が変動する可能性があるため、複数の手法を組み合わせて多角的に評価することが一般的です。
また、会社の規模や業種、M&Aの目的などによって、重視される評価方法も異なります。専門家による適切な企業価値評価は、売り手と買い手の間で適正な売却価格を交渉する上で不可欠な要素となります。
コストアプローチは、企業の保有する資産や負債を基に企業価値を評価する方法です。このアプローチでは、会社が現在保有している純資産の価値に着目します。主な計算方法として、簿価純資産の評価と時価純資産の評価があります。
簿価純資産の評価は、貸借対照表に記載されている帳簿上の資産の合計から、負債の合計を差し引いて純資産を算出する方法です。この方法は、客観的で分かりやすいというメリットがありますが、帳簿上の価値が必ずしも市場価値を反映しているとは限りません。
例えば、古い設備や不動産は帳簿上の価値よりも実際の市場価値が低い場合や、逆に簿外の優良資産があるにもかかわらず評価に反映されないことがあります。そのため、実際の企業価値とは乖離が生じる可能性があるため、他の評価方法と組み合わせて利用されることが一般的です。
時価純資産の評価は、企業の保有する資産と負債を現在の市場価格(時価)で評価し直し、その差額を純資産とする方法です。具体的には、不動産や有価証券などを時価に評価し直し、含み損益を考慮に入れます。また、貸倒引当金や退職給付引当金など、帳簿には現れていないものの将来発生しうる負債(簿外負債)も評価に含めます。
この方法により、企業の現在の正味の価値をより正確に把握できるため、より実態に即した企業価値を算出できます。ただし、時価評価には専門的な知識や情報が必要となるため、公認会計士や不動産鑑定士などの専門家による評価が不可欠です。
マーケットアプローチは、対象企業と類似する他社の市場での評価を参考に、企業価値を算出する方法です。市場の状況や類似企業の動向が直接的に反映されるため、客観性が高いとされています。このアプローチの代表的な計算方法として、「類似会社比較法」があります。
類似会社比較法は、M&Aの対象となる企業と事業内容、規模、収益性などが類似する上場企業の株価や財務指標を基に、対象企業の企業価値を評価する方法です。具体的には、類似会社の株価収益率(PER)や企業価値倍率(EV/EBITDA)などのマルチプル指標を用いて、対象企業の企業価値を算定します。この方法は、市場の評価が反映されるため客観性が高いとされますが、完全に類似する企業を見つけることが難しい場合や、市場の変動に影響されやすいという点に注意が必要です。
また、非上場の中小企業の場合、上場企業との比較では事業規模や流動性などに差があるため、調整が必要となることもあります。
インカムアプローチは、対象企業が将来生み出すと期待される収益やキャッシュフローに基づいて企業価値を評価する方法です。このアプローチは、将来の収益性を重視するため、特に成長性の高い企業や、独自の技術・ノウハウを持つ企業、事業再生を目的としたM&Aにおいて重要視されます。代表的な計算方法として、「DCF法」があります。
DCF法(Discounted Cash Flow法)とは、企業の将来のフリーキャッシュフロー(事業活動によって生み出される現金の流れ)を予測し、それを適切な割引率で現在価値に換算することで、企業価値を算定する方法です。この方法の最大の特長は、企業の将来的な収益力を直接的に評価できる点にあります。
企業の事業計画や成長戦略が適切に織り込まれるため、理論的には最も合理的な企業価値を算出できるとされています。しかし、将来のキャッシュフローの予測には、多くの仮定や前提条件が含まれるため、予測の正確性が評価結果に大きく影響します。また、割引率の設定も評価者の主観が入り込む余地があるため、専門的な知識と経験が不可欠となります。

会社売却を成功させるためには、多岐にわたる要素を考慮し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。単に売却価格を最大化するだけでなく、売却後の事業の安定や従業員の雇用維持など、経営者の目的を達成するためのポイントを押さえることが重要となります。以下に、会社売却を成功させるための主要なポイントを詳述します。
会社売却を成功させるための最初の、そして最も重要なポイントは、売却目的を明確にすることです。なぜ会社を売却したいのか、その理由を具体的に特定することが、その後の全てのプロセスにおいて羅針盤となります。
例えば、「後継者問題の解決」が主な目的であれば、従業員の雇用維持や事業の継続性を重視した買い手を選ぶべきでしょう。「創業者利益の獲得」が目的であれば、より高値で売却できる買い手やタイミングを優先することになります。また、「事業のさらなる成長」を目指すのであれば、自社との相乗効果が期待できる買い手を選ぶことが重要です。
目的が明確であれば、それに合った売却戦略を立てやすくなり、買い手との交渉においてもブレることなく、希望条件の実現に向けて効果的に進めることができるでしょう。売却目的の明確化は、売却後の後悔を防ぎ、経営者自身のセカンドキャリア設計にも影響を与えるため、深く検討することが求められます。
会社売却を成功させる上で、買い手企業との間で「相乗効果(シナジー)」が期待できるか否かは重要なポイントです。シナジー効果とは、M&Aによって企業同士が結合することで、単独で事業を行うよりも大きな成果や価値が生まれることを指します。
例えば、買い手企業が持つ強み(資金力、販売チャネル、技術、ブランド力など)と、売り手企業が持つ強み(特定の技術、顧客基盤、優秀な人材など)を組み合わせることで、新たな事業機会の創出、コスト削減、市場シェアの拡大などが期待できます。
買い手企業は、M&Aによって得られるシナジー効果を重視して買収を検討するため、売り手企業は自社の強みが買い手企業のどのような部分と相乗効果を生み出すかを明確にアピールすることが重要です。相乗効果が期待できる買い手を見つけることで、売却価格の向上や、売却後の事業の発展にもつながる可能性が高まります。
会社売却の成功には、適正な取引金額を検討し、設定することが不可欠です。売却価格は、売り手と買い手の双方にとって納得のいくものである必要があります。
売り手としては、当然ながらこれまでの努力が報われるような高値での売却を望むでしょうが、市場の評価からかけ離れた高額な希望は、買い手候補の選定を難しくし、交渉を長期化させる原因となります。逆に、過度に低い金額を設定してしまうと、本来得られるはずの利益を逃すことになります。適正な取引金額を検討するためには、まず自社の企業価値を正確に評価することが重要です。
これには、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカムアプローチといった複数の評価手法を組み合わせ、多角的に分析することが望ましいでしょう。また、業界の動向、経済状況、買い手の買収意欲なども考慮に入れ、専門家と相談しながら、現実的かつ魅力的な金額を設定することが、円滑な売却交渉と成功への道を開く鍵となります。
会社売却を成功させるためには、適切な売却時期(タイミング)を判断することが極めて重要です。同じ会社であっても、売却時期の違いによって企業価値や売却価格が大きく変動する可能性があります。
一般的に、企業の業績が好調で、売上や利益が順調に成長している時期は、買い手にとって魅力的に映り、より高値で売却できる可能性が高まります。具体的には、過去最高益を達成した直後や、新規事業が成功して収益が拡大している時期などが挙げられます。
逆に、業績が悪化してからでは、企業価値が低下しているため、買い手が見つかりにくくなったり、売却価格が低くなったりする傾向があります。また、経営者の体力や気力が充実しているうちに準備を進めることも大切です。病気や高齢による引退を考えている場合でも、完全に衰えを感じる前に検討を始めることで、精神的に余裕を持って交渉に臨めるでしょう。
さらに、業界再編の動きがある時期や、法改正が有利に働くタイミングなども、売却に適した時期として考慮すべきです。
会社売却を成功させるためには、売却後の経営統合(PMI:PostMergerIntegration)の計画を事前に準備しておくことが重要です。
PMIは、M&Aが完了した後、買い手企業と買収された会社が、組織、システム、文化などをスムーズに統合し、M&Aの目的であるシナジー効果を最大限に引き出すためのプロセスです。売り手企業が売却後の統合計画に積極的に関与し、準備を進めることで、買い手企業はM&A後の事業運営を円滑に進められると判断し、売却交渉においても有利に働く可能性があります。
具体的には、売却後の組織体制、人事制度、ITシステムの統合、主要な従業員の引き継ぎ、企業文化の融合などについて、買い手企業との間で事前に協議し、共通認識を構築しておくことが望ましいでしょう。PMIの準備を怠ると、M&A後に予期せぬトラブルが発生したり、シナジー効果が十分に発揮されなかったりするリスクがあるため、売却後の見通しを立てた上で、入念な準備が必要です。
会社売却を成功させるためには、信頼できる専門家の選定が極めて重要です。
会社売却は、法務、税務、会計、交渉など、多岐にわたる専門知識を要する複雑なプロセスであり、経営者一人で全てを完璧にこなすことは困難です。M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)、弁護士、公認会計士、税理士といった専門家は、それぞれの分野で豊富な経験とノウハウを持ち、会社売却の各段階で適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
例えば、M&A仲介会社は、買い手候補の探索から条件交渉、契約締結までの一連のプロセスを全面的に支援し、売り手と買い手の橋渡し役を担います。専門家を選定する際には、実績や専門分野だけでなく、経営者の売却目的や会社の状況を深く理解し、寄り添ってくれるかどうかを見極めることが重要です。
信頼できるパートナーと協力することで、複雑な手続きを円滑に進め、希望通りの売却を実現できる可能性が高まります。
会社売却を成功させるためには、自社のリスクを正確に把握し、それを買い手候補と適切に共有することが不可欠です。
隠されたリスクや問題点がデューデリジェンスの段階で発覚すると、買い手からの信頼を失い、交渉が不利になったり、最悪の場合、破談になったりする可能性があります。
そのため、売却を検討する早い段階で、自社の財務状況、法務、労務、事業に関する潜在的なリスク(例えば、簿外債務、訴訟リスク、特定の取引先への依存度が高い、従業員とのトラブルなど)を徹底的に洗い出す必要があります。
洗い出したリスクについては、隠蔽することなく、誠実に買い手候補に開示し、その上でどのように対処していくか、あるいは既にどのような対策を講じているかを説明することが重要です。リスクを事前に把握し、適切に共有することで、買い手との間で信頼関係を構築し、円滑な交渉を進めることができるでしょう。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
「赤字の会社でも売却できるのか」という疑問を抱く経営者は少なくありません。結論から言えば、赤字企業でも会社売却は十分に可能です。
買い手企業は、過去の業績だけでなく、将来性や潜在的な価値に注目して買収を検討するためです。例えば、一時的な赤字であっても、特定の高い技術力やノウハウ、独自の顧客基盤、成長市場での将来性、優秀な人材、地理的な優位性など、買い手企業にとって魅力的な強みがあれば、売却の可能性は十分にあります。
買い手企業は、買収後に赤字事業を立て直すことで、自社の事業拡大や新たな事業分野への参入、あるいはシナジー効果による全体的な収益改善を見込むことがあります。また、不採算事業を切り離し、主力事業に経営資源を集中させたいという目的で、赤字事業を売却するケースも存在します。
ただし、赤字の理由やその背景を明確に説明し、将来的な改善計画を具体的に提示できるかどうかが、売却成功の鍵となります。M&A仲介会社などの専門家と相談し、自社の強みや将来性を最大限にアピールする戦略を立てることが重要です。
会社売却を検討する上で、買い手を見つけることは最も重要なステップの一つです。自社にとって最適な買い手を見つけるためには、様々なチャネルを活用し、効率的にアプローチを進める必要があります。以下に、主な買い手を見つける方法を解説します。
買い手を見つける最も一般的な方法の一つが、M&A仲介会社の活用です。
M&A仲介会社は、売り手と買い手の間に立って、両者のマッチングから交渉、契約締結までの一連のプロセスを全面的にサポートします。豊富なM&Aの実績とノウハウを持ち、独自のネットワークやデータベースを通じて、最適な買い手候補を効率的に探索してくれます。
M&A仲介会社は、秘密保持契約のもとで、売り手企業の機密情報を適切に管理しながら、多数の買い手候補にアプローチできます。また、売却価格の算定、条件交渉のサポート、法務・税務に関するアドバイスなど、専門的な視点からきめ細やかなサポートを提供してくれるため、経営者は本業に集中しながら売却を進められます。
特に、中小企業のM&Aにおいては、M&A仲介会社の存在が売却成功の鍵となることが多いです。
会社売却の買い手探しには、公的機関の支援も活用できます。例えば、事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業の事業承継を支援するために国が設置している機関であり、後継者不在に悩む中小企業の経営者に対して、M&Aを含む事業承継に関する相談や情報提供、マッチング支援などを行っています。
これらの機関は、中小企業支援を目的としているため、M&A仲介会社と比較して手数料が安価である場合や、無料で相談できるケースもあります。地域の中小企業診断士や商工会議所なども、M&Aに関する情報提供や専門家への橋渡しを行っていることがあります。公的機関の利用は、費用を抑えつつ、信頼性の高い情報や支援を受けられるというメリットがあります。
金融機関(銀行、証券会社など)や士業事務所(弁護士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所など)も、会社売却における買い手探しやM&Aプロセスを支援する重要な役割を担っています。
金融機関は、M&Aに関する情報やネットワークが豊富であり、顧客企業の中から買い手候補を紹介してくれることがあります。特に、地域に密着した金融機関であれば、地元の企業情報を多く保有しているため、思わぬ買い手候補が見つかる可能性もあります。
また、弁護士は法務面からのリスク評価や契約書の作成・交渉、公認会計士や税理士は財務・税務デューデリジェンスや企業価値評価、税務上のアドバイスなど、M&Aの各段階で専門的なサポートを提供します。これらの専門家は、M&A仲介会社とは異なる視点から買い手探しをサポートしてくれるため、複数のチャネルを組み合わせて活用することで、より最適な買い手を見つけられる可能性が高まります。
近年、M&Aマッチングサイトの利用が活発になっています。M&Aマッチングサイトは、オンライン上で売り手企業が案件を登録し、買い手企業がその案件の中から自社の戦略や条件に合う企業を探して交渉を行うサービスです。
この方法の最大のメリットは、企業自身で案件を探せるため、M&A仲介会社を介する場合と比較して手数料を抑えられる可能性がある点です。また、多くの売り手・買い手が登録しているため、幅広い選択肢の中から効率的に相手を探せる可能性も高まります。
匿名で情報を公開できるサイトもあり、情報漏洩のリスクを軽減しながら買い手候補を募ることが可能です。ただし、M&Aの専門知識がない場合、交渉や手続きを自社で進める必要があるため、専門家のアドバイスを適宜受けるなど、慎重な対応が求められます。
会社売却を成功させるには、適切な時期を見極めることが重要です。
同じ会社でも、売却時期によって企業価値や売却価格が大きく変動する可能性があります。経営者自身の状況、会社の業績、業界の動向など、様々な要因を総合的に判断して最適なタイミングを逃さないようにすることが求められます。
ベンチャー企業やスタートアップ企業において、創業者が投じた資金を回収し、次の事業への再投資や引退後の生活資金とする「イグジット」を目的とする場合、会社売却のタイミングは企業の成長フェーズと密接に関わってきます。
一般的に、企業の成長が見込まれる段階、特に急成長期にある時期が、投資回収を目的とした売却に適したタイミングとされています。この時期であれば、買い手企業は将来の大きな収益拡大を期待して、高い買収価格を提示する可能性が高まります。
具体的には、市場シェアを拡大している、新規事業が成功して収益が拡大している、あるいは競合他社にない独自の技術やサービスを有しているといった状況が挙げられます。会社の業績が最高益を達成した直後や、成長カーブが鈍化する前に売却を検討することで、最大限の投資回収を実現できるでしょう。
ただし、成長が見込めるからこそ、会社を手放すのが惜しいと感じる気持ちとの葛藤も生じるため、経営者自身の明確な意思決定が重要となります。
会社売却に適したタイミングの一つとして、業界再編が活発に進む時期が挙げられます。
業界再編とは、M&Aなどを通じて業界内の企業数が集約され、競争環境が変化していく過程を指します。このような時期には、業界内で生き残りをかけたM&Aが頻繁に行われるため、売却の機会が増え、予想以上に良い条件での売却を期待できる可能性があります。
特に、中小企業の場合、業界再編の波が押し寄せる前に、資本力のある大手企業の傘下に入ることで、業界での生き残りを図るという戦略も考えられます。しかし、業界再編が進み、小規模な会社が統合されていくと、次第に買い手企業が減少し、売却の選択肢が狭まることもあります。
そのため、業界再編の情報をいち早く入手し、その動きが落ち着く前に売却の準備を進めることが、高値での売却や有利な条件でのM&Aを実現するための重要なポイントとなります。
経営者の健康問題も会社売却を検討する重要なタイミングとなります。
長年の経営で培った経験や知識も健康上の理由で経営を継続することが困難になれば事業の継続が危ぶまれる事態に発展しかねません。特に中小企業においては経営者個人の健康状態が会社の経営に直結するケースが多いため体力の衰えや病気の兆候を感じ始めたら早めに会社売却を検討することが賢明です。
経営者の気力体力が充実しているうちに売却の準備を進めることで精神的な余裕を持って交渉に臨めより良い条件での売却を目指すことができるでしょう。逆に病状が進行してしまってからでは売却プロセスを進める上での負担が大きくなり十分な交渉や準備ができないまま不利な条件で売却せざるを得なくなる可能性もあります。
経営者の健康状態の変化をきっかけに会社の将来と自身のセカンドキャリアを真剣に考えることが会社売却の適切なタイミングを見極める上で重要です。
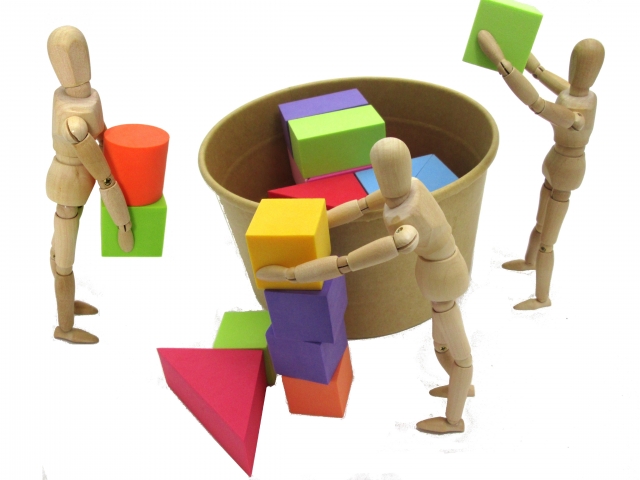
会社売却は、経営者だけでなく、会社の従業員や取引先など、多くの関係者に影響を与えます。売却後の関係者の処遇は、M&Aの成功だけでなく、その後の事業の円滑な運営にも大きく関わるため、事前に十分に検討し、対応策を講じておく必要があります。
会社売却後の経営者の選択肢は、売却の目的や契約内容によって様々です。経営者の中には、売却益を得て完全にリタイアし、自由な時間を楽しむことを選択する人もいれば、新たな事業を立ち上げる「シリアルアントレプレナー」の道を選ぶ人もいます。
また、売却後も引き続き会社に残るケースも少なくありません。
会社を売却した後も、引き続き経営に携わりたいと考える経営者もいます。特に、事業のさらなる成長を目的とした会社売却の場合、買い手企業が旧経営者の知識や経験、人脈を高く評価し、引き続き社長や役員として会社に残ることを要請するケースがあります。
この場合、旧経営者は買い手企業の経営方針に準じることになりますが、これまで培ってきた事業への想いやノウハウを活かし、引き続き会社の成長に貢献できます。ただし、経営権は買い手企業に移るため、売却前とは異なり、意思決定の自由度が制限される可能性があります。
契約内容によって、一定期間の勤務が義務付けられる「ロックアップ」条項が盛り込まれることもあります。
会社売却によって、経営者としての責任から解放され、引退という選択をするケースも多く見られます。
特に、後継者不在の問題を解決するためや、高齢による体力・気力の衰えを理由に会社売却を決断した場合、売却益を元手に第二の人生をスタートさせることが可能です。
長年の経営で負っていた個人保証や経営のプレッシャーから解放され、趣味や家族との時間、あるいは社会貢献活動など、自分の時間を自由に使えるようになるでしょう。セミリタイアやアーリーリタイアを実現し、充実したセカンドライフを送ることは、会社売却の大きなメリットの一つです。
会社売却後、従業員の処遇は経営者にとって非常に気がかりな点です。
一般的に、株式譲渡による会社売却では、会社は法人格を維持するため、従業員の雇用契約はそのまま引き継がれ、原則としてリストラや解雇は行われません。買い手企業は、対象企業の従業員を重要な経営資源と見なすことが多く、彼らのノウハウやスキル、顧客との関係を重視するためです。
しかし、事業譲渡など、M&Aスキームによっては個別の雇用契約の引き継ぎが必要となる場合もあります。また、売却後、買い手企業の経営方針や人事制度が導入され、給与体系や福利厚生、労働条件などが変更される可能性もゼロではありません。
従業員の不安を軽減し、モチベーションを維持するためには、M&Aの目的や売却後の展望、そして自身の処遇について、経営者が直接、誠実に説明し、質問に答えるなど、丁寧なコミュニケーションを心がけることが重要です。
会社売却後、会社は買い手企業の経営方針に従って運営されることになります。
これにより、経営方針や社風、事業内容などに変化が生じる可能性があります。例えば、買い手企業がより大規模な企業であれば、組織体制や業務プロセスが変更されたり、新たなシステムが導入されたりすることが考えられます。
また、重複する事業部門の効率化や、新たな市場への参入など、事業戦略が大きく転換される場合もあります。買い手企業の強力な経営資源を活用することで、売却前には実現できなかった事業規模の拡大や、新たな成長機会を得られる可能性が高まります。
しかし一方で、これまでの企業文化や慣習が大きく変わることにより、従業員が戸惑いを感じたり、取引先との関係性が変化したりする可能性も考慮しておく必要があります。
会社を可能な限り高値で売却することは、多くの経営者が望むことです。そのためには、単に現状の企業価値を評価するだけでなく、戦略的に会社の魅力を高め、買い手にとっての価値を最大化する取り組みが必要です。以下に、高値で売却するための具体的な戦略を解説します。
高値で会社を売却するためには、長期的に安定した顧客基盤を構築していることが重要な戦略となります。
買い手企業は、M&Aによって安定した収益源と将来の成長性を求めています。強固な顧客基盤は、継続的な売上と利益の基盤となるだけでなく、新規顧客獲得にかかるコストを削減し、安定したキャッシュフローを生み出す可能性を示します。
特定の顧客に依存せず、多様な顧客層を確保していることや、顧客との長期的な関係性を築けていることは、企業の安定性と成長性をアピールする上で非常に有利に働きます。顧客満足度を高める取り組みや、リピート率向上施策などを通じて、盤石な顧客基盤を構築することは、企業価値を高め、結果として高値での売却に繋がる重要な要素となるでしょう。
高値で会社を売却するためには、優秀な人材や独自の技術を確保していることが非常に重要な戦略となります。買い手企業は、M&Aを通じて単なる事業の拡大だけでなく、人材や技術といった無形資産の獲得も重視しています。
特定の分野における専門性の高い人材や、市場で競争優位性を持つ独自の技術は、企業の将来的な成長性や競争力を高める源泉となります。
特に、技術革新が激しい業界においては、優れた研究開発力や特許技術が、企業価値を大きく左右する要素となります。また、組織全体に優秀な人材が揃い、組織として機能していることは、買収後の事業運営の円滑さやシナジー効果の創出を期待させるため、買い手にとって魅力的に映ります。
従業員のスキルアップやキャリア形成への投資、働きやすい環境の整備などを通じて、優秀な人材の定着と技術力の向上を図ることが、高値売却に繋がるでしょう。
特定の分野で高い市場シェアを確保していることは、高値で会社を売却するための強力な戦略となります。市場シェアが高いということは、その分野において競合他社に対する優位性やブランド力が確立されていることを意味します。
買い手企業は、市場シェアの高い企業を買収することで、既存事業の強化、新規市場への参入、競争力の向上などを期待します。特に、ニッチな市場であっても独占的な地位を築いている場合や、大手企業が参入しにくい独自のポジショニングを確立している場合は、その希少性から企業価値が高く評価されやすくなります。
市場シェアの高さは、安定した収益基盤と将来的な成長の可能性を示すため、高値売却を実現するための重要なアピールポイントとなるでしょう。
高値で会社を売却するための最も重要な戦略の一つが、業績が好調な時期に売却を検討することです。
企業の業績が伸びており、売上や利益が過去最高を記録しているような時期は、買い手にとって非常に魅力的に映ります。好調な業績は、企業の安定性、成長性、そして将来的な収益性を明確に示す指標となるため、買い手は高い企業価値を認め、より高値で買収に応じる可能性が高まります。
逆に、業績が悪化してから売却を検討すると、企業価値が低下しているため、希望通りの売却価格で売却できないだけでなく、買い手が見つかりにくくなる可能性もあります。そのため、常に自社の業績を把握し、潜在的な成長が見込めるタイミングや、市場環境が好転している時期など、最適な売り時を逃さないよう戦略的に判断することが、高値売却を実現する鍵となります。
高値で会社を売却するためには、自社の強みを明確に把握し、それを買い手候補に対して効果的にアピールすることが不可欠な戦略です。
買い手企業は、M&Aを通じて自社の成長や課題解決に繋がる強みを求めています。単に売上や利益といった数字だけでなく、他社にはない独自の技術、特許、ブランド力、特定のニッチ市場での優位性、優秀な人材、強固な顧客基盤、優れた企業文化、効率的な生産体制など、自社の競争優位となる要素を洗い出し、具体的にアピールすることが重要です。
これらの強みが、買い手企業にとってどのような相乗効果を生み出し、どのようなメリットをもたらすかを具体的に示すことで、企業価値を高め、より高値での売却に繋げることができます。専門家と協力し、企業概要書やプレゼンテーション資料を通じて、自社の魅力を最大限に伝える工夫が求められます。
高値で会社を売却するための戦略として、相乗効果(シナジー)が期待できる買い手を慎重に選定することが挙げられます。単に高値をつけてくれる買い手を探すだけでなく、M&Aによって自社の事業がさらに発展し、新たな価値を創造できるようなパートナーを見つけることが、長期的な成功につながります。
買い手企業が自社と同じ業界であれば、重複する事業を統合することでコスト削減や市場シェアの拡大が期待できますし、異なる業界であっても、互いの技術やノウハウ、販路を組み合わせることで、新たな市場開拓やサービスの拡充が可能になるかもしれません。
買い手候補の事業内容、経営戦略、企業文化などを十分に調査し、自社との間でどのようなシナジー効果が生まれるかを具体的に検討することで、買い手もM&A後の成功を具体的にイメージしやすくなり、より積極的な買収姿勢を示す可能性があります。これにより、売却価格の向上にも繋がるでしょう。
高値で会社を売却するための戦略の一つとして、「アーンアウト条項」の活用が挙げられます。
アーンアウト条項とは、M&Aの売却価格の一部を、売却後の対象会社の業績に応じて変動させる条項のことです。例えば、売却後数年間の売上や利益目標を達成した場合に、追加で売却代金が支払われるという形式です。
この条項を活用することで、売り手は将来の業績向上に対する自身を買い手に示すことができ、買い手は買収後のリスクを軽減しながら、将来の成長性を考慮した高い買収価格を提示しやすくなります。特に、将来性はあるものの、現状の業績が芳しくない企業や、特定の技術や開発中の製品に大きな期待がかかる企業などにおいて、アーンアウト条項は高値売却を実現するための有効な手段となり得ます。
ただし、達成目標の設定や、目標未達成の場合の取り決めなど、契約内容を十分に精査することが重要です。
高値で会社を売却するための重要な戦略の一つに、信頼できるM&A仲介会社の選定があります。
M&A仲介会社は、買い手候補の探索から交渉、契約締結に至るまで、M&Aプロセス全体を専門的な知識とノウハウでサポートします。経験豊富な仲介会社は、市場の動向や企業価値評価の知識に長けており、自社の強みを最大限に引き出し、適切な買い手を見つけることで、より高値での売却を実現できる可能性を高めてくれます。
また、買い手との交渉において、売却価格だけでなく、従業員の処遇や契約条件など、多岐にわたる項目で売り手側の利益を最大限に守るよう尽力します。仲介会社を選定する際には、実績や専門分野、担当アドバイザーとの相性などを慎重に見極めることが重要です。信頼できる仲介会社は、売却成功への強力なパートナーとなるでしょう。
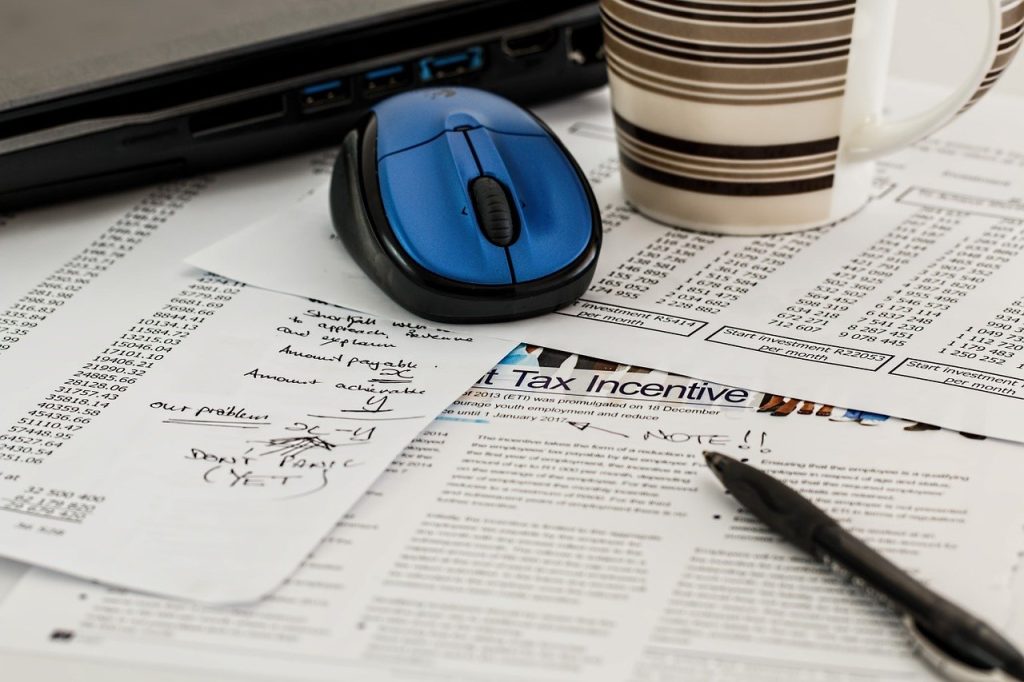
会社売却は、売却益を得られるという大きなメリットがある一方で、様々な税金や費用が発生します。
これらのコストを事前に把握し、資金計画に含めておくことが、売却後の手元に残る金額を正確に把握し、後悔のない売却を実現するために不可欠です。売却方法によって発生する税金の種類や税率が異なるため、注意が必要です。
会社売却における税金は、選択する売却方法(M&Aスキーム)によって大きく異なります。主な売却方法である株式譲渡と事業譲渡では、それぞれ課される税金の種類や税率が異なるため、事前に理解しておくことが重要です。合併についても、税務上の取り扱いがあるため、確認が必要です。
株式譲渡は会社売却で最も多く用いられる方法であり、税務面でのメリットも大きいとされています。
株式譲渡の場合、売り手である会社の株主個人が保有する株式を買い手企業に譲渡して得た所得は譲渡所得とみなされます。この譲渡所得に対しては申告分離課税が適用され、所得税と住民税、そして復興特別所得税(2037年までの時限措置)を合わせた税率約20.315%が課せられます。
この税率は個人の所得税率(累進課税)とは異なり、所得額に関わらず一律であるため、多額の売却益を得た場合でも税負担が比較的軽減されるという特徴があります。ただし、売却益から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が課税対象となる点に注意が必要です。
事業譲渡は、会社が営む事業の一部または全部を買い手企業に譲渡する方法であり、税務面では株式譲渡とは異なる取り扱いとなります。事業譲渡の場合、売却益は売り手である会社に帰属し、法人税が課せられます。法人税の税率は、会社の規模や所得額によって異なりますが、一般的に約20%〜30%程度です。
また、事業譲渡では、譲渡対象となる資産(土地、建物、機械設備、営業権など)の種類によっては、別途消費税が課される場合があります。例えば、土地の売却は非課税ですが、建物や機械設備、営業権などの売却には消費税が発生します。
そのため、消費税の納税義務が発生したり、買い手企業から受け取る消費税額を考慮した売却価格を設定したりする必要があるため、株式譲渡と比較して税務上の手続きが複雑になる傾向があります。事前に税理士と相談し、正確な税負担を把握しておくことが重要です。
合併は、複数の会社が一体となって一つの会社になる組織再編の手法であり、税務上の取り扱いも複雑です。合併には、一定の要件を満たすことで税制上の優遇措置が受けられる「適格合併」と、そうでない「非適格合併」があります。適格合併の場合、繰越欠損金の引き継ぎや資産の簿価引き継ぎなど、税金面で優遇されることが多いです。
一方、非適格合併の場合、資産の時価評価に伴う含み益への課税や、株主へのみなし配当課税が発生するなど、多額の税金が課される可能性があります。合併の目的や当事会社の状況によって税務上の影響が大きく異なるため、合併を検討する際には、事前に税理士や弁護士などの専門家と綿密に相談し、最適なスキームを選択することが不可欠です。
会社売却を進める上で、税金以外にも様々な経費が発生します。これらの経費は、売却プロセスを円滑に進めるために必要不可欠なものであり、事前に予算に組み込んでおくことが重要です。
主な経費としては、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)への手数料、弁護士や公認会計士、税理士などの専門家への報酬が挙げられます。M&A仲介手数料は、一般的に成功報酬制が採用されており、売却が成立した場合に、売却価格に応じて一定の料率(レーマン方式など)で算出されます。この他にも、企業価値評価費用、デューデリジェンス費用、契約書作成費用、登記費用など、多岐にわたる費用が発生する可能性があります。
これらの費用は、会社の規模や売却の複雑さによって大きく変動するため、事前に専門家に見積もりを依頼し、全体像を把握しておくことが大切です。
会社売却は経営者にとって人生を左右する大きな決断であり、多岐にわたる専門知識と慎重な準備を要する複雑なプロセスです。後継者問題の解決、創業者利益の獲得、事業のさらなる発展、個人保証の解消など、多くのメリットが期待できる一方で、希望条件での売却が難しい、従業員の退職リスク、情報漏洩の危険性、税金や費用が発生するといった注意点も存在します。
会社売却を成功させるためには、売却目的の明確化、適切な売却時期の判断、自社の強みとリスクの正確な把握、そして何よりも信頼できるM&A仲介会社などの専門家を選定し、密に連携しながら進めることが不可欠です。本記事で解説した会社売却の全体像と具体的なポイントを参考に、ご自身の会社にとって最適な売却戦略を立て、後悔のないM&Aを実現されることを願っています。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください