
事業売却は、特定の事業を第三者に譲渡するM&Aの手法です。この記事では、事業売却の基本的な意味から、会社売却との違い、そして売り手と買い手の双方にとってのメリットとデメリットについて詳しく解説します。事業売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
\成約例や支援の特徴・流れを紹介/

事業売却とは、企業が特定の事業の全部または一部を、他の会社や個人に対して売却する行為を意味します。
これはM&A(企業の合併・買収)の手法の一つとして位置づけられ、法律上は「事業譲渡」と称されることが一般的です。事業を売却する目的は多岐にわたり、大手企業では「選択と集中」の戦略として、不採算事業やノンコア事業を切り離し、そこで得た資金を成長分野に再投資し、組織の再編と再生を図る事例が見られます。
また、中小企業においては経営者の高齢化や後継者不在が深刻化する中で、事業の継続を目的とした有効な手段として活用されています。
事業売却では売却対象となる資産や負債、さらにはブランド、流通販路、従業員などが個別の取引行為として移転・承継されます。

事業売却と事業譲渡は一般的に同じ意味で使用されることが多く、事業売却の法律上の正式名称が「事業譲渡」であり、実務上でもこの名称が頻繁に使われています。
実質的な意味合いに違いは無く、どちらも会社の一部または全部の事業を他社に売却するという行為を指しています。
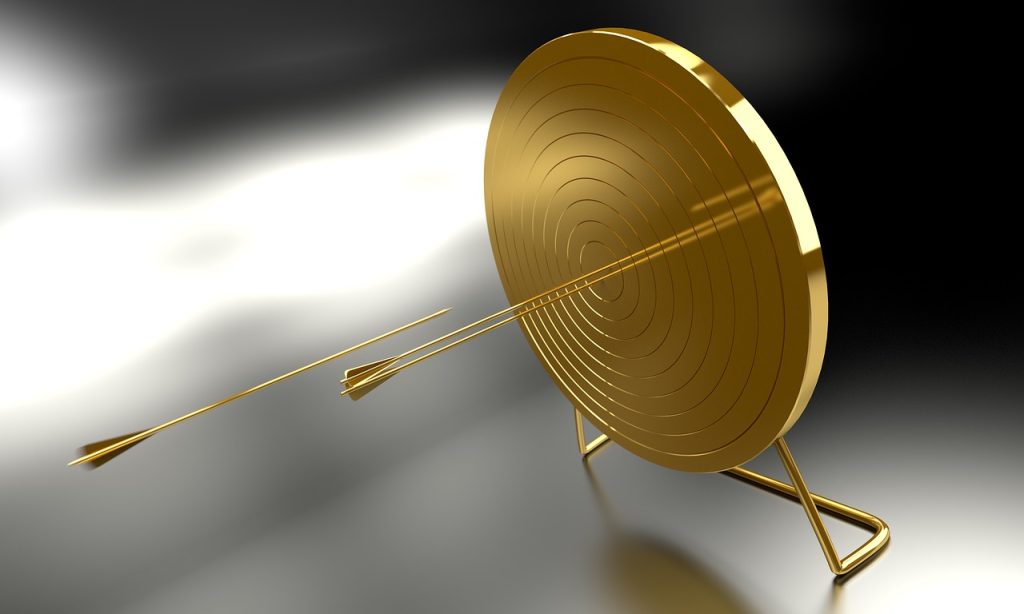
事業売却と会社売却は、M&Aの手法として似ているように見えますが、そのスキームと売却対象において明確な違いがあります。
事業売却は、会社が持つ特定の事業の一部または全部を第三者に売却することを指し、売却対象は事業そのものやそれに付随する個別の資産・負債となります。
一方、会社売却は主に株式譲渡を指すのが一般的で、会社の株式を売却することで会社の経営権そのものを第三者に譲渡するスキームです。売却対象は会社全体であり、株式の売買を通じて会社が包括的に買い手に引き継がれるため、個別の資産や負債の移転手続きは不要です。
会社売却が比較的シンプルな手続きで済むのもここにあります。また、税務上の違いもあり、事業売却では消費税の課税対象となる資産が含まれる場合があるのに対し、会社売却(株式譲渡)は消費税の対象外となります。このように、売却の対象、経営権の移転の有無、手続きの複雑さ、税務上の取り扱いなど、会社売却と事業売却には重要な違いが存在します。
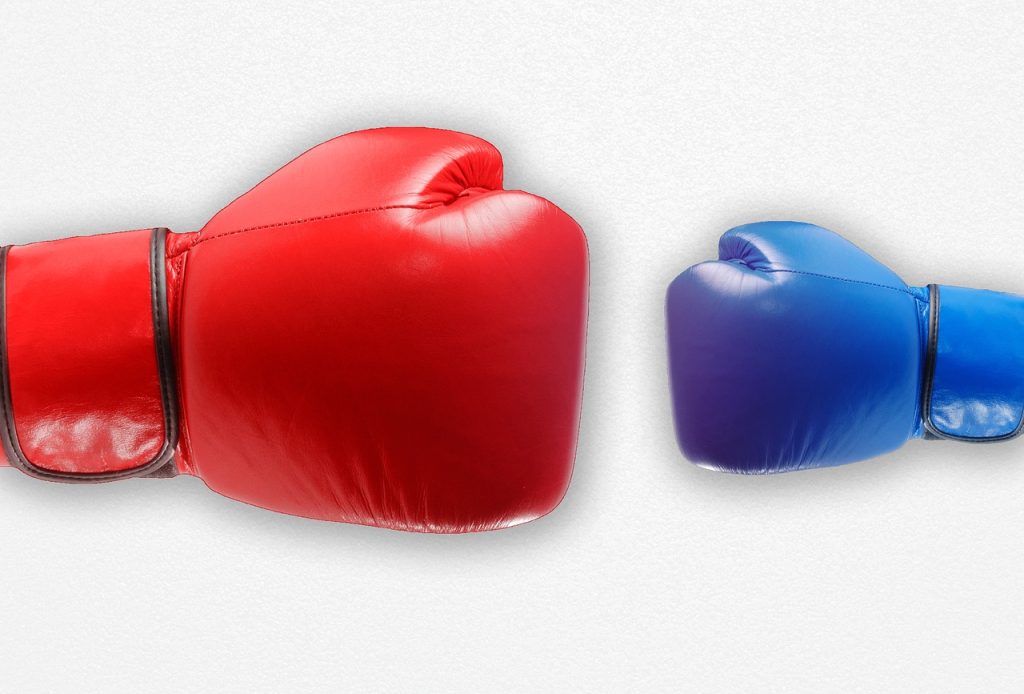
事業売却を検討する際には、メリットとデメリットを総合的に評価し、自社にとって最適な判断を下すことが重要です。
売却側(売り手)にとっての事業売却のメリットは複数存在します。
事業売却は会社全体を売却する会社売却とは異なり、特定の事業部門のみを切り離して売却する手法です。そのため事業を売却した後も、売却した会社そのものは存続し経営権は引き続き維持できます。
社名や株主構成、住所といった会社の基本的な情報は変わることがありませんし、売却した事業に携わっていた従業員についても、配置転換などで継続して雇用することが可能となります。
不採算事業や成長が見込みにくいノンコア事業を切り離すことで、これまで分散していた資金、人材、設備といった経営資源を、企業の成長を牽引する主力事業に集約することが可能です。
例えば赤字事業を売却して得た資金を、黒字事業や将来性のある分野に再投資することで企業はより効率的な組織体制を構築し、迅速な事業拡大を目指すことができます。
このように、事業売却は企業が「選択と集中」の戦略を実行し、事業構造を最適化するための重要な選択肢となり得るのです。
事業を売却することで売却価格から譲渡対象資産の簿価を差し引いた利益が発生した場合、これを会社資金として得ることができます。この利益は新たな事業への投資、既存事業の設備拡充、または財務体質の改善など多岐にわたる用途に活用することが可能です。
特にベンチャー企業にとっては、IPO(新規株式公開)に代わる、より短期的なイグジット(出口戦略)として譲渡益を次のビジネスへの投資資金とすることを目的とするケースも増えています。
ただし、譲渡益には法人税が課税されるため、事前に税金負担を考慮した上で資金計画を立てることが重要です。
事業売却は、株主総会の特別決議によって実行が可能です。
会社法において、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合に要求される決議方法であり、通常決議よりも高い承認要件が求められます。具体的には、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。
ただし、譲渡する事業の帳簿価額が譲渡企業の総資産の20%以下である場合など、取引の重要性が低いと判断される「簡易の事業譲渡」に該当する際は、株主総会の特別決議は不要となり、取締役会決議のみで進めることが可能です。
また、他の会社から事業のすべてを譲り受ける場合、譲受けの対価として交付する財産の帳簿価額が、譲受会社の純資産の20%を超えない場合も、簡易の事業譲受けに該当し、株主総会の決議は不要となります。
購入側(買い手)にとっての事業売却のメリットは、主に以下の点が挙げられます。
事業売却において購入側(買い手)が得られるメリットの一つは、譲り受ける事業範囲を自由に選択できる点です。株式譲渡のように会社全体を丸ごと引き継ぐ場合、不要な資産や負債、さらには売り手企業が抱える潜在的なリスクまで包括的に承継することになります。
しかし、事業売却では買い手が必要とする特定の事業部門や、その事業に関連する資産(例えば、機械設備、特許、顧客リストなど)を個別に選んで取得することが可能です。
不要な負債や将来のリスクを回避しつつ、自社の経営戦略に合致する事業や資産のみを効率的に取り込むことができるため、買収後の事業統合を円滑に進め、企業価値の向上をより確実に目指すことができます。
事業売却において購入側(買い手)が得られる税務上の優遇措置として、特に注目されるのが「のれん」の損金計上です。買い手が支払った買収対価が、譲り受けた資産から負債を差し引いた純資産額を上回る場合、その差額は「のれん」として計上されます。
この「のれん」は、税務上、『資産調整勘定』として原則5年間の償却が認められており、これにより買い手企業の課税所得が減少し、結果として法人税の負担を軽減する節税効果を期待できます。また、株式譲渡ではのれんを損金計上できないため、この点は事業売却の買い手にとって有利な点となります。
さらに、取得した減価償却資産や棚卸資産も、新たな取得価額で減価償却や原価算入ができるため、税務上のメリットを享受できる場合があります。
売却側(売り手)にとっての事業売却のデメリットはいくつか存在し、リスクとして認識しておく必要があります。
事業売却は、株式譲渡と比較して、売り手側の税金負担が大きくなる可能性があります。
事業売却で得られる譲渡益は売却側の法人所得として扱われ、法人税の課税対象となり、法人税の実効税率は企業の規模や所得によって異なりますが一般的に約30%前後が目安とされています。
これに対し、株式譲渡で個人株主が得る譲渡所得に課される所得税と住民税を合わせた税率は、約20.315%とされています。
ただし、事業売却によって譲渡益が出たとしても、他の事業で損失が出ている場合は相殺されるため、一概に税負担が重いとは言えません。
税務上の取り扱いは複雑であり、多額の税金が発生する可能性があるため、事前に税理士や公認会計士に相談し、適切な税金対策を講じることが重要です。
事業売却は、株式譲渡と比較して契約の手続きが複雑であり、手間と時間を要するデメリットがあります。
会社売却としての株式譲渡は、株式の移転のみで完了するため比較的シンプルですが、事業売却は事業を構成する個々の資産(不動産、機械設備、在庫)や負債、取引先との契約、従業員の雇用契約などを一つずつ個別に承継する手続きが必要です。
例えば、買い手が事業に必要な許認可を新たに取得し直す必要がある場合や、不動産を含む場合は登記手続きも必要となるなど、通常のM&Aにはないプロセスが発生し、手続きがより煩雑になる傾向があります。
これらの手続きは売り手と買い手の双方で多くの書類作成や交渉、関係者への説明や同意を得る作業が伴うため、完了までに長期間を要する傾向があります。
事業売却の契約には、会社法に基づき、売り手が譲渡した事業と同一の事業を一定期間(原則20年間、特約で最長30年間まで延長できますが、実務では多くの場合5〜10年で設定されることが多い)、一定地域(譲渡した事業の地域的範囲)において行わないとする「競業避止義務」が課されることが一般的です。
これは、買い手が取得した事業の価値を保護し、売却によって得たノウハウや顧客関係が競合に利用されることを防ぐ目的があります。
売り手にとっては、将来的に特定の事業分野での再参入や類似事業の展開が制限される可能性があるため、今後の事業戦略を慎重に検討する必要がある契約上の制約となります。
購入側(買い手)にとって、事業売却にはいくつかのデメリットやリスクが存在します。
事業売却は、売り手だけでなく、購入側(買い手)にとっても手続きに多大な時間と手間がかかるデメリットがあります。会社売却(株式譲渡)が株式の移転のみで比較的簡潔に済むのに対し、事業売却では、譲り受ける個々の資産(不動産、機械設備、在庫など)や負債、そして取引先との契約、従業員の雇用契約などを、一つずつ個別に承継する手続きが必要です。
例えば、事業に必要な許認可の再取得、不動産の登記変更、取引先との新規契約の締結など、多岐にわたる契約や手続きが発生します。これらの作業には、買い手側の担当者が多くの時間と労力を割く必要があり、特に規模の大きな事業の売却では、買収完了までに長期間を要する傾向があります。
この手続きの煩雑さは、買い手にとって事業売却を選択する際の大きなハードルの一つとなり得ます。
事業売却における購入側(買い手)のデメリットとして、消費税の課税が挙げられます。
事業売却は課税取引とみなされるため、譲渡される資産の中に消費税の課税対象となるものが含まれている場合、買い手はその消費税を負担する必要があります。具体的には、土地を除く建物や機械設備などの有形固定資産、特許権や商標権、ソフトウェアなどの無形固定資産、棚卸資産、そして「のれん」などが課税対象となります。
これらの資産の譲渡対価に対して、消費税率(現在10%)が適用されるため、買収金額が大きい場合は、消費税の負担も相応に大きくなる可能性があります。消費税は利益に対して課される法人税とは異なり、たとえ事業譲渡による利益がマイナスであっても課税されるため、買い手は事前に消費税の負担額を正確に把握し、資金計画に含める必要があります。
ただし、消費税は売り手が買い手から徴収して税務署に納付する形式であり、買い手は仕入税額控除の適用を受けられる場合があります。
購入側(買い手)にとっての事業売却のデメリットの一つとして、譲り受けた事業に関連する新たな許認可の取得が必要となる場合がある点が挙げられます。会社売却(株式譲渡)では、会社の法人格がそのまま存続するため、通常、許認可や免許はそのまま引き継がれます。
しかし、事業売却の場合は、事業の主体が変わるため、売り手が保有していた許認可や免許が自動的に買い手に引き継がれるわけではありません。そのため、買い手は、譲り受けた事業を継続するために必要な許認可を、改めて行政機関などから取得し直す必要があります。
この再取得の手続きには、時間と費用がかかるだけでなく、事業内容によっては取得が困難な場合や、新規取得までの期間中に事業活動が制限されるリスクも存在します。
したがって、事業売却を検討する際には、対象事業に必要な許認可の種類と、その取得の可能性や手続きにかかる期間を事前に十分に確認することが重要です。

事業売却には、売り手と買い手の双方に税金が発生します。
事業売却における売却側には、主に法人税と消費税が課税されます。事業売却によって利益が発生した場合、その譲渡益は法人所得の一部として扱われ、法人税の課税対象となります。法人税には、法人税本体の他に、地方法人税、法人住民税、事業税が含まれ、これらの合計税率はおよそ30%前後が目安です。
譲渡益は、売却金額から譲渡した資産の簿価と負債の差額を差し引いて計算されます。例えば、売却対象事業に利益が出ている場合は、この譲渡益に対して法人税が課税され、逆に売却損が生じる場合は課税されません。また、売却側は、土地などの非課税資産を除いた課税対象資産の譲渡に対して消費税を徴収し、税務署に納付する義務を負います。
消費税は買い手が負担するものですが、売り手が徴収・納付する形になります。
このように、事業売却の際には、利益に対する法人税と、課税対象資産に対する消費税という二種類の税金が発生するため、事前に税務上の影響を十分に理解しておくことが重要です。
事業売却における購入側(買い手)には、主に消費税が課税されます。
事業売却は資産の個別承継を伴うため、土地を除く有形固定資産(建物、機械装置など)、無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェアなど)、棚卸資産、そして「営業権(のれん代)」といった消費税の課税対象資産に対して消費税が課されます。消費税率は原則として10%であり、買収金額が大きくなるほど、この税金負担も増大します。
ただし、土地や有価証券、売掛金・貸付金などの債権は消費税の非課税資産です。消費税は売り手が買い手から徴収し、税務署に納付する義務を負いますが、実質的な負担は買い手側が負うことになります。また、事業譲渡の対象に不動産が含まれる場合には、不動産取得税や登録免許税も発生する可能性があります。
不動産取得税は原則として固定資産税評価額の4%が課税され、登録免許税は登録や許可の申請の際に発生します。これらの税金は、買い手にとってM&Aの総コストに影響を与えるため、事前に税理士などの専門家と連携し、正確な税金計算を行うことが不可欠です。

事業売却を行う場合の流れ、手続きに関しては以下の順に進めていきます。
事業売却を行う上で、まず最初に行うべき重要なステップは、自社のどの事業を売却するのかを明確に決定することです。自社の経営戦略に基づき、不採算事業の整理、将来的な投資額の増加が見込まれる成長事業の売却、あるいはノンコア事業の切り離しなど、様々な理由から行われます。
売却する事業を特定する際は、単に現在の収益性だけでなく、今後の市場動向や自社の経営資源の配分、将来の展望なども考慮に入れる必要があります。
売却対象事業が決定した後には、その事業に関連する財務情報を詳細に整理しておきましょう。
具体的には、事業別の貸借対照表や損益計算書などを作成し、売却対象事業の収益性、資産状況、負債状況などを明確に把握する必要があります。
この準備は、後の買い手探しやデューデリジェンスのプロセスにおいて、正確な情報提供とスムーズな交渉を進める上で極めて重要です。
買い手を探す方法としては、主に以下の2つのアプローチが考えられます。1つ目は売り手が直接売却の打診を行う方法、2つ目はM&A仲介会社やM&Aプラットフォームを活用する方法です。
この方法の主な特徴は、仕入先や得意先といった既存の取引関係にある企業や、経営者同士が顔見知りである企業など、既に信頼関係が構築されている相手に対して直接アプローチする点にあります。
最大のメリットは仲介者が存在しないため、M&A仲介会社に支払う手数料などのマージンを節約できることです。
また、経営トップ同士が直接交渉を行うことで、意思決定のスピードが上がり、プロジェクトが迅速に進展する可能性もあります。
しかし買い手候補の数が限られる可能性や、売却価格の交渉において客観的な評価を得にくいといったデメリットも存在するため、この方法を選択する際には、メリットとデメリットを慎重に比較検討することが重要です。
M&A仲介会社やM&Aプラットフォームの活用は、事業売却において買い手を探す上で非常に有効な方法です。
M&A仲介会社は多くのM&A案件を取り扱っており、幅広いネットワークを通じて、多数の買い手候補企業に事業名を明かさないまま初期的な売却の打診を行うことが可能です。
これにより、複数の買い手候補から提案を受けることで、オークション形式のように売却価格の上昇効果が期待できるというメリットがあります。
また、法務、財務、税務など専門的な知識を持つM&Aアドバイザーが交渉をサポートするため、複雑な手続きを円滑に進めることができます。
M&Aプラットフォームは買い手と売り手がオンライン上で案件情報を登録し、マッチングを行うシステムであり、仲介会社に比べてシステム面での効率化が図られているため、成約手数料が比較的安価であるという特徴があります。
例えば、譲渡を希望する企業は無料で登録できるプラットフォームも存在し、買い手企業が負担する手数料も一般的な仲介会社より安価なケースが見られます。
M&Aプラットフォームでは、掲載されているM&A案件の一覧から自社に合った譲渡案件を検索できるため、より広範な買い手候補の中から最適なパートナーを見つけ出すことが可能になります。
基本合意とは、最終契約を締結する前に事業売却に関する基本的な事項を書面で確認するものであり、「LOI(Letter of Intent)」や「MOU(Memorandum of Understanding)」と呼ばれることもあります。
この段階で合意に盛り込むべき内容は多岐にわたりますが、主なものとしては事業売却のスキーム、譲渡金額、対象となる主な資産や負債の範囲、従業員の引き継ぎ条件、そして事業譲渡契約書の締結日やクロージング日の目安などが挙げられます。
基本合意書に法的拘束力を持たせないことが一般的ですが、これを締結することでその後のデューデリジェンスや最終契約に向けた交渉がスムーズに進み、事業売却の成功確率を高めるメリットがあります。
買い手にとっては、独占交渉権の獲得や買収価格の上限設定、スケジュールの明確化といったメリットがあり、売り手と買い手の双方にとって、今後の交渉を円滑に進めるための重要な土台となるのです。
デューデリジェンス(DD)とは、M&Aにおける買い手側が、買収対象事業のリスクを詳細に把握し、権利移転手続きなどの準備を行う目的で実施する事前監査のことです。
事業売却において、最終的な事業譲渡契約を締結する前に必ず行われる重要な手続きの一つです。
デューデリジェンスは、対象事業の様々な側面を多角的に検証するために、財務DD、税務DD、法務DD、ビジネスDD、人事DD、システムDDなど、複数の分野に分類して実施されます。
例えば、財務DDでは対象事業の収益性や資産・負債の状況を詳細に分析し、税務DDでは過去の税務処理に問題がないか、将来的な税務リスクがないかなどを確認します。
事業売却の場合、会社売却と比較してデューデリジェンスの範囲は対象事業のみに絞られるため、より集中的な調査となります。
売り手としては、デューデリジェンスのプロセスで買い手から求められる膨大な資料を迅速に準備し、マネジメントインタビューと呼ばれる質疑応答に適切に対応する必要があります。
事業譲渡契約書の締結は、事業売却プロセスにおける最終的な合意形成の段階です。
この契約書の内容は、当事者の合意に基づいて自由に定めることができる部分が多いですが、会社法において競業避止義務や株主総会の特別決議に関する規定など、一部法的な規制が設けられています。
主な記載事項としては、
・譲渡の対象となる事業の範囲
・対象となる資産、負債の詳細
・譲渡対価の金額
・譲渡の期日(クロージング日)
・譲渡対象資産等の移転手続きに関する事項
・売り手の競業避止義務
・M&A契約で一般的に定められる表明保証やコベナンツなどの条項
が挙げられます。
事業譲渡契約書を締結するためには、売り手と買い手のそれぞれで社内における機関決定が必要です。
売り手側は、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合、会社法に基づき株主総会の特別決議が必要となります。
ただし、譲渡する事業の帳簿価額が総資産の一定割合以下である「簡易事業譲渡」に該当する場合は、株主総会の特別決議は不要となる例外規定も存在します。
一方、買い手側も事業の全部を譲り受ける場合は株主総会の特別決議が必要となることがありますが、一部の譲受であれば不要となる場合が多いです。
金額的な重要性に応じて、取締役会決議などを経て事業譲渡契約書を締結することになります。
事業譲渡契約書を締結した後も、事業売却は完了ではありません。
契約書を締結しただけでは個別の契約や法的地位が自動的に移転するわけではないため、実際に事業を買い手に移転させ、関係各所への届出を行うための詳細な手続きが必要となります。
具体的には、事業の買い手は取引先との既存の契約を個別に巻き直し、新たな契約を締結する必要があります。また、譲り受けた事業を継続するために必要な許認可を改めて行政機関などから再取得することも求められます。
例えば、飲食業であれば飲食店営業許可、建設業であれば建設業許可など、事業内容によって必要な許認可は多岐にわたります。さらに、不動産を伴う事業譲渡の場合には不動産の登記変更手続きも必要となります。
売り手はこれらの個別の契約や地位の移転が円滑に行われるよう、買い手に対して積極的に協力する義務があります。これらの手続きは、多大な時間と労力を要し、関係者への説明や同意を得る作業も伴うため、事業売却をスムーズに完了させるためには、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが重要です。
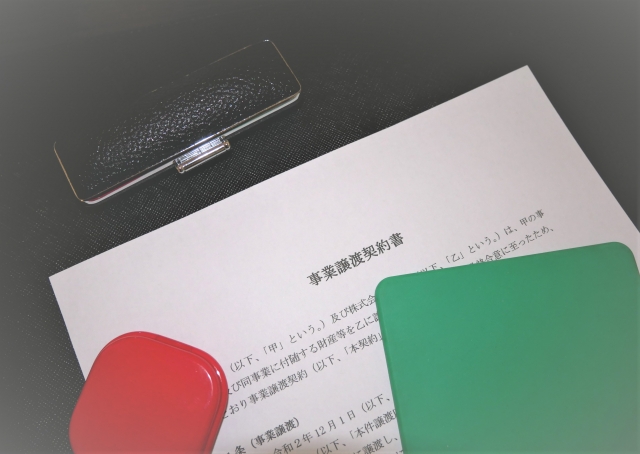
ここでは事業売却の成功例を3つ紹介します。
2021年8月、大手音響メーカーであるオンキョーホームエンターテイメントは上場廃止となりました。2020年3月末、2021年3月末と2期連続の債務超過で東証の廃止基準に該当していたためやむを得ないことですが、あわせて業績向上を目指す発表を行いました。
それがシャープ、VOXXへの、主力事業であるAV事業の売却でした。売却価額は33億円以上となりました。この事業売却により、同事業の生産部門をシャープが、販売部門をVOXXが担当し、オンキョーのブランド名は維持されました。
財務状況の悪化から、企業が本業を売却することでブランドの維持を図った事例です。買収側もそれぞれの特性を活かし、事業拡大に成功しています。
クレイテックワークスは、プロフェッショナルエージェンシー事業を展開する企業です。30万人以上のプロフェッショナルと25,000社以上のクライアントをマッチングして、映像やゲーム、Webなどでのウィンウィンの関係構築を目指しています。
2019年9月、同社はインタラクティブブレインズ社からの事業譲渡を受けました。売却事業の内容は3DCGアバターやVR、コンテンツ開発などです。買い手側の事業拡大のねらいを達成するために、積極的に事業譲渡を求めた事例です。
2018年4月、株式会社オーネットは、親会社である楽天から、「楽天ウェディング」というウェディング事業の売却を受けました。売却価額は公表されていません。
楽天ウェディングは、結婚式の準備に関する情報などを提供するWeb事業を展開していました。披露宴の会場や結婚指輪の検索サービスなども充実し、ユーザからも好評を得ていました。この事業売却で、結婚情報サービス事業を展開するオーネットは、事業領域を広げることに成功しました。
親会社の組織整理のねらいも満たしつつ、グループ企業間で事業売却が行われた事例です。
事業売却は、特定の事業を売却することで経営資源の集中や資金獲得など多くのメリットを享受できるM&A手法です。会社売却とは異なり、会社全体ではなく一部の事業に限定されるため、経営権を維持しつつ事業構造を最適化したい場合に有効な選択肢となります。
しかし、事業売却には複雑な手続きや税務上の注意点、譲渡後の事業活動の制限といったデメリットも存在します。これらのリスクを最小限に抑え、円滑に売却を進めるためには、M&A仲介会社や弁護士、税理士などの専門家から適切なサポートを受けることが不可欠です。
事業売却を検討する際は、メリットとデメリットを総合的に評価し、自社の状況に合わせた戦略を立てることが成功への鍵となります。
ウィルゲートが目指すのは、売り手様、買い手様、双方に納得感のあるM&Aです。M&Aがお客様の目的やご希望に合致しない場合、無理にM&Aをすすめることは絶対にありません。
M&Aで思わぬ失敗をしないためにも、まずは一度、ウィルゲートM&Aにご相談いただければ幸いです。
M&Aが解決策として見込める場合、15,100社以上の経営者とのネットワークから、最適なマッチングを迅速にご提示させていただきます。
成約実績は2年で50件以上、完全成功報酬型で着手金無料ですので、まずはお気軽にご相談ください!
ご相談・着手金は無料です。
売却(譲渡)をお考えの際はお気軽にご相談ください